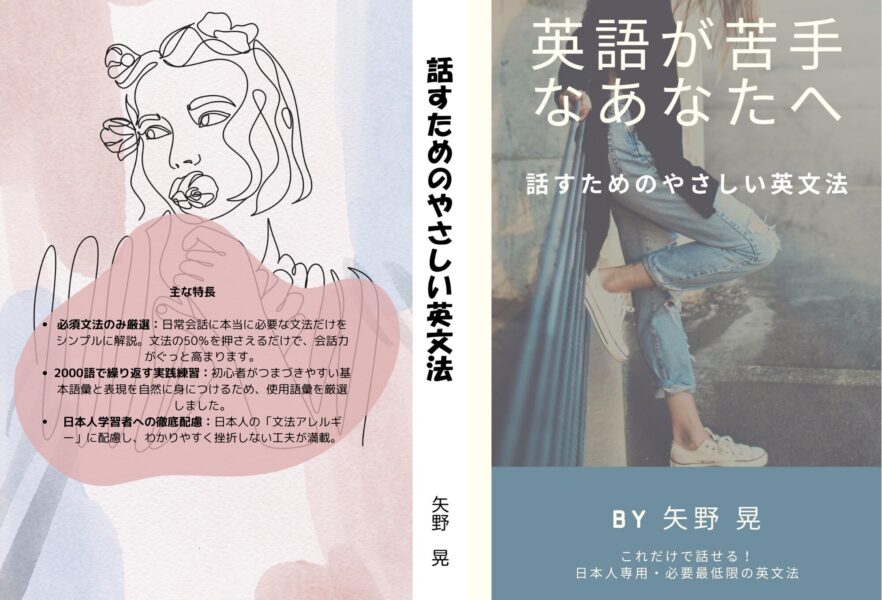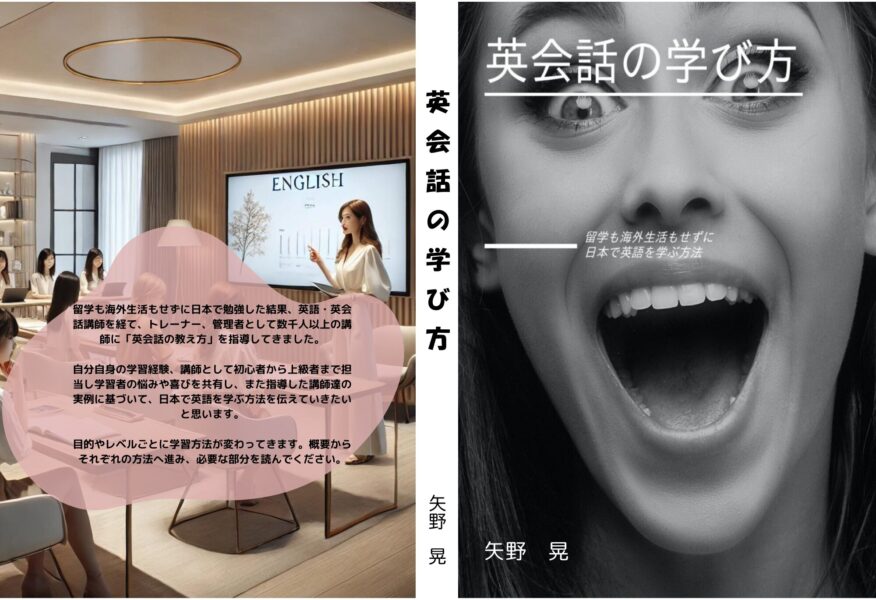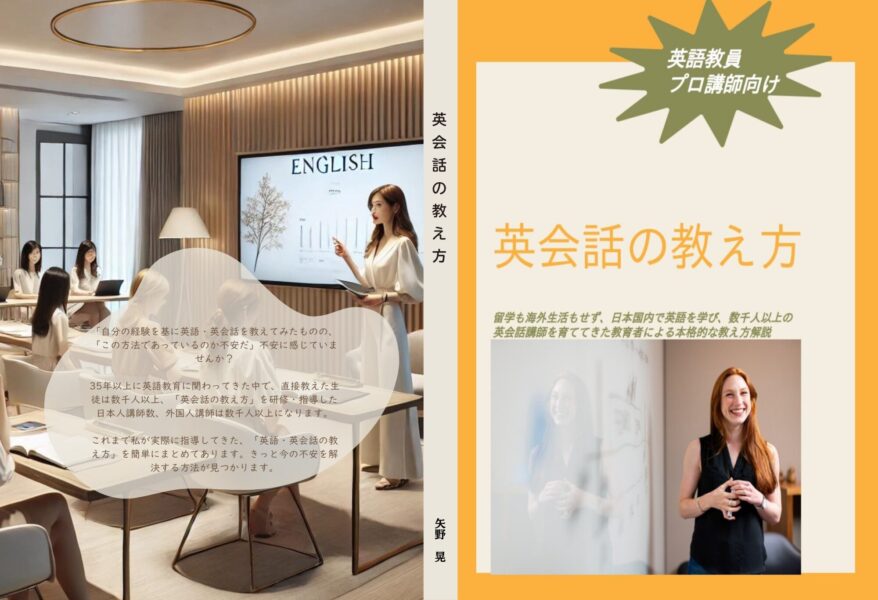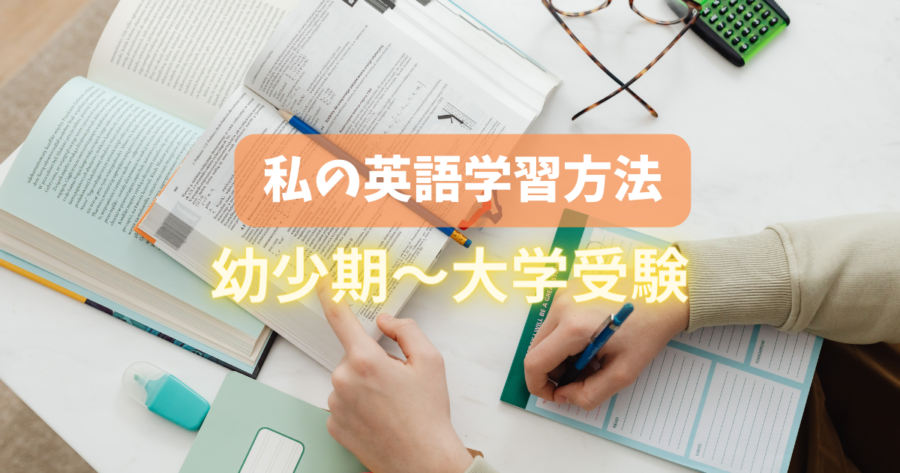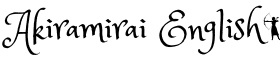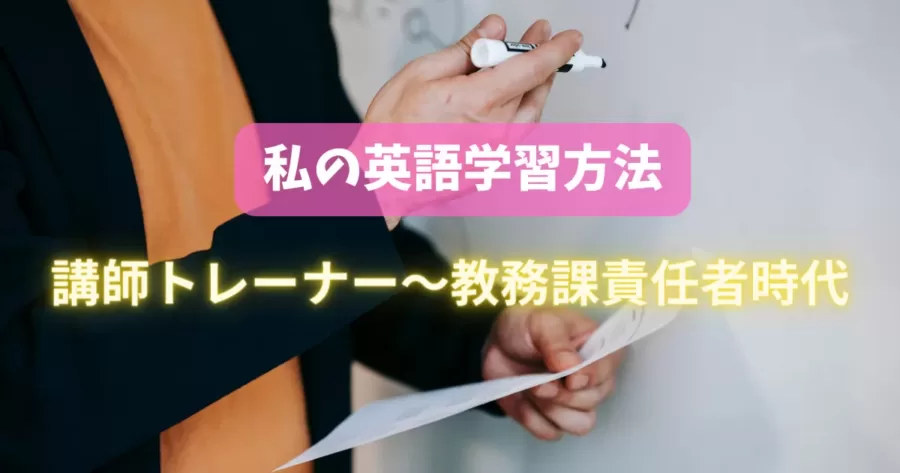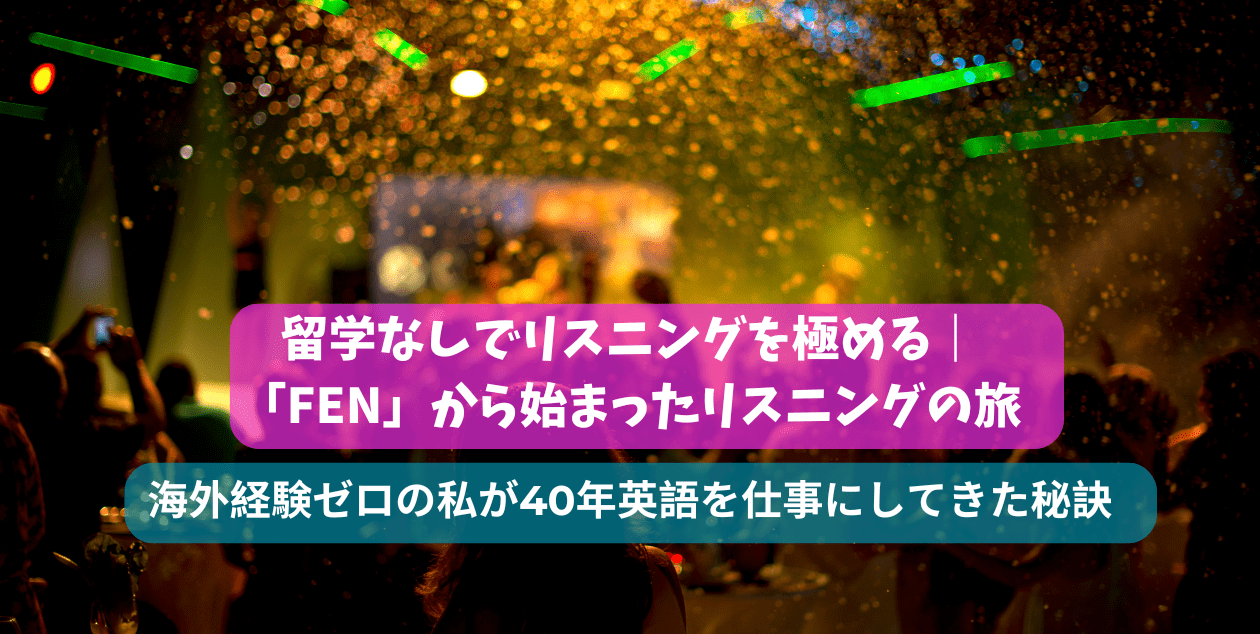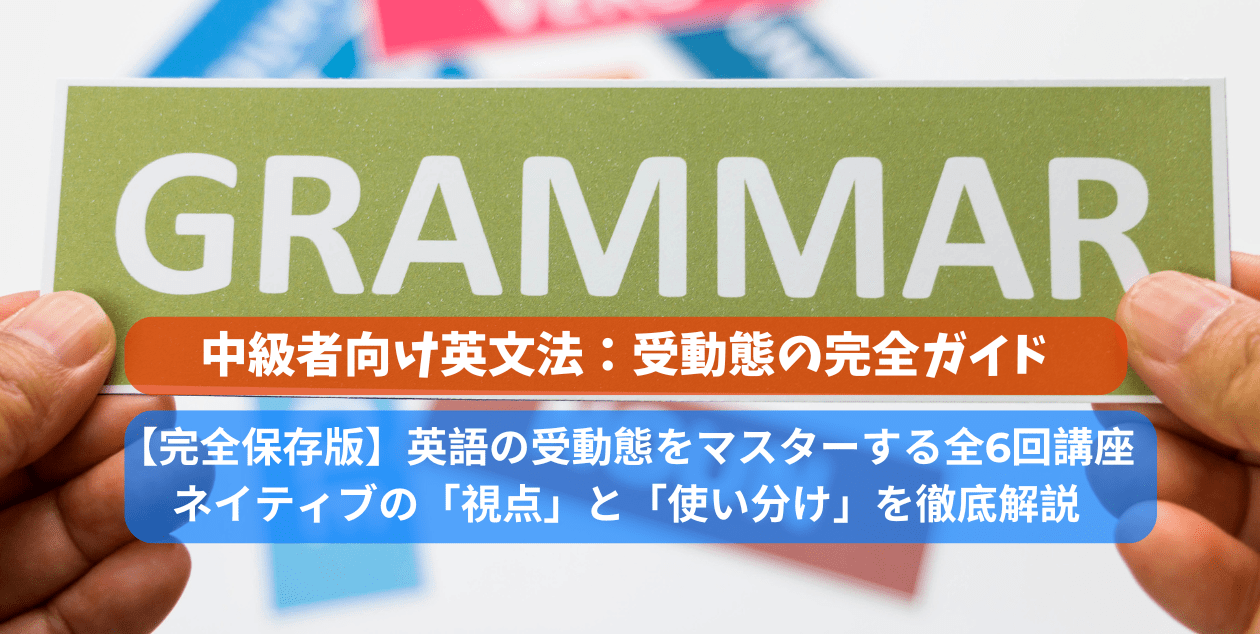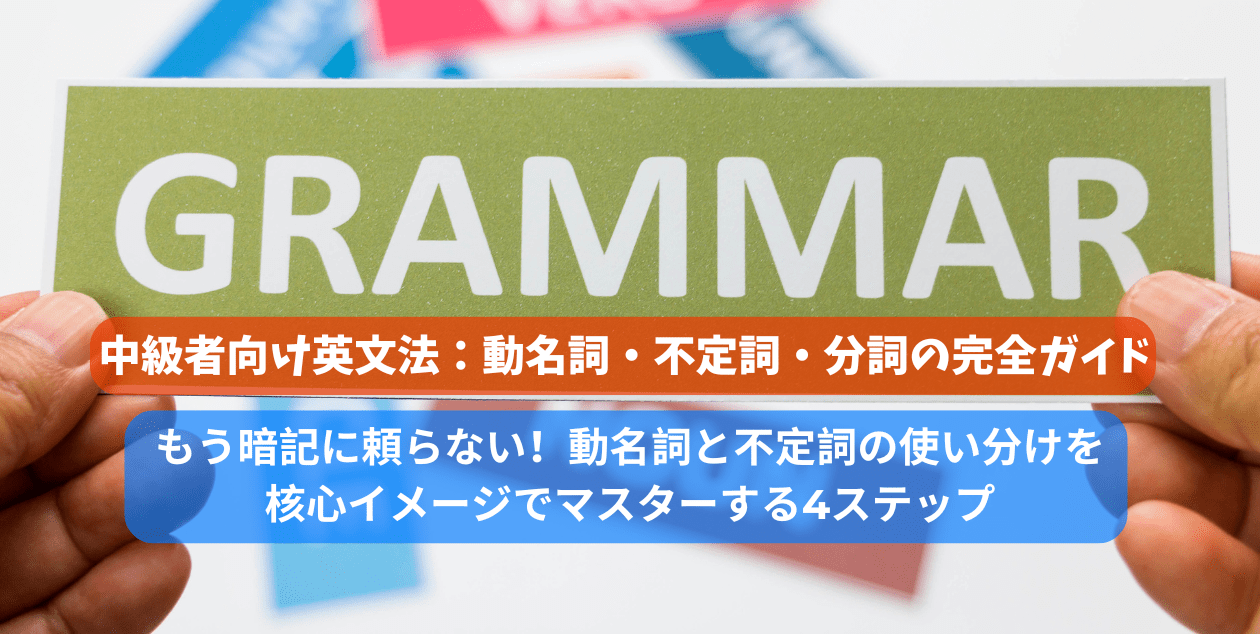30歳を過ぎ、「音楽で世界をとってやる」的な無謀な夢は砕けさリ、「そろそろ堅気の道を進まないといけないのかなぁ」と思い始めた頃、父親が病気になり、自由奔放な20代の日々は終わりを告げた。
と言っても、大学を中退し20代を築地の魚市場で過ごしたので、いきなりサラリーマンになれる訳ではない。幸い、アルバイトで講師をしていたAEONでフルタイム講師として正社員採用してくれた。アルバイトで入社した時も採用研修を受けたけど、フルタイム採用された時も、大宮のセミナーハウスで1週間缶詰の採用研修を受けた。これが「教える」と言う面では非常に良かったのだけど、「英語力」と言う面ではあまり関係ないので、ここでは割愛する。
と言うことで、研修後に千葉県船橋校でフルタイム講師として働き始めた。パートタイム講師の時は比較的同じようなレッスンを毎週担当していたけど、フルタイム講師になってからは、テキストもレベルも「隅から隅まで教える」的に、イレギュラーなクラスも非常に多く、プライベートレッスンも多かったので、色々なテキストを使って教えた。やはり、テキストの種類が増えれば増えるほど、英語力は上がってくる。でも、この辺りは、塾講師と英会話パートタイム講師の時と同じ。
英語力の向上という面では、ここからは、実際に外国人講師を「管理する」立場になって、職場でコミュニケーションを取りながら、学んで行った事。
- 主任講師
- 講師トレーナー
- 教務課責任者
1. 主任講師
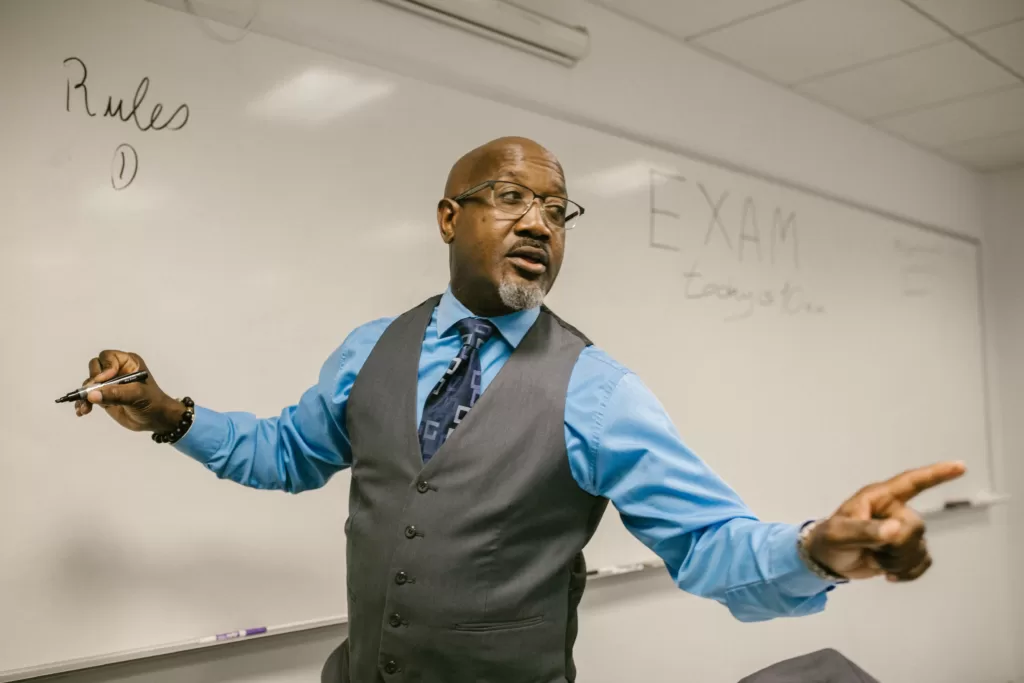
AEONの各スクールには、「主任講師」と言うポジションがあった。その名の通り、そのスクールの講師の責任者として管理すると言う立場なのだけど、実際には1日8時間勤務のうち、7コマ(1クラス=50分)、(中には60分レッスンもあった)、レッスンをするので、ほとんどレッスンをする時間だったし、レッスンとレッスンの合間に見込み客相手に体験レッスンをしたり、既存生徒のカウンセリングをしたり、(ちなみにカウンセリングとは契約更新や教材販売のためにするものである)、管理業務をする時間はそれほどなかった。
そして教えるレッスンの範囲がパートタイム講師の時よりも圧倒的に増えた。所謂オリジナルテキストの初級から中級だけでなく、市販の教材を使ったレッスン(Interchange, Side by Side, Coast to Coast, American Streamline,その他)の各レベル。プライベートレッスンで高校生の受験勉強とか、洋楽の歌詞を勉強するとか、客室乗務員の転職面接練習とか、とにかく、面倒なレッスンは全て「フルタイム講師に回す!」的な感じだった。
その中で、特に多かったのが、「資格試験クラス」、英検1級対策とか、TOEIC/TOEFL対策のレッスン。AEONの(と言うか、恐らく同業他社も)日本人講師は留学帰りの講師が圧倒的に多かった。彼女達はコミュニケーションスキルに長けていて、英語で聞く、話すが非常に得意だった。ただし、”読む”、”書く”が苦手な人が多かった。だから、みんな”資格試験クラス”を毛嫌いしていた。
でも自分の場合は、中学1年~高校3年/大学受験までの英語を学習塾で、ありとあらゆるテキスト、過去問をその場で対応する、と言う実体験を数年間持っていたので、英会話スクールの”資格試験クラス”は苦でも何でもなかった。必然的に、”英検1級クラス”とか”TOEICクラス”とか”TOEFLクラス”は全部自分に回ってきた。これもまた教えながら、それぞれのテストに特徴的な語彙力を身につける大きな力になっていった。
それでも、1週間に1時間程度「講師ミーティング」の時間があり、講師間で情報共有していた。「主任講師」と言っても、当時は管理職の経験無かったし、それほど権限があったわけでは無いので、「職場の仲間と話し合う」みたいな感覚だった。とは言え、自分が後から入って、そのスクールで働き始めて、元々そこで働いていた外国人講師に指示を出していく事は、当初多少難しかった。
その時に役に立ったのが、「インターナショナルパーティー」で様々な国籍の、違うタイプの(英会話講師だけでなく、軍人や海外企業の日本赴任者、そしてモデル)、人達と出会い、また音楽活動でイギリス人ボーカリストと意見を戦わせてきた経験。
恐らく当時一緒に働いていた外国人講師にとって、「あまり会ったことがないタイプの”日本人”」だったのだと思う。当時(1990年代)日本人で英語を勉強していた人、海外留学してきた人などに共通していた傾向は、「英語圏の人が言うことは全て正しい!」的な発想で、外国「いつかネイティブのように話せるようになりたい!」と言う気持ちでいるので、盲目的に人講師たちに迎合することが多かった。やはり、英語が好きで一生懸命勉強してきていて、心酔していたのだろう。
決して悪い訳では無いけど、自分が「単なる日本語のネイティブスピーカーと言うだけで、特別な存在でない」のと同様に、外国人講師含む一般的な英語圏の人は「単なる英語のネイティブスピーカーと言うだけで特別な存在ではない」し、英語という言語に対して彼らが言っていることを盲目的に信じる事はできない。自分自身の日本語、日本語に関する知識が絶対的でないのと全く一緒。
とは言え、当時同じスクールで働いていた外国人は、後に遭遇する「非常識な」人達とは違い、ごく常識的な範囲だった。それでも、外国人と日本国内で仕事をする上で、いくつか覚えて行ったことがあった。
- 1から説明しないといけない
- ムキになってはいけない
- 褒めないといけない
- Noと即答しないといけない
- 100%を求めてはいけない
1)1から説明しないといけない
意外とこれが出来ない。どうしても日本人同士だと、”以心伝心”の文化なので、意識している以上に、「言葉にだして」表現しない。「そんな事まで言わなくてもわかるだろ!」「周りを見ろ!」「空気を読め!」、子供の頃から言われ続けてきた、これらの事が無意識に反映されている。
一般的に英語圏の人は、「Verbal Communication」の文化、それに対して日本人は「Non-Verbal Communication」の文化。日本人同士のコミュニケーションをそのまま英語で行ってもなかなか上手くいかない。かなり意識的に、1から10まで、細かいところまで、「これでもか!」って言うくらい、言葉で説明していかないとわかって貰えない。
普通のコミュニケーションでもそうだけど、特に職場でのコミュニケーションの場合、これに加えて、「日本で日本の会社で働く上での”常識”」とか「ある特定の会社風土、慣習」とか、「仕事の進め方」とかが加わってくる。しかも、語学力の問題も出てくるので、文章、図、表などを使いながら、できるだけ細かく説明していかないといけない。この辺りは、英会話のレッスンをする時と全く一緒。相手のレベルに合わせてレッスンする、常に相手の頭の中で何が起こっているのか考えながる進める、これがレッスンの基本。
2) ムキになってはいけない
相手は、「Verbal Communication」の文化、なので、色々と言ってくる。日本人同士だったら、相手の気持ちや状況を考え、忖度し、発言や表情、態度をコントロールすることが多いが、英語圏の人は必ずしもそうではない。
そもそも、「忖度する事が常識」と言う文化ではない。なので、「この場で、そんなこと言うのか!」的な感じで頭にくることも多かった。後になって理解できたのだけど、彼らも「自分達の常識」の範囲で行動しているだけ。別に「裏切り者」でも「謀反者」でもない。
こう言う時に、感情的になってカッカしては逆効果。論理的に自分が正しい事を言葉で説明して打破するだけ。基本的に、”agree to disagree”の文化なので、討論した事が、後まで糸弾く事は少ない。
でも、これが難しかった。頭ではわかっていても、「いい加減にしろ」とか「勝手なことばかり言うな!」的な感情が出てきてしまう。これは、自分の場合、経験だけが解決方法だった。いつの頃からか、「こんなもんだ」と、最初から想定して、その枠の中のコミュニケーションに収まるようになった。
3)褒めないといけない
これが一番難しかったかな? 今の若い人にはあまり難しくないのかもしれない。でも当時30歳前後で、「バリバリの昭和人」だった自分には、”無意味に(自分の感覚では)、相手を”褒める”と言う感覚はない。
これは完全に文化の違いなんだと思うが、昭和の人間には難しい。「当たり前のことをする。」「普通の事をする」「仕事を(普通のレベルで)する」と言うことに対して、お礼を言う感覚はない。ましてや”褒める”と言う感覚はない。
しかしながら、これがどうやら彼らには必要らしい。(らしかった)「お礼を言われない」「褒められない」と自分が評価されていない、と感じるらしい。ある時期、この「お礼を言う」とか「褒める」と言うことは頭では理解し意識するようになったけど、心の底では、「馬鹿馬鹿しい」とか「面倒くさい」とか、言う気持ち、感覚が強く、なかなか実践できなかった。
実際に実践できるようになったのは、その20年後以上、50歳過ぎたくらいから。何故かはわからない。単に、自分の中でもそれが当たり前になったからかも。
4)Noと即答しないといけない
良く、英語で話すとき、外国人と話す時、「YesとNoをはっきりと言わないといけない」と言う。まさにその通りだと思う。しかしながら、そんなに簡単な事ではない。語学力の問題ではなく、どちらかと言うと、と言うか完全に、文化の問題。
先ほどの話と反対に、日本の文化が、日本語の文化が邪魔をする。日本語でコミュニケーションを取るとき、基本的に「同意」を着地点とする。相手の気持ちや感情を意識し、「出来るだけ、悪い印象を残さないように」コミュニケーションをとる。
「断る」と言う行為は、相手を傷つけ、悪い印象を残してしまうので、出来るだけ婉曲的に話し、相手に忖度してもらう手法を取る。それが、「日本語的コミュニケーション力」の高い人。そして、断られる人も、相手の意図を汲み取る事ができる人が、「日本語的コミュニケーション力」の高い人。
ただし、英語で英語圏の人とコミュニケーションを取る時は、まず最初にYesかNoかはっきりと答えないといけない。これは、表現的に「きつい」とか「柔らかい」とかとは関係ない。「YesとNoをはっきりと言わないといけない」だけ。と言うのも、文化的に話の展開の仕方が違うから。以下は一般論です。個人差があり、例外は多々あります。
まず現在の状況を説明します。
その状況の中で、自分が色々と努力してきた事を説明します。
努力したけれども、力が及ばず不本意な結果につながっていることを説明します。
お詫びをします。この段階で、「相手には”NO"を汲み取って欲しい」と思っています。
ここで”No”と言うのですが、はっきりと言うのではなく、「やはり現状ではなかなか難しいと言わざるを得ない状況です。」くらいの表現をします。
まず最初に、「出来ない」「駄目」のように、”Yes”,”No”を伝えます。
“Yes”なら”Yes”,,”No”なら”No”の理由を論理的に伝えます。
その場合の具体的な解決方法や提案を伝えます。
単に順番が違うと言うこともあるし、英語の場合は、”Agree to disagree”の感覚がある。日本語の場合、ややもすると、Noと言われると、全人格が全否定されるような感覚がある。
ある時期から、意図的に ”No"と即答するようになった。最初のうちは、内心では抵抗があったのが、数を重ねるうちに、「相手は、こちらが思っているほど、感情的には捉えていない」と思えるようになった。
5)100%を求めてはいけない
最初のうちは、「英語力さえつけば、完全なコミュニケーションが取れるようなる」と思っていた。でも、少なくとも自分の場合は、そこまでの英語力を身につける事はできなかった。
「言いたいことが、100%伝わらない」「伝えたい事を十分に理解して貰えない」「思っているように動いて貰えない」と常に感じ、それが全て自分の英語力の問題だと思っていた。
でもそれは「英語学習者の感覚」なのだと思うようになった。「英語学習者」は英語を話せるようになりたいと思う。「英語学習者」はネイティブのように話せるようになりたいと思う。彼らの感覚や考え方が正しいと思う。だから、彼らのように考え、感じられるようにならないといけないと思う。「同じでなければいけない」と感じる。
でもそれは、ある意味非常に日本的な考え方だと気づいた。そもそも、言葉も文化も習慣も違うのだから、「同じように感じ、考えられる」訳が無い。「100%理解しあえる」訳が無い「思ったように動いてくれる」訳が無い。ある程度、できれば十分だ。
まして、外国人とかアメリカ人とかイギリス人とか、一括りにできる訳がない。一人一人みんな違う価値観を持った個人だ。とりあえず、50%くらいの精度でコミュニケーション取れればなんとかなる。
考えてみれば当たり前のこと、日本人同士で日本語で働いている職場でも、同様のケースはいくらでもある。「部下が思ったように動いてくれない」「上司が何を考えているのかわからない」「自分が正当に評価されていない」「積極性が足らない」「反抗的だ」 「(上司には)ビジョンがない」
なので、文化も国籍も民族も言語も違う相手と一緒に働いていて、「100%理解できない」「思ったように動いてくれない」のは当たり前。だから、最初から目標を50%程度に設定しておいた方が良いと思うようになった。
2. 講師トレーナー

主任講師として勤務していた期間は2年間程度、ただし、正社員になる前にパートの講師として多分5-6年くらい働いていたので、スクールで7-8年教えてから本部に異動になり、講師トレーナーとして働くようになった。講師トレーナーの仕事は主に次の5つくらい。
- 日本人講師の面接と採用
- 採用研修
- フルタイム講師の月例会議、勉強会、研修の計画と実施
- スクール現場でのレッスンオブザーブ
- 外国人講師採用研修サポート、トラブル処理
ここでは「英語を身につけてきた方法」を書いているので、所謂仕事内容詳細的な事は省くが、主任講師としてスクール勤務をしていた時期と比べて大きく変わったのは、使用する英語レベル。
AEONに限らず、所謂「英会話スクール」と言う場所には、圧倒的多数は初心者層。「仕事で絶対に必要!」と言うタイプはそれほど多くはなく、大多数は「旅行に行った時、英語が話せたら良いなぁ!」「いつか仕事でも英語が使えるようになったら良いかも!」と言うタイプ。だから、毎日教えるレッスンも、やはり初心者クラスがほとんど。
「英語の教え方」は別のカテゴリーで書くけど、一般的に英語を教える時は、相手の英語レベルに合わせて教えて行く。初心者に教えるのであれば、初心者にわかりやすい単語や文型を使って教えていく。なので、初心者クラスを教えると言うことは、ずっと初心者に分かりやすい英語で話し続けることになる。本部で仕事をするようになると、ほとんど日本人講師か外国人講師が相手なので、特に自分の英語をコントロールする必要はなくなる。
1)日本人講師の面接と採用
例えば、日本人講師の面接。一般的な流れはこんな感じ。(順序はその日のスケジュールによって変わる事が多い)
会社の事業や仕事の内容を説明
履歴書を見ながら、これまでの経歴等を質問する
読解力、文法力、語彙力などを見る筆記テストを受けてもらう
テキストを渡し、10分程度のでもレッスンをしてもらう
英語で質問して、コミュニケーション力のチェックをする「
このうち、①から③までは当然ながら日本語で行う。④と⑤は英語。④デモレッスンは応募者が英語でレッスンする様子を見るので、自分で話す訳ではない。⑤インタビューは英語で応募者にいろいろ質問しながら応募者の英語レベルを判断する。
採用情報には、「TOEIC900点以上、英検1級程度、の英語コミュニケーション力があること」的な条件が書いてあったので、日本人講師に応募してくる人はある程度の英語力がある。スクール勤務時の「体験レッスン」でレベルチェックするのとはだいぶインタビューの内容が変わってくる。
面接時のインタビューは、当初外国人トレーナーが担当していたんだけど、どうやら彼らには中上級の英語学習者の英語力を判断するのが難しいようだった。英語でレッスンするのはそれほど簡単なことではないので、英語力不足だと「大宮セミナーハウス」の1週間泊まり込み研修で脱落することになり、応募者本人にも講師トレーナーにとっても、あまり良い事はない。
これは本当に不思議だけど、履歴書上は英語力が高そうでも実際に英語コミュケーション力を測ってみると全く違う事がある。例えば、「TOEIC900点以上、英検1級程度」の筆記テストのスコアがあっても英語が話せない、と言う事はよくある。筆記テストと実際の英語コミュニケーションは異なる種類のものだから。
でも、高校3年間と大学4年間の合計7年間以上、アメリカで生活してきました、とか、海外の大学卒業後、6年間仕事をしてきました、と言う履歴書上の経歴でも、あまり英語コミュニケーション力が高くないことが、年に数回以上あった。しかも、そう言う場合よくあるケースとして、社会人レベルの日本語が書けない、話せない、という事があった。
このように、日常的に接する英語のレベル、内容がスクール勤務時とは大きく変わってきた。そして、色々な国で様々な経験をして英語を身につけてきた新人講師達と1週間缶詰で研修することで、それぞれどういう理由、目的で留学し(留学帰りの新人が圧倒的に多かった)、どんな点で苦労し、どのように英語力が向上してきたか、色々な実例を知ることができた。
2)採用研修
当時の採用研修は大宮のセミナーハウスで1週間泊まり込みの研修だった。なぜこのような泊まり込みの研修というスタイルになったのかは不明だが、理由はいろいろ考えられる。
- 詰め込む量が多いので泊り込みにした
- 課題の量が多いので泊り込みにしないと出来ない
- 寝ないで頑張る他の研修生から刺激を受けて全体のレベルが上がる
- 「あんなにきつい研修を乗り越えたんだから」という意識が、その後の勤務に好影響を与える
- 通勤時間が長くなり過ぎるという現実的な理由
勤務していた当時は、③とか④とかが理由かなと思っていたけど、今思い返してみると実際には⑤の理由だったのだと思う。当時は「イーオン・イースト・ジャパン」と言って、関東と東北、北陸の全135校がエリアだったので、さすがに毎日秋田から来れないでしょって。
研修自体は日本語で研修をするんだけど、やはりテキストの研究とレッスンの練習がメインになるので、研修中はずっと英語の勉強しているような時間。スクールでレッスンをしていた時は初心者中心だったけど、講師研修は質問も高度なものになる。スクールでレッスンをしていた時以上にテキストの理解度、吸収度合いが高まった気がする。
また、レッスンの練習をする時、研修生の英語のミスを全てチェックしていくので、これまで以上に文法や語法に意識が向くようになった。ミスをチェックする時は理由を説明しないといけない。あやふやな点があれば、その都度確認した。
と言っても、自分自身100%の文法力があった訳ではないので、そういう時はいつも研修生に自分で調べさせていた。辞書と文法書を手渡し、「なんで間違っているか、自分で調べて発表しなさい!自分で調べないと覚えないから!」みたいな事を言っておきながら、研修生が自分で調べた結果を聞いて、「あぁそういう事か!」って心の中で思いつつ、あたかも全て知っているようなふりをしていた。
当時のAEONはCMが当たり急成長していたので、研修は1週間おきに毎月2回実施、毎回10人から15人くらい研修生がいた。だから1年間で200人以上研修していたんだと思う。そしてその200人を採用するための面接はその5倍くらいだった気がする。
このくらいの数をこなしてくると、英語の面でも教え方の面でも大体の傾向が掴めてきて、「よくあるパターン」がはっきりしてくる。スクールで初心者を教えていた時もそうだったけど、大体皆同じようなところでつまづき、同じような質問をする。講師研修を受ける上級レベル者もやはり同じで、皆同じようなところで間違え、同じような質問をする。
やはり多かったのは、
- 加算・不加算名詞、単数・複数
- 冠詞
- 長い文章の主語と動詞の一致
- 前置詞
- 仮定法
- 発音
留学帰りの研修生が多かったので、Fluencyは高い。でもレッスン中は講師は正しい英語を話さないといけないので、細かいミスにも気をつけないといけない。「細かいミス」と言っても普通に英語でコミュニケーションを取っている時には問題ないレベル。と言うか、ミスと気づかないかもしれない。
ここで2つのパターンに分かれる。ミスを指摘するとすぐに気づくタイプと全くわからないタイプ。後者の場合は、文字で書いて説明しても分からない事があるので、そもそも正確な知識が身についていないケース。この場合は自分で勉強してもらわないといけないんだけど、かなり時間がかかる作業になるので、途中でドロップアウトする人もかなりいた。
もう一つ2パターンに分かれる傾向があって、これは日本人社会への適応性。当時(1990年代)の日本は今ほど多様性に対する寛容性がなかった。外国人講師が多数勤務している英会話学校と言っても、日本人顧客向けのサービス業。社会人対象のスクールなので、所謂「お客様対応」が日本語で出来ないといけない。
一つ目のグループは、留学・海外生活中に頭の中が「アメリカ人」(アメリカに限定している訳ではない)になってしまっていて、ある意味「日本的価値観」とか「日本人顧客から見た常識」を見下すような態度で、時には「日本語そのもの」さえ軽視するタイプ。一般的にこのタイプは「英語で表面的な会話を流暢にするには十分な英語力があるが、教えるための正確な英語力は身についてない」事が多かった。
もう一つのグループは、英語でコミュニケーションを取る時と日本語で日本人に接する時と完全に対応法を使い分けるタイプ。このタイプには、英語力が非常に高く、日本語で話していても「きっとどんな職業のお客さんが来ても大丈夫だ」と思えた人が多かった。
この両者の違いを見た時に、本人の意識も違いもあるけれど、やはり親御さんの教育に対する考え方が反映されている気がした。きっと「英語さえ出来れば何とかなる」と言う発想だったのかもしれない。性格的には素直で良い子がほとんどだったので、少し可哀想に感じた事が多かった。
3) フルタイム講師の月例会議、勉強会、研修の計画と実施
当時のAEONでは毎月1回主任講師会議を実施していた。主には、その時その時の営業方法の確認がメインだった。英会話スクールには”募集期”と”閑募集期”があり、それにより営業の重点項目が変わってくる。と言うことで、時期によっては”体験レッスンの仕方”がテーマになったり、”教材販売の仕方”がポイントになったりした。
ところが、”留学帰りの英会話講師達”にとっては、この営業活動が非常にストレスになっていたらしい。(築地の魚市場で魚を売っていた人間には、何も難しいことは無かったけど)この”営業活動”の話だけだと、意味消沈してしまうので、”教え方の練習”とか”英語学習方法” とかを取り上げる時間があった。当然ながら、これを毎回計画し準備していかないといけない。
なので、教授法の英語文献とかを使って勉強したり、外部からNHKテレビ講座の講師を招いて講演してもらったり、出版社から外国人営業担当者を呼んで教材紹介してもらったり、と色々工夫しながら、出来るだけ、「英語を使って仕事をしている」と言う印象を与えられるようにしていた。この準備をすることは、スクール現場でレッスンをするのと同様に自分の英語力向上に役立っていたと思う。何でもやったことのない事を実践する事は向上につながっていく。
この主任講師会議は50人規模のミーティングだったけど、支部毎の講師勉強会というのがあって、これが10人規模のミーティング。基本的にはレッスンの進め方などがテーマになるので、「教えにくいレッスン/テキストの教え方」とか「対応が難しいタイプの体験レッスンの進め方」とか、実践的な物が多い。「英語・英会話を教える」と言う面では、凄く向上していて言った時間だったと思う。
以前にも書いたように、日本人講師達は留学帰りの子が多く、一般的な特徴として、「”聞く””話す”を中心とする、”英語コミュニケーション力”」に長けている人が多かった。その反面、”読む””書く”と言う英語力があまり高くなく、特に時事問題を扱う、ニュース記事のようなものは、驚くほど読めなかった。
なので、毎回この勉強会では、英文ニュースを読み、単語テストを実施する、と言うことを繰り返した。「読めない理由」の半分は語彙力なので、まずニュースを読むのに必要な語彙力を上げないと話にならない。「読めない理由」の残り半分については、”英語学習法”のカテゴリーで書くけど、この勉強は、毎回ニュース記事を読むレッスンをしていたような物なので、自分の英語力向上に大きく役立った。また、上級レベルの英語学習者の指導法についても、実体験を積む良い経験になった。
4)スクール現場でのレッスンオブザーブ
研修、面接、会議の合間に、担当しているスクール(50校以上あった)に行って講師のレッスンオブザーブをしていた。事前に伝えることもあったし、いきなり行くこともあった。スクール勤務の講師からすると、突然本部からトレーナーが来てレッスン見られて指導されるので、面倒な存在だったと思うが、意外と悩み相談みたいになる事が多かった。
やはり、「英語が好きで、英語を身につけたくて留学した」と言うタイプの講師が多かったので、「英語を教える」とか「生徒の英語力を上げる」とか「外国人講師のティーチングスキルを上げる」とか言うことに関しては凄く真面目だった。
50校以上担当していると、各スクールに行けるのは年に1,2回になってしまうので、オブザーブに行った日は、かなり遅くまで悩み相談になる事があった気がする。その中で多かったのが”外国人講師問題”で、レベル設定を間違える、とか、生徒から苦情がくる、とか、教え方が下手だ、と言うケース。
これは色々な問題があるので、ここでは英語力以外の部分は省力するとして、「外国人講師のレッスンが下手だから見てくれ」と頼まれる事がかなりの頻度であった。自分が講師トレーナーとして勤務していた時期のAEONは、まだ日本人講師と外国人講師が、研修方法も指示系統も別だった時代なので、本来は外国人講師のオブザーブは外国人講師トレーナーが担当するべき物だったけど、自分の場合は結構外国人研修も手伝っていたので、有無を言わせずオブザーブしてレッスン内容の指導をしていた。
最初のうちは、おそらくフィードバックされている外国人講師もよくわからなかったんじゃないかと思う。これは英語力とか文化の違いというよりも、情報量とか知識量の差異を理解し、考慮した話し方をしていなかったから。本部に来て講師トレーナーとして働き始めると、スクールで初心者相手にレッスンをしていた時のことを忘れてしまう。初心者や中級者を教えていた時は、常に「相手のの頭の中」を考えて、レッスンして、話していた。
講師トレーナーになった当初は、まだ自分と同じ感覚の講師、英語上級者、ネイティブスピーカーと話している、と言う感覚だったので、あまり、生徒相手に注意していた、”情報量とか知識量の差異”を意識していなかったのだと思う。特に外国人講師に対しては。
でもスクールで外国人講師のレッスンをオブザーブして指導しているうちに、「日本人講師相手に日本語でフィードバックしている内容をそのまま英語で行っても効果がない。」と言う、ごく当たり前のことに気がついた。
ここは「教え方」がテーマでなく、あくまでも「英語力」がテーマなので詳細は省くとして、日本人講師は、「自分が英語を学んできた経験を基に、初心者や中級者の特徴を理解して教えている。」だから、それを前提に指導していけばすぐに理解し、向上できる。
外国人講師に対しては、「なぜ日本人生徒がそのような問題を持つのか」を、最初から説明していかないと理解できない。レッスンの問題だけでなく、勤務上の誤解も同じ。どうしてもスクール勤務の日本人スタッフや講師は、日本人同士のコミュニケーションをそのまま英語でしてしまう。
ただし、各スクールの営業状況であったり、生徒の情報であったり、色々な面で「情報量の違い」が大きい。だから、最初の前提として「お互いが理解している」と認識している領域が違う。外国人講師は知らない事、聞かされてない事、理解しいない事を「常識」的な感覚で話してしまうので誤解が生じてしまう。
この、両者の「誤解」を解消していくと言うのが、スクールにオブザーブに入った時、かなり頻繁に起こっていた。これはなかなか難しい問題で、”Agree to disagree”の感覚がないと難しいのだと思う。
英語を使ってコミュニケーションを取る時に、特に中級レベル以上になってくると、”文化面”の問題が大きくなってくる。色々な考え方があると思うけど、個人的には、どこかで割り切る必要があると考えている。自分の場合、「結局、文化、価値観が違うので100%理解し合うことはできない。」と割り切って考えている。中には、「人類皆兄弟」的な発想の人もいるみたいだけど、少なくとも自分はそこまでの許容範囲はない。
以前、インターナショナルパーティーで感じた、「結局、文化、価値観が違うので100%理解し合うことはできない。」と言う割り切り方は、英語で仕事をしていく上では役に立っていたのだと思う。
5)外国人講師採用研修サポート
講師トレーナー時代のメインの仕事は日本人講師の採用~研修~教育~管理だったけど、外国人講師の採用研修サポートもしていた。当時は1週間毎に日本人講師の採用研修と外国人講師の採用研修を大宮セミナーハウスで実施していた。
研修自体は外国人講師トレーナーが実施していたけど、二つほどサポートしていた。
① 日本語レッスン
1週間の研修中に1時間だけ日本語のレッスンをしていた。目的は以下の3つ。
”直接教授法”とは「母語を介さずに教える言語だけで教える」。簡単に言ってしまうと英語のレッスンであれば、日本語を使わずに英語だけで教える、と言うこと。この場合は、日本語のレッスンを英語での説明無しに日本語だけで受けること、になる。
当時は90%以上の研修生は、日本語の超初心者だったので、実際に日本語だけで日本語のレッスンを受けると、「英語が苦手な初心者」の気持ちを実感する事ができた。
当時のAEONは、基本的に全ての外国人講師を国内採用ではなく、現地採用(アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなどで)していた。いきなり成田空港から大宮のセミナーハウスで1週缶詰になる訳だし、経験した事のない仕事を始める訳なので、かなり大変そうだった。日本語レッスンは、ある意味、息抜きの時間だった。
② 模擬レッスン
当時の採用研修は、1回あたり大体10人から20人くらいの研修生がいた。配属先スクールへ着任してレッスンをするための研修なので、何回か模擬レッスンをする。4-5人のグループに分かれてレッスンをして、トレーナーがフィードバックしていくのだけど、20人も研修生がいたら、トレーナーが4-5名必要になる。外国人講師トレーナーは確か2-3人位程度だったので模擬レッスンの時はヘルプに行って、レッスンのフィードバックをして指導していた。
レッスンのフィードバックに関しては、最初のうちこそ少し難しかったけど、テキストもレッスン方法も、新人講師がよくやる間違いも把握していたので、それほど難しいことではなかった。
「英語力向上」と言う面で大きかったのが、「ネイティブスピーカーのグループの中に日本人1人が入り、ディスカッションしながら進めて行く」、と言うこと。特に採用研修の場合、成田空港から直行してきているので、「日本人と英語で話す」と言うことにまだ慣れていない。
グループ心理もあるので、勝手に盛り上がっている事もある。実際何言ってるのかわからないこともあったし。そういう環境の中で、決まったスケジュールの中で必要な研修を進めて行くためには、相手のペースに合わせてはいられない。自分でコントロールして進めていかないと何も学ばないうちに配属先のスクールに着任してレッスン開始してしまうので、ある時からかなり強引に進めて行くようになった。これは、語彙とか文法とか、そう言うことよりも、心理的な問題だと思う。
この外国人講師研修の中で、ある時面白い事があった。当時勤務していたアメリカ人トレーナーが研修しているグループの中にニュージーランド人がいた。このニュージーランド人が凄く良い人だったけど、思いっきりニュージーランドアクセントが強かった。
最初は何言っているのかわからなかったけど、数時間話しているうちに特徴が掴めてきたので普通にコミュニケーション取れるようになった。ところが、アメリカ人トレーナーはいつになってもニュージーランド人が言っていることが聞き取れなかったみたい。最終的に、自分が間に入ってあげて、アメリカ人とニュージーランド人の通訳をした事がある。
このアメリカ人トレーナーは、数年に日本で生活していたのに全然日本語できなかったし、他の外国語が話せたような記憶はない。多分、外国語学習のセンスが無いというか、この場合は外国語じゃ無いんだけど、アクセントにも慣れなかったのかな?かなり不思議な時間だった。
この「外国人講師研修サポート」中は、かなり英語を使っていたと思う。とは言え、ある程度回数をこなしてくると、結局毎回同じような話をしているので、「大きく英語力が向上した」とかいう事はない。
「話す」と言うことに関しては、仕事に関することなら自分の言いたいことは言えるので、と言うか、言いたいことを表現するための最適な語彙・表現を知らなくても/思い出せなくても、他の言い方をして誤魔化す的なコミュニケーションの仕方を身につけていた。
ただし、いつもこの「誤魔化す」的なコミュニケーションをしていたので、自分の英語力の「語彙力不足」と「文法力の不正確さ」を実感していた。基本的に「アウトプット」中心の日々だったので「インプット」の必要性を感じていた。
この点を勘違いしている英語学習者が意外と多い。英語を話せるようになりたいと思って、「アウトプット」/「英語を話す機会」ばかりを求める人が非常に多い。このタイプの人を過去に何千人と見てきたけど、大体において「インプット」が足りてない場合が多い。結局、「インプット」以上には「アウトプット」はできないので、「インプット」量が少なければ、「アウトプット」できるのはそれ以下にしかならない。
3. 教務課責任者

講師トレーナーとして、恐らく3-4年くらいだろうか、勤務した後、教務課責任者になった。と言っても、講師トレーナーの仕事は兼任していたので、トレーナーの仕事内容はそのまま継続しつつ、管理業務が増えてきた。新たに増えた業務はこの5つ。
- 日本人講師トレーナー管理
- 外国人講師トレーナー管理
- 外部との折衝(主に)出版社
- トラブル処理
- その他
講師トレーナーを始めた頃は、日本人講師の採用・研修・管理は日本人トレーナー、外国人講師の採用・研修・管理は外国人講師トレーナー(正確には、外国人講師の場合は「採用」に関しては現地のリクルーターが担当していた)が担当すると言う区分けだった。
しかしながら、日本人講師と外国人講師を別々に管理する事の弊害が徐々に顕著になってきたので、「レッスンの教え方」や「研修方法」を統一する事になった。なので、教務課責任者としての最初の仕事は、外国人講師の研修方法と管理方法のテコ入れだった。
1)日本人講師トレーナー管理
これはあまり大変な事はなかった。と言うのも、全体的に日本人講師は優秀でよく働く人が多かった。ほとんどの日本人講師は海外、主にアメリカの4年制大学を卒業し帰国、あるいは数年海外で働いてから帰国した子だった。帰国後、英語を使った仕事をしたくて就職活動したものの、規模の大きい企業だと最初から英語が使える訳ではない。
元々英語が好きで何年間もひたすら英語を勉強して身につけた「英語を使って仕事をしたい」、と言う気持ちが強く、生徒にも「英語を身につけて欲しい」と言う気持ちが強いので、熱心に取り組んでくれていた。その中でも特に優秀な講師を昇格させていたので、転職されないように、フォローしていく事くらい。
正直言って、英会話スクールの日本人講師、というか社員の収入は決して多い訳ではない。労働条件が悪くても、「英語を使える仕事をしたい」と言う気持ちだけで一生懸命頑張ってくれていたんだと思う。中には非常に優秀な子もいたので、2-3年英会話スクールで勤務した後、20代半ばで外資系企業に転職し、年収が3-4倍に増えた子もかなりいた。
この辺りの話は、自分の英語力向上とは特に関係ないので、ここでは割愛。
2)外国人講師トレーナー管理
同じ講師トレーナーでも、外国人講師トレーナーの場合は少し状況が変わってくる。日本人講師トレーナー同様に、スクール勤務講師の中から優秀な人材を昇格させて本部に異動する。この場合、「優秀な」と言う意味は、このような意味。
- レッスンが問題なく出来て、生徒からの評判が良い(当たり前だけど)
- 日本人スタッフからの評判が良い(一緒に働きやすい)
- 日本人顧客に対して、サービス業としてレッスンを提供している、事を理解している。
この中で、③を十分に満たしている人は本当に少なかった。
ある意味、「レッスンの教え方」とか「スタッフとコミュニケーションを取る」とかを指導していく事は、大体の外国人講師トレーナーには、理解出来、実践できるんだけど、問題のある講師、生徒から苦情が絶えない講師、会社やマネージャーからの指示に従わない講師、に対して、「日本人顧客に対して、サービス業としてレッスンを提供している」仕事に従事しているのだから、「日本人顧客の顧客満足度を高める」ために努力しないといけない、と言うことを理解させ、改善させられる外国人講師トレーナーはほとんど皆無だった。
なので、外国人講師トレーナーに対して、「生徒=顧客」という事を、十分に理解させるために、日々コミュニケーションを取り続けていた。この時難しい点があって、基本的に講師トレーナーとして昇格してくる外国人講師は、スクール勤務時に、「生徒から評判が良かった」とか「日本人スタッフと上手く働けていた」という成功体験を持っている。
しかも、一般的に日本人生徒も日本人スタッフ、特に新人、は、外国人に対する憧れが強く、外国人講師を甘やかしていることが多い。なので、どうしても「顧客満足度」に関する基準が甘くなる傾向がある。その状態で、「生徒から評判が悪い講師」に指導すると、管理者の目にはどうしても「甘すぎる」「全然改善されていない」と見えてしまう。最初のうちは、怒ってばかりいたかもしれない。
それでも、管理職を1年、2年と続けていくと、自然と問題が減ってきた。と言うのも、結局スクール勤務時に主任講師として外国人講師と接していた時と同じようなアプローチで良いと思うようになったから。
それは、この5つ。
- 1から説明しないといけない
- ムキになってはいけない
- 褒めないといけない
- Noと即答しないといけない
- 100%を求めてはいけない
特に、大切だったのは、①、③と⑤。
やっぱり、本部に来て外国人講師トレーナーと言っても、日本人幹部社員との、情報量の差は大きい。小まめに細かく説明していかないと、「誰もが当たり前の事として知っているような事を全く知らなかった。」なんてことも珍しくなかった。
そして、自分にとってはいつになっても難しかったのが、「褒めないといけない」と言うこと。文化的な違いなので、純日本人的な感覚の自分には難しい感覚。なんか、凄くわざとらしい、薄っぺらな感じがして、どうしても躊躇してしまっていた。特に当時は、自分が上司と言っても、同年代だったし。
後に、自分が40代、50代になってから、20代-30代の外国人講師を部下として持つようになってからは、それほど違和感なく、ある意味、子供に対して話すような感覚で、自然と褒められるようになっていった。
しかしながら、究極的には、⑤。
100%を求めてはいけない。これに関しては、自分自身は比較的早い段階で、まだスクール勤務していた時代から、理解していた事。ただし、本部に来て働くようになってからは、一緒に働いている日本人講師トレーナーからすると、外国人講師トレーナーは同格になる。日本人講師トレーナーが日本人講師に対する期待値や要求も高かったので、外国人講師トレーナーや外国人講師にも同様の基準で見てしまう。
また、スクール勤務の日本人スタッフは、直接お客さんから、「講師に対する不満や苦情」を聞かされる訳なので、1日も早く100%の状態になって欲しい、と言う気持ちで、本部に指導を依頼してくる。この中で、「なんとか80%くらいの基準まで持ち上げよう」と、日々外国人講師トレーナーや外国人講師と接していた。
3)トラブル処理
その延長線上で出てきたのが、外国人講師のトラブル処理。
① レッスン内容や教え方に関する苦情
これは比較的簡単なトラブル処理。スクールに行って苦情の多い講師のレッスンをオブザーブし、改善点を伝える。研修に呼ぶ。再度スクールに行ってオブザーブする。この繰り返し。大体において、講師に悪気はない。自分なりに試行錯誤し、良いレッスンをしようとしているのだけど、上手くいかない。
「情報量の差」が原因の事が多い。たかだか数ヶ月、多くて数年、限られた生徒を教えた事があるだけ。この状態で独りよがりの考えで進めていっても上手くいくもんじゃない。この時、注意していた事は、出来るだけ客観的に解るように説明すること、文字や図を使うこと。
まぁ、レッスンと同じですね。実際に講師が言った言葉をボードに書いて、生徒の反応も文字で書く、あるいは自分で再現して見せて、出来るだけ視覚的に解るように説明した。
「百聞は一見にしかず」じゃないけど、見せるのが一番早い。プレゼンや交渉も一緒で、必ず同じ図や表、フレーズ、など見ながら話す。英語力そのものよりも、このような視覚的補助がより大切だと思うようになった。
② 勤務態度に関する問題
スクールマネージャーは20代の女性が多かったので、どうしても外国人講師からなめられる事が多かった。また、日本人講師ほどの英語力はないので、上手く伝えられない事が多い。更に、日本の文化として「以心伝心」「察する」的な感覚があるので、直接本人に問題点を伝えていない事が多い。
この状態で、私がスクールに行って外国人講師に「勤務態度を改善しなさい」的な事を言っても本人的には「寝耳に水」的なことが多いので、全く自覚していない事がほとんど。
なので、ここでも1から10まで、全て言葉で説明し、図を書き、箇条書きを見せ、視覚的にも分からせる。その場で理解しても、数ヶ月後にまた同じ状態に戻っている事が多い。これは、「何も言わない、問題点を伝えない」日本人スタッフも悪いのだけれど、すぐに治るもんじゃない。
この勤務態度の問題には、以下のような情けないものもあった。
- 不潔だ
-
「洗濯しないので、シャツの袖や襟が真っ黒」
「入浴しないらしく、悪臭がする」
- 二日酔いだ/酔っ払っている
-
「酒臭い」
「酩酊状態だ」
- 毎日遅刻してくる
-
これは数十分単位の時もあるし、5分-10分程度の事もある。「文化の違い」と言ってしまえばそれまでだけど、「時間に関する感覚/意識の違い」は大きい
- 昼休みに行ったきり帰ってこない
-
これも「文化の違い」と言ってしまえばそれまでだけど、昼休みが5-10分伸びてしまっても(遅れて帰ってきても)何の問題もない、と考えているみたいだった。(1990年代の話なので2023年の今とはだいぶ時代背景や人々の考え方も違う)
- アパートがゴミ屋敷
-
当時外国人講師が住んでいたアパートは会社が借りていて、講師は社宅に住んでいる形だった。例によって「文化の違い」として片付けようとする外国人講師がいたものの、他の住人にとっては迷惑極まりない。
当時所属していたのはイーオン・イーストジャパンの首都圏本部。首都圏本部と言っても、東京都内だけじゃなく、千葉県の市原五井校とか神奈川県の小田原校とかもあったので、新宿のオフィスから移動時間2時間くらいのところもある。
21時にレッスンが終わってから、「洗濯しなさい」とか「風呂に入りなさい」とか「ゴミを捨てなさい」とか、何回も話して、2時間以上かけて自宅に帰ると24時過ぎて、「一体、俺はなんの仕事をしているんだろう?」って。と、思ったことは、数回ではない。
③ 処罰
この勤務態度の問題が悪化すると、最終的には処罰と言う事になる。当然ながら、スクール内で、スクールマネージャーなり、主任講師なりが注意するのだが、改善されない場合は本部に連絡が来る。基本的には外国人講師トレーナーが注意しにいく。それで改善されれば良いのだけど、あまり変化が見られない事が多かったので、責任者の私が出向いていく事になる。
色々なケースがあったけど、こう言う時はネイティブスピーカーが圧倒的に有利になる。とにかく言いたい事を言ってくるし、駄目元で無理なことも言って来る。最初のうちは、一々真に受けてしまって、「弁護士と相談する」とか言われると怯んでしまったりしたが、段々と相手の出方がわかるようになってきた。
また、英語でこの手の話をする時に、「相手のペースに付き合う必要もない」と言うことも学んできたので、自然と間を取りながら、ゆっくりと話すようになった。そして、決して怒ったり感情的になったりせずに、事実や問題点を淡々と告げ、まず相手の言い分を聞くようにした。
「双方から公平に話を聞く」という意味もあったけど、先にこちらの情報を全て出してしまうと、ネイティブスピーカーに言い包められてしまう事があるからだ。まず相手に話させて、説明させて、その上で、相手の言った言葉を使いながら、一つずつ理詰めで問題点を追求するようになった。
更に問題のある講師が相手の時には、外国人講師トレーナーを同席させるようにした。基本的に外国人講師トレーナーに話をさせて、必要なところだけ自分が話すという方法を取った。自分一人で対応すると、どうしても相手の話を聞きながら、それに対する自分の反論を頭の中で考えながら聞くので、覚え切れないこともあったが、外国人講師トレーナーに話をさせると、相手の話を聞くことに集中できるので、必要な時に直ぐに話に割り込み、反論する事ができた。
また、面談後の記録を書く時も、外国人講師トレーナーに書かせた上で修正すれば良かったので非常に効率が良かった。と言っても、AEON在籍時に対応した「問題のある講師」はそれほど悪質な類ではなかったので、大きな問題になったことはなかった。後に、転職後の会社で裁判や労働問題になった時対応した「問題のある講師」に比べると、何の問題も無いというレベルだった気がする。このトラブル処理は、「実践的な英語コミュニケーション力」を向上させるのに非常に大きな影響を与えていたと思う。
4) 外部との折衝(主に)出版社
これまでは、「英語を使って仕事をする」と言っても、生徒相手にレッスンしたり、応募者に面接したり、外国人講師の研修や管理をする、と言う程度だった。「英語を使って仕事をする」とは言え、やってる事はレッスンの延長線上だったので「仕事感」はあまりなかった。
これが外部との折衝になると、多少「仕事感」が出てきた。当時のAEONはだいぶスクール数も増え、知名度も上がってきていたので、出版社がセールスに来た。スクールではAEONの「オリジナル教材」をメインで使っていたけど、1部のレッスンや自宅学習用の教材として、出版社のテキストを登用していた。
とは言え、当時の出版社の営業は、「元英会話講師」がほとんどだった。当時不思議な風潮があって、外国人講師の出世街道みたいな流れがあった。
大学卒業して何も分からないまま日本に来て、「初めての仕事」として英会話講師をする。「スチューデントローンを返すため」「世界を見てみたい」「アジアに興味があった」など、何となく日本に来てみた。
スクール勤務でそれなりの評価を得て、外国人講師トレーナーに昇格すると、本部社員となり、マネージメント能力が求められる。ジョブスキル的には「マネージメント」能力が経験値としてプラスされるので、それなりの経験になる。
「英会話スクールの講師」と言うと、ある意味「ネイティブスピーカーなら誰にでも出来る」職種として日本国内ので外国人居住者のカースト的には低い。それが、「出版社勤務」になると「普通のビジネスパーソン」に格が上がる。
みたいな流れ
やっぱり、英会話スクールの外国人講師って、ネイティブスピーカーなら誰でも出来る的なイメージがあったので、出版社みたいな「普通の会社」に勤めて、月曜日~金曜日で9時~5時で働く、と言うのが外国人講師の最終目標的な感じで、ちょっとエリート意識を持っていたような気がする。
こちらがクライアントなので、基本的に「商品を紹介され、興味があれば話を聞き、気に入れば採用する」と言う流れ。「トラブル処理」のように気を使わなくても良いので、かなり軽い気持ちで、息抜きのような感じで対応していた。
この時感じたのが、「欧米人=プレゼンが上手い」訳ではない、と言うこと。当たり前の事だけど、外国語を勉強していると、「欧米では子供の頃からスピーチの訓練を受ける」、「自分の意見を言えない人は認められない」、みたいな事を繰り返し聞かされていたので、「外国人/ネイティブスピーカーなら、誰でもプレゼンが上手い」的な、馬鹿馬鹿しい先入観を持っていた。
やはり、自分を含めて、外国語学習、特に英語学習の場合、文化的な意味でのコンプレックスが強いのだと思う。外国語としての英語を学び、そのためにネイティブスピーカーのレッスンを受ける、と言うことはともかくとして、プレゼンやミーティングなど含めて「ビジネスの仕方」を、単なるネイティブスピーカーから学ぼうとするのは違う気がする。
なので、外国人セールスマンと対応していく中で、当たり前の事だけど「セールスの上手い人/下手な人」、「プレゼンの上手い人/下手な人」、「コミュニケーション能力の高い人/低い人」がいる事を認識した。
とは言え、「電話で話す」とか、「メールでやり取りする(当時はFAX)」とか、外部の人と英語でやり取りする事はなかったので、良い経験だった。後に、海外の出版社や企業とやり取りをする上で、良い準備練習だったと思う。
5) その他
この時期に英語力アップに役立った事というと、「教材研究」と「学習法研究」。
① 教材研究
教材研究は色々あった。まずオリジナル教材。教材の特徴やメリットを、スクールスタッフが説明できるように「差別化」のシナリオを作る。当然、よく出来ていたテキストだけど、初心者にもよく伝わるように、他のテキストと比較したり、大学受験や資格試験(TOEIC、英検など)にどのように役立つのか、とか、調べ上げていく。
いろいろなテキストやテストを研究したので、それぞれの特徴や違いを理解することで、英語に関する知識が向上した。特にテストに関しては、文法など確認ポイントはどのテストでも同じような傾向があるけど、使用される語彙の種類は大きく異なる。
語彙に関してはかなり客観的に見れるようになったと思う。また、AEONでは年に2回、家庭学習用の教材を販売していた。市販の教材を使う事が多かったけど、初心者向けの文法の解説書を作った。これは自分の中で、日本の学校教育を受けた学習者が最低限必要な文法的な知識を身につけるために何が必要なのか、を徹底的に考えたので、語彙同様にしっかりと整理できたと思う。
② 学習法研究
英会話スクールに通う生徒たちは、当然ながら、「英語力を伸ばしたい」と思っている。レッスンが大切なのだけど、週1回のレッスン受講では限界があるので、「学習法のアドバイスをする必要がある」、
これが非常に難しい。特に講師の場合、「英語が好きで、一生懸命勉強し、留学して英語漬けになって身につけました!」的な人が多いので、どうしても学習量、学習時間ともに負荷のかかるアドバイスをしてしまう。
また、個人個人の学習スタイルは人によって異なるので、「自分にとって最適だった学習方法が、他の人にも有効とは限らない。」と言う事をしっかりと意識している人は少ない。
なので、出来るだけ色々な「効果的学習方法」を出来るだけ多くの人にヒアリングし、講師同士で情報交換できるようにした。自分の体験と、数多くの英語学習者の経験を比較する事で、客観的に「効果的学習方法」を考えられるようになったと思う。