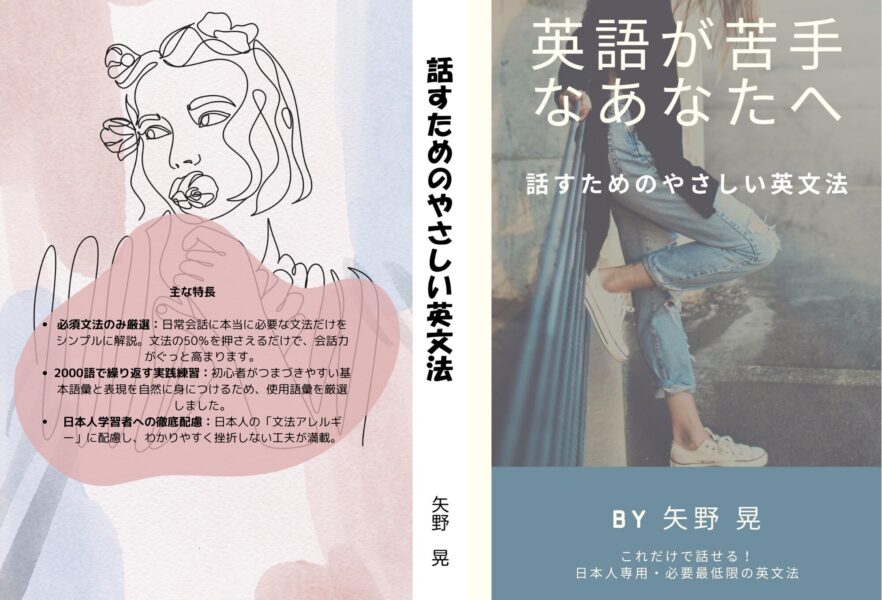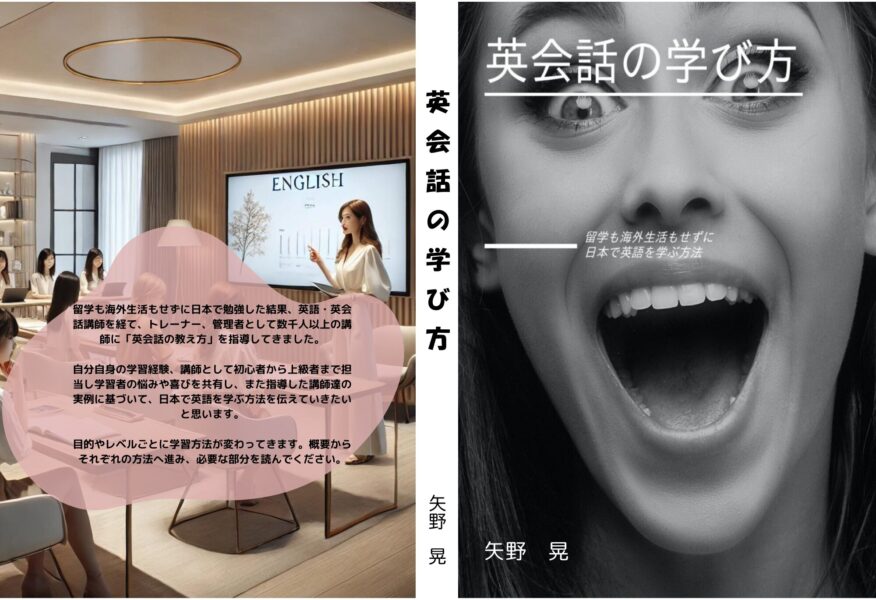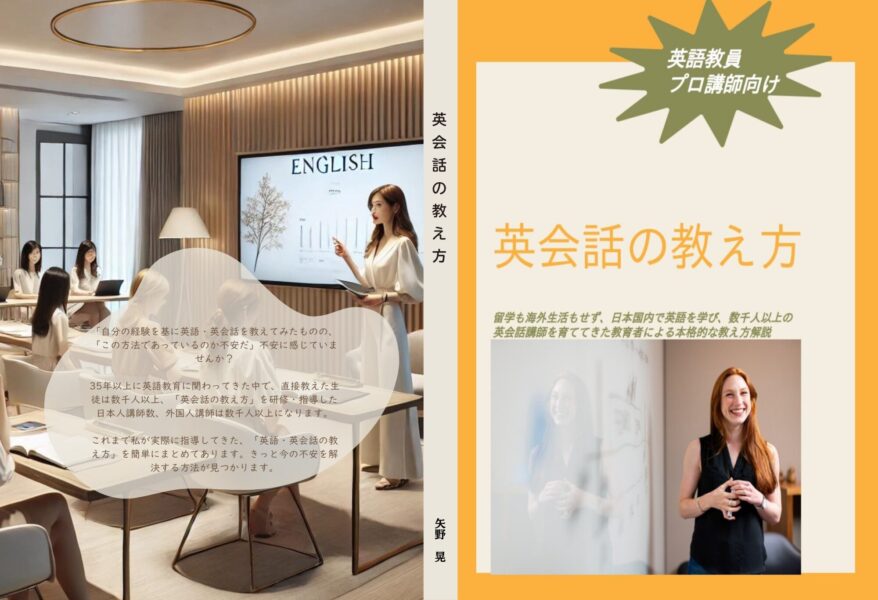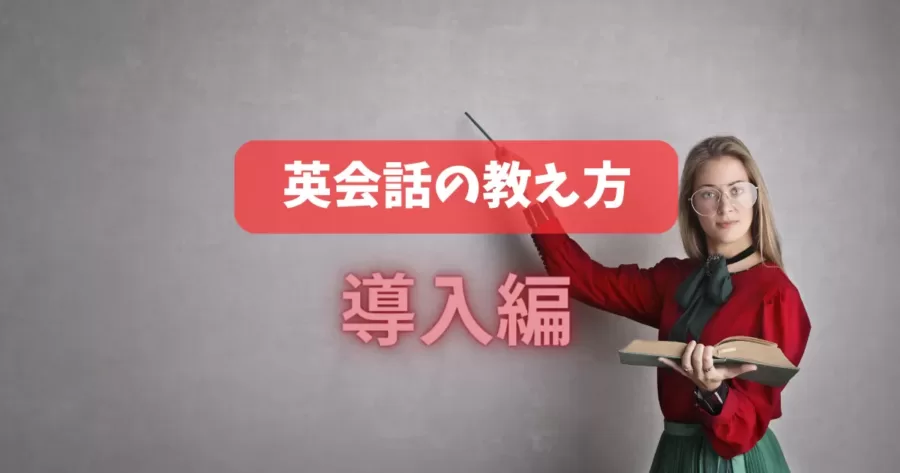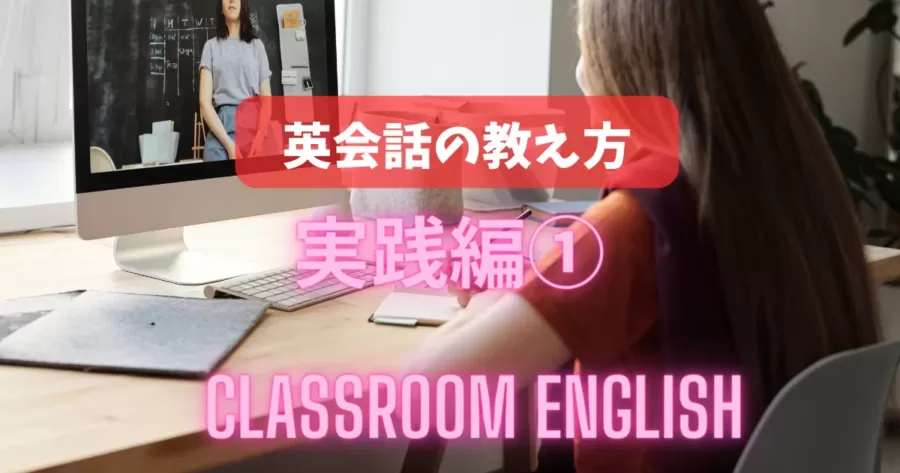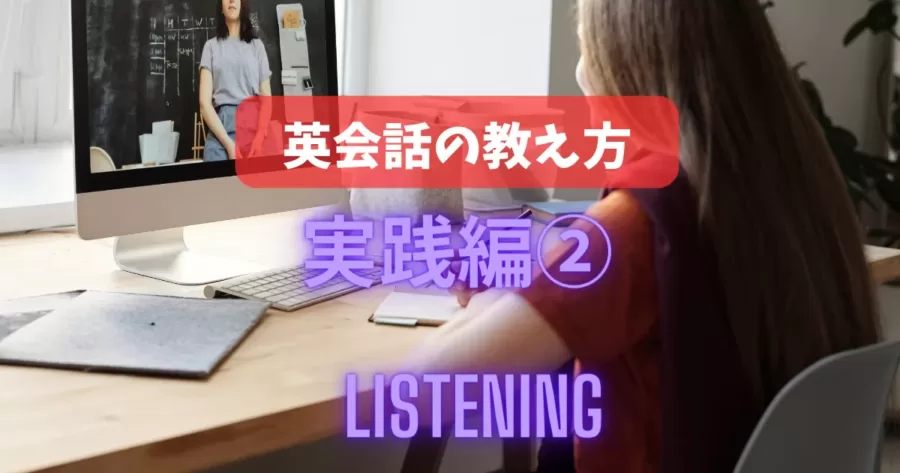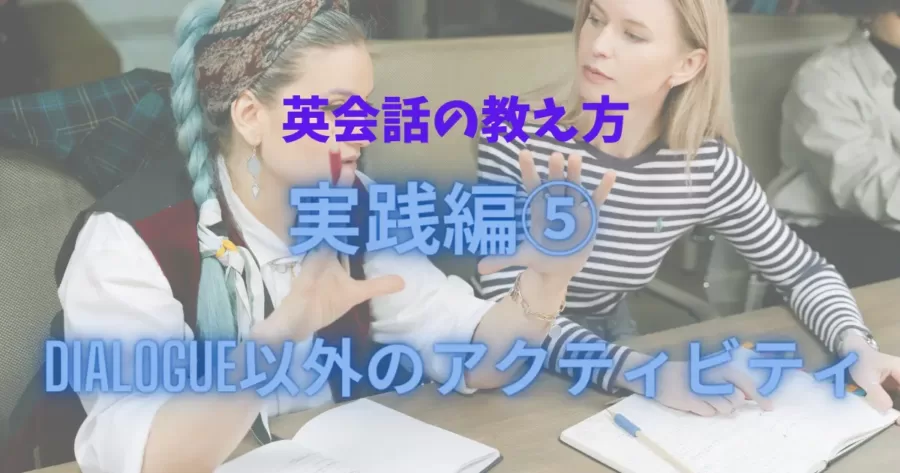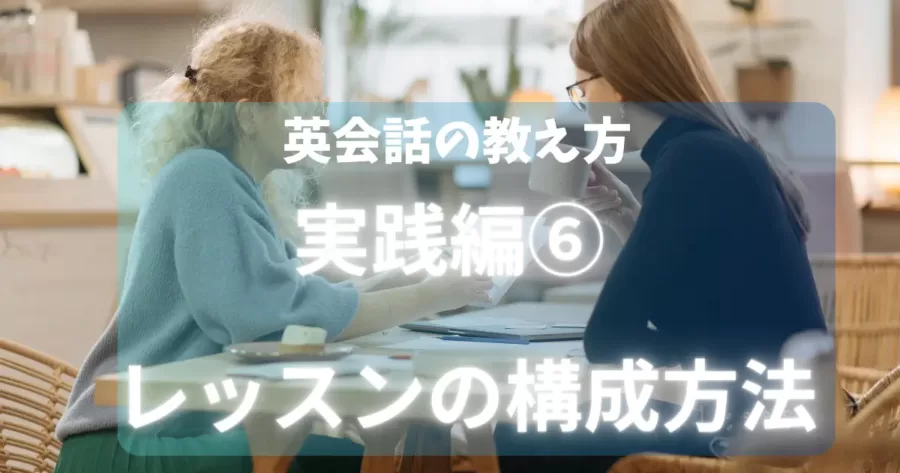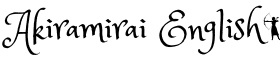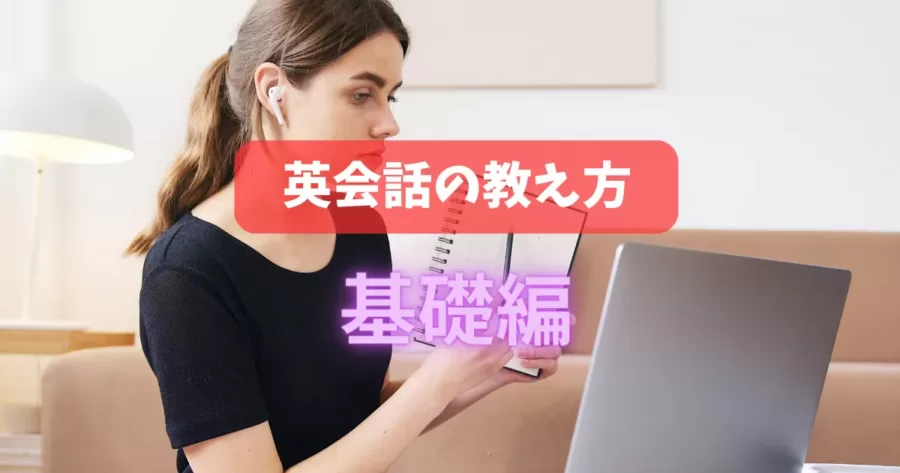「英語を教えてみたい」「英会話を教えてみたい」と思ってみたものの、いざ教えてみようとすると、「どうやって教えたらいいのか」「どんなテキストを使ったらいいのか」迷ってしまう。あるいは、実際に自分の経験を基に英語・英会話を教えてみたものの、「この方法であっているのか不安だ」、「生徒とうまくかみ合わない」などと不安に感じていませんか?
私は留学も長期間の海外生活を送ったこともありませんが、20代前半から英語・英会話を教え始め、その後英会話スクールで、講師トレーナー、教務課責任者、事業部長などを務めながら35年以上にわたり、英語教育に関わってきました。その間に直接教えた生徒は数千人以上、「英会話の教え方」を研修・指導した日本人講師数千人以上、同様に研修・指導した外国人講師数千人以上になります。
これまで私が実際に指導してきた、「英語・英会話の教え方」を簡単にまとめてあります。「英語・英会話の教え方」に関しては、ある「一つだけの正解」はありません。あくまでも、一つの例として参考にしてください。
1. なぜ日本人は英語が話せないのか

よく「日本人はあんなに学校でたくさん英語を勉強したのに、なぜ英語が話せないのか?」と言われたりします。以前に比べると最近では、英語が話せる日本人の数は非常に増えてきました。とは言え、英語が話せない日本人はまだまだたくさんいます。
「なぜ英語が話せないのか?」と言う質問に対して、よく聞かれる答えが「英語を話す機会が無かったから」というものです。これは正しくもあり、間違ってもいます。
- ①日本人は学校で英語を「本当にたくさん」勉強したのか?
-
一般的な公立の中学校・高校の場合、英語の授業は1週間に何時間くらいでしょうか? 英語の授業時間数は少しずつ増えており、週に4時間のようです。私の子供のころよりかなり増えています。と言っても50分授業を4回ですので週に200分(3時間20分)です。学校の場合長い夏休み、冬休み、春休みがありますので、週4回×52週=208回にはならず、年間140時間(回)なので7,000分(116時間40分)になります。
なんかよく分からない時間数ですが、夏休みなどを考慮せず均等に52週で割ってみると週に2.6時間くらいの授業時間という事になります。決して「本当にたくさん勉強した」というレベルではないですよね?
以前外国人講師として働いていたドイツ人講師に聞いたところ、彼女の行っていた学校では週に10時間以上英語の授業があったそうです。この子は非常に英語が上手いドイツ人でした。(当然ながらドイツの学校全てがそうだと言う訳ではないと思います)
いずれにしても、「学校であんなにたくさん勉強したのに」という表現は正しくないと思います、ただし、大学受験などで必死に英語を勉強した記憶が強く残っているのだと思います。
- ②一般的な学校教育の「英語」の目的は「道案内の英語」ではない
-
「日本人はあんなに学校でたくさん英語を勉強したのに、なぜ英語が話せないのか?」と言う文脈で話す時に、「英語が話せる」という意味は、所謂「旅行で使える」とか「日本国内で外国人とコミュニケーション取る」というようなニュアンスで考えられているのだと思います。
最近の英語教育が「コミュニケーション力」に力を入れているとはいえ、学校教育における英語という科目の目的が、「生徒全員が英語で道案内できる」と言うようなことではないと思います。中学生・高校生が成人し、社会人として日本を支えていくための、「教養」や「知識」を身につけるのが学校教育だと思いますので、「生徒全員が英語で道案内できる」ようになっても仕方がないのではないかと。それよりもインターネットその他で英語で情報収集が出来、仕事で簡単なメールのやり取りが出来、大学で専攻した専門分野の文献を英語で読めるようになるための教育があるべき姿だと思います。
実際、学校の英語をしっかりと勉強し、大学受験のための英語の受験勉強を頑張ってきた人は、最初のうちは話せなくても、英会話のレッスンを受けると短期間で急成長することが非常に多かったと思います。その意味でも、本当に英語力が必要になった場合、後々自力で英語力を伸ばせるだけの素地を学校教育で身につけていたのだと思います。
- ③実践力がないのは、「英語」に限った話ではない。
-
この、「日本人はあんなに学校でたくさん英語を勉強したのに、なぜ英語が話せないのか?」と言う議論を聞くたびに、学校の英語の先生方を不憫に思います。なぜ「英語」だけをやり玉に挙げるのか理解に苦しみます。
研修中にこの話をする時にいつも簡単な質問をしていました。「大政奉還は何年ですか?」とか「スウェーデンの首都は?」、「未然連用形を説明して?」とか、非常に簡単な質問です。だいたいみんな答えられません。
このような所謂「暗記物」をテスト勉強一夜漬けで覚えたようなことは、時間がたてば忘れて当たり前です。歴史の年号や国文法の活用形を忘れてしまうのと同様に「3単現のS」を忘れ、「時と条件の副詞節」を忘れてしまうのです。
「英語だけ特別に出来ない」訳ではありません。個人的な意見としては、日本の学校の英語教育は非常に良く出来ていると思います。どちらかと言うと、過度に「コミュニケーション重視」の方向に進んで欲しくないと思っています。
少し話がそれましたが、実践力がないのは、「英語」に限った話ではありません。
- ④「話す機会」を持てば話せるようになるのか?
-
正確には、「話す機会だけ」を持てば話せるようになるのか? と言う意味です。答えはシンプルです。
なりません。
正確には、「多少は話せるようになります。」の方が正しいでしょうか。
「英語によるコミュニケーション力」としてしまうと非常にややこしくなってしまうので、ここでは「英語を話す力」に限定して考えます。「英語を話す力」を考える時に大切な事は、InputとOutputの関係です。この二つは常にこのような関係にあります。
Input > Output
つまり、ごく当たり前の話ですが、Input以上にOutputは出来ないのです。もし知っている単語の数が1000語であれば(Inputです)、実際に話せる単語の数はMAXで1000語です。当然ながら、知っている単語と実際に使いこなせる単語の数には差があります。私の感覚だと使いこなせる単語の数は知っている単語の数の50-60%くらいです。1000語知っているのであれば、実際に使いこなせるのはそのうちの500語から600語程度と言う事です。
知っている単語の数が1000語の人が、ひたすら「話す機会だけ」を追及していると、実際に使いこなせる単語の数が500-600語から徐々に700語、800語と増えていきます。ただし1000語を超える事はありません。
もし、知っている単語数が300語の人であれば、「話す機会だけ」を追及して300語に近づいていく事になります。
この事を理解していない学習者が非常に多く、必要以上に「話す機会だけ」を求めようとします。その結果、直ぐに伸び悩み、上達実感を得られないので、嫌気がさし、挫折してしまいます。
先程、「学校の英語をしっかりと勉強し、大学受験のための英語の受験勉強を頑張ってきた人は、最初のうちは話せなくても、英会話のレッスンを受けると短期間で急成長することが非常に多かった」と説明しました。
もうお分かりだと思いますが、このタイプは圧倒的にInput量が多く、Inputの情報が正確で質が高いのです。なので、「話す機会だけ」を求めても、Inputのレベルが高いので、上達度も高くなります。
反対に、所謂英会話学校に通うタイプの方は、「学校の勉強は嫌いだったけど英会話なら出来そう!」「ワーホリで海外さえ行けば自然と話せるようになるはず!」と考えるタイプで、一般的にInput量が少なく、その知識もあいまいな事が多いようです。そのため「話す機会だけ」を求めても、思うような結果が得られません。
レッスン中に「さぁ、話してください!」と言って、無理やり話させようとしても話せるようにはならないのです。残念ながら、この点を理解しておらず、無言の生徒を黙って放置する講師をたくさん見てきました。
中には「日本人が英語を話せないのは、その性格のためだ!」と決めつけていた講師もいました。”Don’t be shy!” と言って、ひたすら待ち続ける。いくら待っても、知らない単語はいきなり頭の中に降ってきたりしません。
「英会話を教える」時には、常にこの、inputとoutputの問題を意識している必要があります。自分が今実施している練習が、inputのためなのか、outputの練習なのか、これを理解し、意識してレッスンをしていくことが大切です。皆さんが思っている以上に、inputが大切なのだと思ってください。
2. 学校での教え方

大人に英会話を教えていく場合、(この場合の「大人」とは高校生以上と考えてください、つまり中学校3年間の英語を勉強してきていると言う意味です)、「学校で英語を勉強してきた」と言う前提で教えていきます。何らかの理由で、この前提が崩れてしまう場合は、特別な教え方が必要になります。
前述した通り、私は決して「学校英語」の批判者/攻撃者ではありません。日本の英語教育は非常に優れたものだと思っています。とは言っても、中学校と高校の英語の授業だけで英語コミュニケーション力が身につくかというと、ほとんどの場合難しいと思います。これは、学校の英語教育があくまでも「知識としての英語」を目的としているので、そのカリキュラムも教え方も「コミュニケーション」のためのものではないからです。
一般的な英語の授業を思い浮かべてみてください。中学校1年生1学期や「コミュニケーション目的」の時間を除いて、ほとんどの場合、間接教授法で教えていきます。テキストにある英文を辞書を使って解読していきます。当然ながら、英和辞典を使って調べて、「village=村」みたいな感じでノートに書いていきます。そして、テキストの英文をノートに写し、その下に日本語訳を書いていきます。
授業では先生に指名されて、日本語訳を答え、先生が文の構造を説明しながら、正しい日本語に直します。生徒は、先生による日本語の解説と正しい和訳をノートに書きます。復習する場合は、テキストとノートを照らし合わせ、先生の日本語での解説を思い出しながら、正しい日本語訳見てテキストの意味を確認します。
このようにして、予習→授業→復習、そしてテスト勉強と続けます。何時間もかけて一生懸命勉強するのですが、テキストに英語で書いてある内容は、「頭の中で何語で記憶されていきますか?」
残念ながら、英語ではなく、日本語で記憶されていきます。
話せるようになるために、英語のinput量の大切さを説明しましたが、この勉強法では残念ながら、あまり英語がinputされていかないのです。英語と日本語と比較すると、圧倒的に日本語が強いので、日本語で記憶されていってしまいます。
また、テキストの内容が中学校2年生くらいから急速に難しくなっていきます。中学校3年間で学ぶべき文法事項と語彙数が決まっているので、それは仕方がないことなのですが、文型も複雑になってくるので、テキストの「解読化」が進みます。文章を一度最初から最後まで目を通し、文型を確認して、日本語に組み替えます。
例えば、このような文章があれば、まず最初のOnから最後のplaceまで目を通します。
On my way home, I saw a woman that I met at the party my boss held a few weeks ago, which I should not have gone to in the first place.
そして文章全体の主語と動詞、目的語や補語などを探します。
- I 主語 「私は」
- saw 動詞 「見た」
- saw 動詞 「見た」
- a woman 目的語 「女の人を」
→ 「私は女の人を見た」
そしてこのa woman を関係代名詞thatで修飾している事を発見します。
- a woman 「女の人」
- that I met at the party 「私がそのパーティーで会った(ところの)」
さらにこのpartyを、省略された関係代名詞whichで導かれた節で修飾している事に気づきます。
- the party 「そのパーティー」
- (which) my boss held a 1few weeks ago 「 私の上司が開いた(ところの)」
しかしながら、関係代名詞を訳すときに使う、この「ところの」という日本語の意味がいまだによくわかりません。
このように解読していき、さらに「自然な日本語」に修正します。
「私は、上司が2,3週間前に開いたパーティーで会った女の人を見かけた。」
このような作業をしているはずです。
当然ながら、「解読している」時間も、「意味を考えている」時間も、「正しく、自然な日本語に組み直している」時間も、全て日本語で考えているので、この英文も頭の中で日本語で記憶されていきます。
これはこれで大切な勉強なのですが、この読み方に集中してしまうと、英語を読む速度が圧倒的に遅くなります。また、一度最後まで読んで、それから文の構造を考えて意味を理解しようとするので、この読み方をしている限り、同じ文を聞いて理解することはできません。Listeningの時は、音は待ってくれないのです。文の最後までいって文型を考えている間に、次のセンテンスに進んでしまいます。
文法に関しては、中学校で勉強する文法事項は必要不可欠な項目だし、中学生向けの文法問題集もよくできているものが多いので、もう一押しです。学校の勉強やテスト勉強だと、やはり「知識のための英語」なので、「何となく頭で理解している」状態です。
例えば、過去形を例に挙げると、
I (go) to the movies yesterday.
よくあるパターンですね。
これを中間テストとかで解く場合、結構時間を掛けられます。生徒は頭の中で、「yesterdayだから過去形だ。goを過去形にすればいい。goは不規則動詞だから、edをつけてもダメだ。goの過去形は、wentだ」みたいに考える時間があります。まぁ、10秒から20秒掛けたとします。
これが会話だと、
 講師
講師What did you do yesterday?
 生徒
生徒I ……
これを答えるのに、10秒から20秒掛かったらどうですか?
20秒ってかなり長いので、タイマーで測ってみてください。とてもじゃないけど、待てるもんじゃないです。
また、常に目で文字を見て考えているので、文字がなくなると途端にわからなくなってしまいます。スピードと音の二重苦ですね。
「スピード」と「音」と言うと全く別の事のように思えるかもしれませんが、実は非常に似通っています。「スピード」と言うのは、「何となく頭で理解している知識」をフル活動させて、何とか「アウトプット」するために必要な時間を指します。この時間が人の話す速度に追いつかないと、「スピード不足」で話せないと言うことになります。つまり頭の中でのプロセスのスピードです。
「音」の問題も初心者の場合、耳で聞いた音(英語)を、頭の中で「文字起こし」します。その文字起こしにかかる「時間」と、「文字起こし」した文やフレーズを「解読」するのに要する「時間」です。つまり、こちらの場合も頭の中でのプロセスのスピードです。
学校の英語の授業で、大切な文法事項は勉強してきているのだけれど、「何となく頭で理解している知識」の段階なので、「コミュニケーションとして使えるレベルの文法力」に昇華させるためには、「頭の中でのプロセスのスピード」を大幅に上げていかないといけない。また、文字に頼らず、音だけで理解できる力もつけていかないといけない、と言うことになります。
ライティングと言うか、「英作文」の時間があると思います。和文英訳ですね。恐らく中学1年-2年くらいまでの英語の授業で行われている「和文英訳」は全く問題ないと思います。と言うか、非常に有効です。こんな感じの練習です。
次の日本語を英語に直しなさい。
- トムは昨日ジムと公園で野球をした。
- 私はアメリカに一度も行ったことがない。
- 彼は毎朝8時に起きます。
なぜこれが全く問題がなく、非常に有効かと言うと、テキストで「基になる英語/英文」を勉強しているので、その英文の1部の単語を置き換えるだけで済むからです。つまり、1から10まで「英作文」する必要がなく、「英借文」しているからです。「英借文」している限り、変な英語になりません。練習することによって、基本英文が定着していきます。
ところが、高校の「英作文」になると、極端に難しくなってしまいます。
次の文章を英訳しなさい。
- 若いうちはお金を払ってでも苦労を買えと言う話をよく聞く。確かに困難を乗り越える努力をすることは非常に大切だし、その過程で学ぶことも多い。また、必ずやり遂げると言う精神力を養うこともできる。しかしながら、どんな苦労でもすべきだと言うことにはなるまい。
こうなると、もう手に負えません。和英辞書を頼りに、無理矢理「英作文」します。「英借文」しようにも、「基になる英語/英文」が見えてこないのです。仕方なく、無理矢理「英作文」してしまいます。残念ながら、限りなく意味不明なジャパニーズイングリッシュになってしまいます。時間に無駄にしかなりません。
実際には、「書く力」と「話す力」は非常に密接に関係しているので、「コミュニケーション力」を伸ばすには、「書く練習」は非常に大切です。とは言え、「週1回の英会話レッスン」ではレッスン時間内に「書く練習」のために割く時間はありませんので、工夫が必要になります。
リスニング、発音、文化的違い、など大切なことは他にもありますが、これらは通常の学校の授業ではほとんど扱っていません。「書く力」と「話す力」は非常に密接に関係しています。「リスニング」と「読解」も密接に関係しているのは分かると思います。同様に、「リスニング」と「発音」の練習も非常に密接に関係しています。
特に、大人が英語を学ぶ時には、「発音」に関しては、「頭で理屈で理解する」事が非常に大切になります。
残念ながら、「週1回の英会話レッスン」ではレッスン時間内に「発音の仕方を頭で理屈で理解する」のために割く時間はありませんので、こちらも工夫が必要になります。
3. 代表的な教授法

これまでに英語や英会話を教えた事がない人には、「英会話を教えるためには英語教授法を勉強しなければいけない!」と思うかもしれません。でも実際には必要ないと思います。と言うのも、例えば英会話スクールで英語を教える場合、それぞれのスクールで独自の考え方や方針に基づいた「そのスクールの教え方」が存在します。「そのスクールの教え方」で講師にレッスンしてもらうために「研修」を実施し、「研修」を終了した人が教え始めます。研修期間中に脱落する人も少なくありません。
スクール毎に存在する「そのスクールの教え方」に関しては、似ているところもあれば違うところもあります。あるスクールでは「良し」とされることも他のスクールでは「ダメ出し」されることも結構あります。恐らく、英語・英会話を教えるという仕事をしていなければ、気づかないようなこと、どうでも良いとも思われるようなことに、ひどく拘っている事もあるようです。
もし皆さんが、どこかの英会話スクールで教えようと思っているのであれば、「英語教授法」の勉強はしない方がいいと思います。「英語教授法」で何を学んだかに関わらず、ある英会話スクールで教えるのであれば、そのスクールの研修通りに教えないといけないからです。ある意味当たり前ですよね。ラーメン屋さんやお寿司屋さんと一緒です。「〇〇軒」とか「〇〇亭」と言う看板に魅かれてお客さんは来るわけなので、その期待値に応えないといけません。個人の知識が反映されるのは、その個人の実績が積み上がってきてからです。
とは言え、ある程度の知識は持っているに越したことはないので、ここでは最低限知っておくと役に立つ(かもしれない)教授法に関する情報を上げていきます。
まずは大きな枠組みから
- ①TESOL
-
Teaching English to Speakers of Other Languages と言う意味です。「英語を母語としない人に対して英語を教える」と言う教授法全般の事です。大学などで「教授法」を学ぶ場合は、これが一番多くなると思います。ただし、「学問」「研究」の意味合いが強く、あまり実践的なイメージはありません。
- ②TESL
-
Teaching English as a Second Language の略です。②のTESLと③のTEFLはペアで覚えると良いでしょう。簡単に言ってしまうと、学習環境の問題です。TESLは日常的に英語が使われている環境で英語を教えると言う事です。イメージしやすいのは、フィリピンとかインドとかでしょうか。英語圏で移民や留学生などに教えるのもこちらの枠組みになります。
- ③TEFL
-
Teaching English as a Foreign Language の略です。②のTESLが日常的に英語が使われている環境で教える、に対して、③のTEFLは日常的に英語が使われていない環境で教える、と言う事です。日本で英語を教える場合はこちらになります。韓国や中国で教えるのも同じです。
次は英語教授資格です。
- ①CELTA
-
The Certificate in English Language Teaching to Adults の略です。
- ②DELTA
-
The Diploma in English Language Teaching to Adultsの略です。
どちらもイギリスのケンブリッジ大学の検定機構が認定している教授資格で、DELTAがCELTAの上位になります。私自身、過去に何人もCELTAやDELTAの資格を持っている外国人講師を採用してきましたが、特別な印象は残っていません。
そして、具体的な教え方ですね。この3つの中ではこれが一番大切です。
最初の二つは使う言語の問題です。③以下はより具体的な教え方です。
- ①間接教授法
-
簡単に言ってしまうと、その国の母語を使って教える。日本の場合であれば、「日本語を使って教える」と言う事です。
- ②直接教授法
-
簡単に言ってしまうと、「英語だけを使って教える」と言う事です。
①間接教授法と②直接教授法のメリット・デメリットを比較するとちょうど正反対になります。
| メリット | デメリット | |
| 直接教授法 | 聞く・話す力が養える | 分かりにくい |
| 間接教授法 | 分かりやすい | 聞く・話す力が伸びない |
基本的にタイプの全く異なる方法なので、その目的が大きく異なります。間接教授法は知識のための学習に向いています。そのため所謂学校教育に適しています。直接教授法は実践力向上のための学習に向いています。そのため英会話スクールに適しています。
皆さんが、英会話スクールで教える、あるいは英会話を中心に教える、と言う事であれば、直接教授法が中心になります。
- ③グラマートランスレーション
-
日本語、というか、カタカナで書くとかなり違和感ありますね。Grammar Translation Methodです。間接教授法の一種で、文法の説明をして文の構造を理解させ、和訳させて(日本で教える場合)、生徒の理解度を確認すると言う教え方です。つまり、学校教育における英語の授業そのものです。弱点は、間接教授法の弱点そのままです。「聞く」「話す」と言うコミュニケーション力はあまりついてきません。
- ④ナチュラルアプローチ
-
Natural Approachです。大人が外国語を学ぶ方法は、子どもが母語を身につける過程と同じ方法で学ぶという考え方です。子どもが母語を身につける順序は、「聞く」→「話す」です。なので、「まず聞く」事から始めます。「聞く」事を続けていくと「話す」事もできるようになると言う考え方です。考え方は間違っていないと思いますが、弱点は時間がかかり、「タイパ」が悪い事です。
- ⑤オーディオリンガルメソッド
-
Audio-Lingual Methodです。この記事は、教授法を系統立てて学ぶのが目的ではありませんので、教えたことのない人が「英会話を教える」ために最低限必要な知識として、分かりやすく理解できるように書いています。そのためAudio-Lingual Method に関しても、かなりシンプルな言い方で説明していきます。
簡単に言ってしまうと、「会話文の丸暗記」と「文型のパターン練習」です。基本的な文系を、例文を暗記し、機械的な口頭練習を繰り返して、定着させていきます。元々はアメリカの軍隊で外国語習得のために使われていたようです。
基礎力が定着し語学力向上が見込まれる方法ですが、弱点もあります。文法的に学習していくことになるので、ちょうど中学校の英語の授業のように、現在から始めて過去形、未来形、肯定文、否定文、疑問文、などのように少しずつ積み上げていきます。そのためあまり即刻性はありません。また、丸暗記とパターン練習のように単調な練習を繰り返し続けていくので、あまり「楽しく」ありません。なので、上達度の個人差が大きく、挫折する確率もかなりあります。
- ⑥コミュニカティブアプローチ
-
Communicative Approach です。Audio-Lingual method が文法的な教え方だったの対して、Communicative Approach は Function 中心に進めます。例によって、簡略化して説明をしますが、Function とは「〇〇の仕方」と覚えてください。
例えば、「頼み方」「断り方」「謝り方」などです。よくある「旅行英会話」のテキストなどはFunction中心に学習していくので、「オーダーの仕方」「苦情の言い方」「チェックインの仕方」などを学びます。
Communicative Approach では、文型などにあまり拘らず、「目的を達成する」ためのコミュニケーションを重視します。疑問文でも過去形でも、単文でもフレーズでも、あるいは単語1語でも、構わないので、「オーダーできる」ようにコミュニケーション取る練習をしていきます。
利点は即刻性があると言うことで、レッスンを受ければ「すぐにオーダーできる」と言うようにレッスンの成果を感じる事ができます。反対に弱点は、この教え方だけでは「伸び悩む」と言う事です。Communicative Approachのレッスンは、「場面毎につける表現を覚える」的なレッスンになりがちです。この練習だけだと、あまり応用が効かず、「英語が話せない人がサバイバルレベルの英語力を身につける」のには有効だけど、「中級・上級レベル」まで向上させていくことは難しいことが多くなります。
「英会話を教える」ための基礎知識としてはこのくらいで十分だと思います。一番理解して欲しいことは、現時点では「ある一つの方法で、全学習者に有効な完全な一つの教え方はない」と言うことです。
なので、英会話スクールや語学学校では、それぞれのメソッドやアプローチ、方法を、そのスクール毎の解釈で組み合わせている、その組み合わせ方法がスクール毎に異なると言うことです。
結果的にどこのスクールでも、かなり似通った教え方になっています。多くの場合、Audio-Lingual Method と Communicative Approach のミックスで、その割合がスクール毎に異なります。更に、他の要素をどのくらい混ぜるかによって変わってきます。
もし、英会話スクールで講師として働いてみたい、と思っているのであれば、面接に行く前にそのスクールの「教え方」を調べてみると良いでしょう。デモレッスンをする時に、Audio-Lingual よりにするか、Communicative よりにするか、自分で調整する事ができるレベルになっていれば採用される確率は高くなります。反対に、ある一つのスクールでどれだけ経験を積んでいたとしても、違う教え方を使っているスクールに行くと「悪い癖がついてしまっている」と敬遠されることにもなりかねません。
4. テキストとシラバスについて
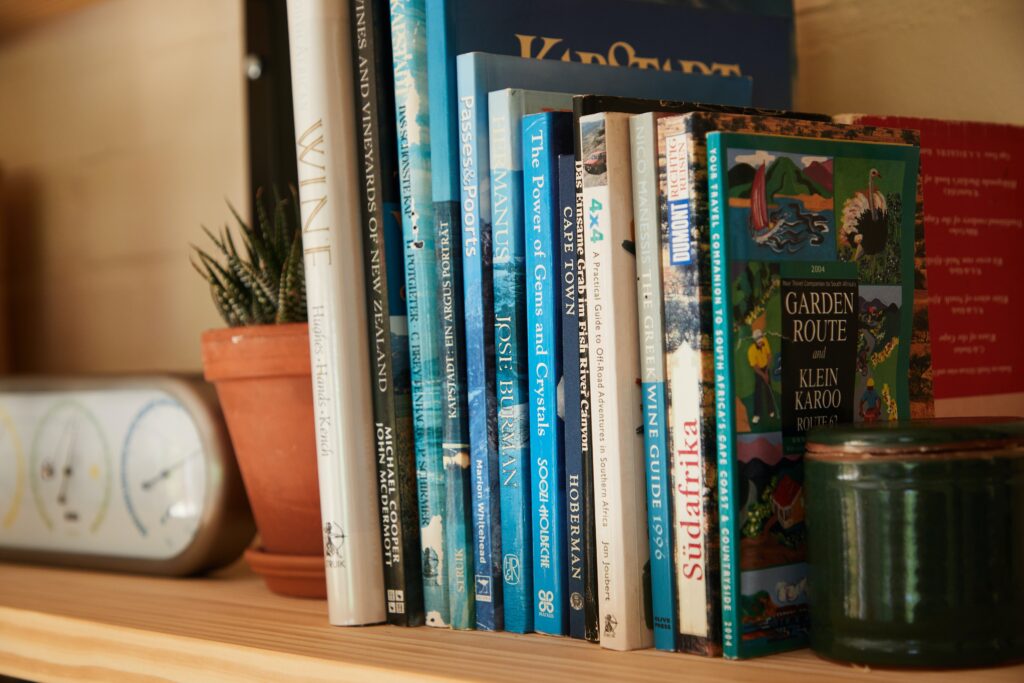
既に説明しましたが、テキストをよく理解して教える事は非常に大切な事です。テキストを理解せずにレッスンをして、「完全に的外れなレッスン」をしている講師を数多く見てきました。やはり、ネイティブスピーカーや英語力の高い日本人講師からすると、初心者や中級者向けのテキストはシンプルなものが多いので、「教えるのも簡単」と勘違いしてしまうのでしょう。
出鱈目にテキストを作る人はいませんので、特に教育出版社が出版しているテキストは時間をかけて開発されています。シラバスを作り、言語レベルを考慮し、語彙・表現、文型、その他をレベル毎に到達目標を設定し、全体の構成を組み立てていきます。そのテキストがどのような方向性、方針で作られ、どのような目標に向かって、それぞれの練習が何を意図しているのか、しっかりと把握していく事が大切です。
語学学習用のテキストにはいろいろな種類、例えば、リスニング教材、文法書、TOEIC/TOEFLなどのテスト対策、旅行英語、など多種多様です。ここでは、所謂「英会話レッスン用」のテキストについてみていきます。
1)シラバス
まず一番最初に確認する必要がある事に「シラバス」があります。そのテキストが、「何をポイントにおいて構成されているか」と言う事です。一つ一つのユニット/レッスンの学習ポイントが、文法であれば「文法シラバス」、Functionなら「Functionシラバス」です。「Functionシラバス」のテキストで、講師が勝手に「文法中心」のレッスンをしてしまっている事をよく見てきました。
レッスンは「1回1回のレッスンで何を学ぶか」と言うことだけでなく、「1回1回のレッスンの積み重ねで、1年後にそのテキストを修了した時に、何が出来るようになっているか」を意識する事が必要になります。講師が勝手にテキストの方向性を無視してレッスンしてしまうと、1年後も何もあったものではありません。
では代表的なテキストのシラバスを見ていきます。
- ①文法シラバス
-
各レッスン/各ユニットの目的が、文法項目のテキストです。例えば、
Unit 1 現在形
Unit 2 過去形
Unit 3 未来形
のようなテキストです。
- ②Function シラバス
-
各レッスン/各ユニットの目的が、Function のテキストです。分かりやすい例だと旅行英語ですね。
Unit 1 チェックインの仕方
Unit 2 レストランでのオーダーの仕方
Unit 3 ホテルでの苦情の言い方
などです。
- ③Vocabulary シラバス
-
各レッスン/各ユニットの目的が、語彙力のテキストです。
Unit 1 体の部位
Unit 2 家具、家電、部屋の中にある物
Unit 3 食材と台所用品
などです。
- ④マルチシラバス
-
各レッスン/各ユニットの目的が、文法、Function、語彙、リスニング、など複数のターゲットがあるテキストです。
この20年くらいは、このタイプのテキストが非常に多くなっています。
なので、一番分かりやすいのは、それぞれのテキストの目次を良くみる事です。そして、「テキストの使い方」のページを端折らないで、しっかりと読むこと。シラバスを理解し、テキストの方向性が掴めれば、それに合わせた教え方も見えてきます。
反対に、既に教え方が決まっているスクールが、市販のテキストを使用してレッスンをする場合は、「スクールの教え方」に合わせてテキストの使用方法を調整していく必要があります。具体的実践編で説明しますので、ここでは、テキストの見方を理解してください。