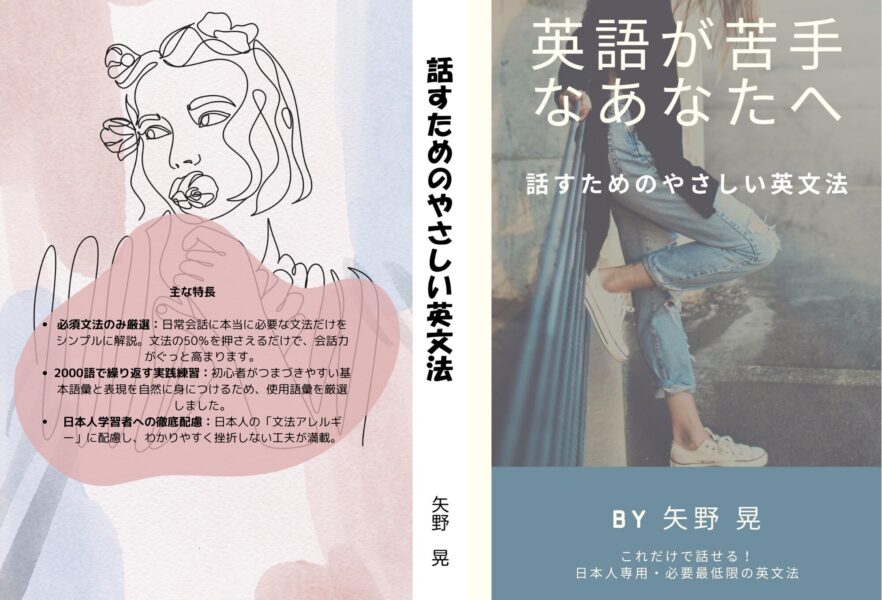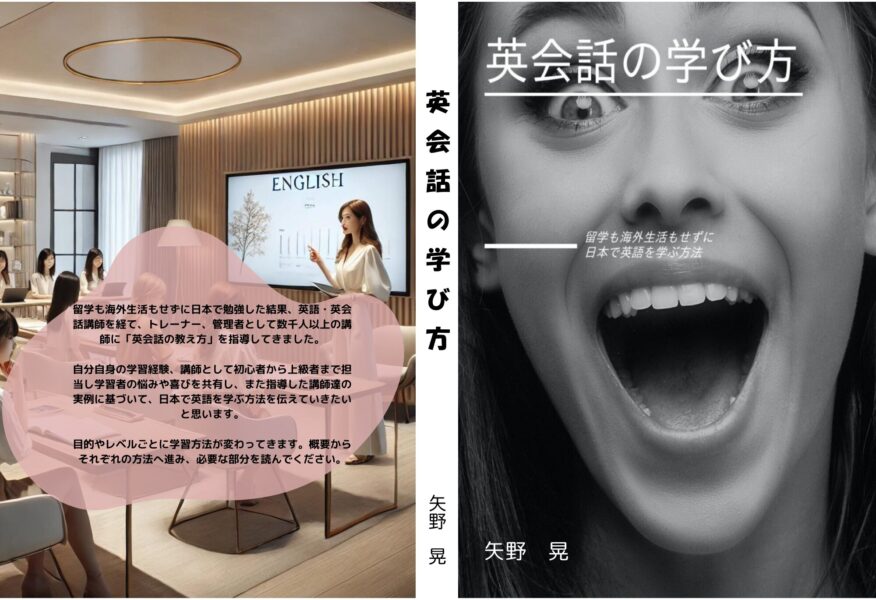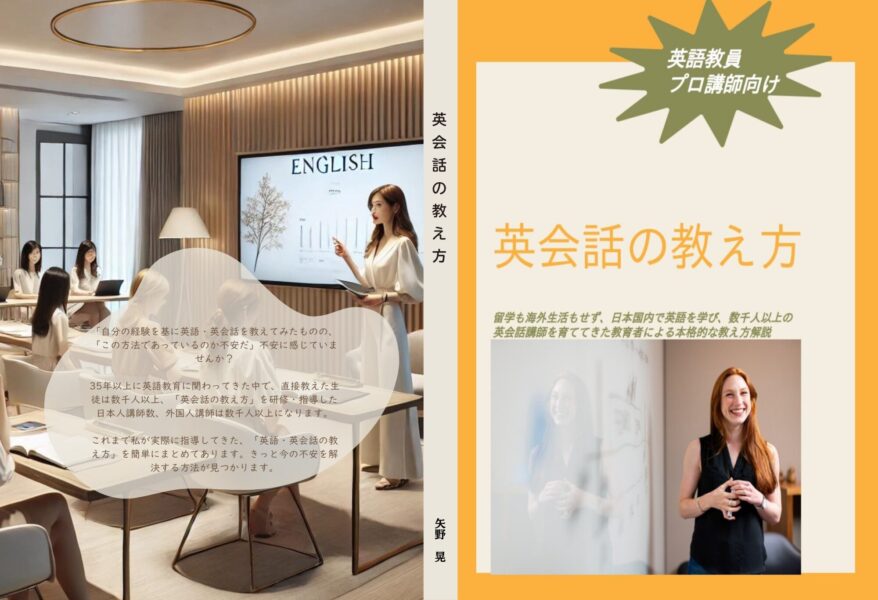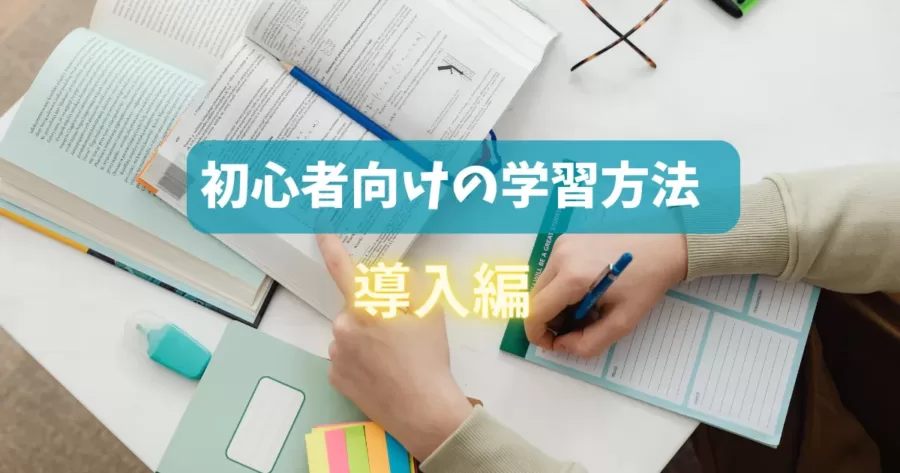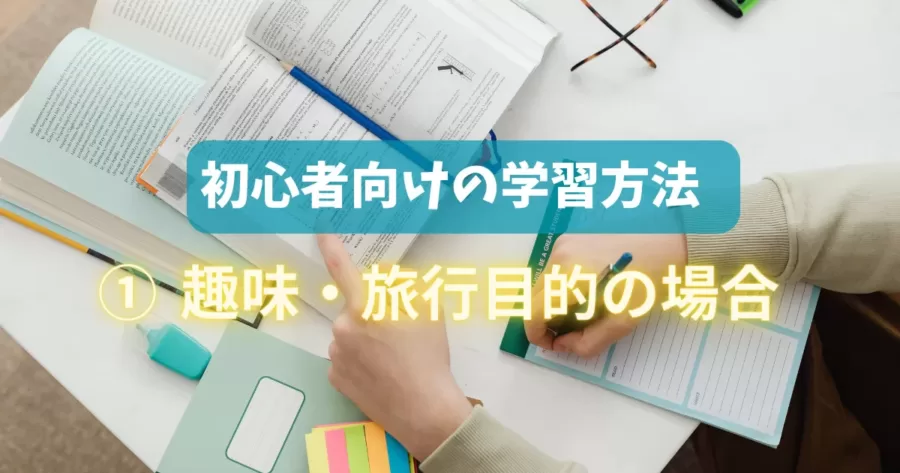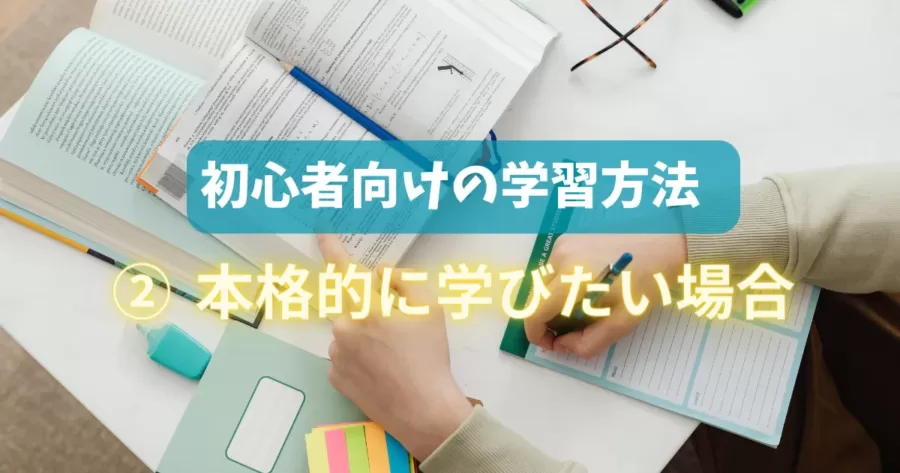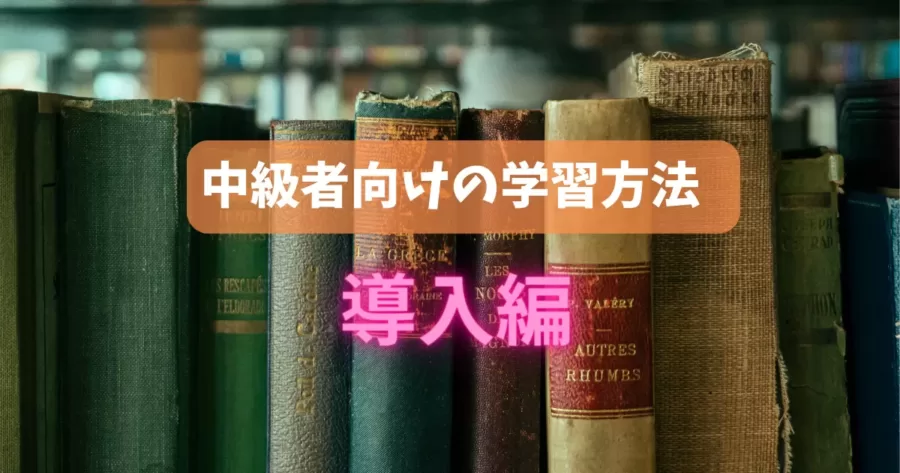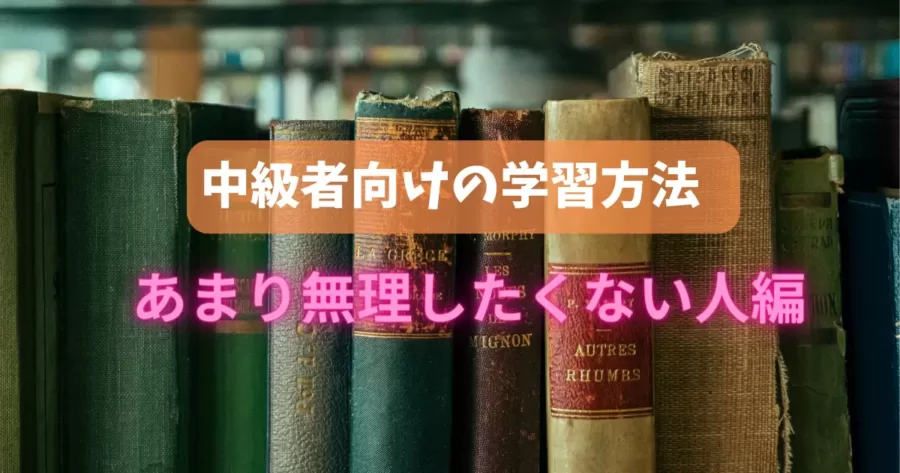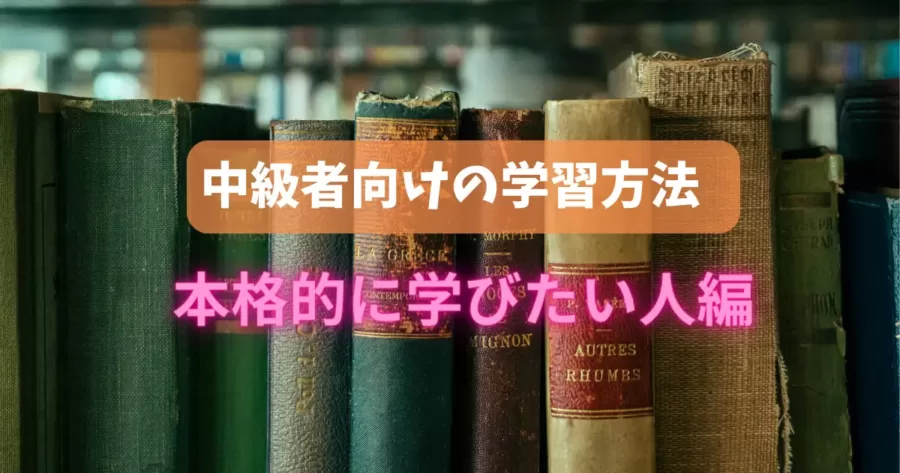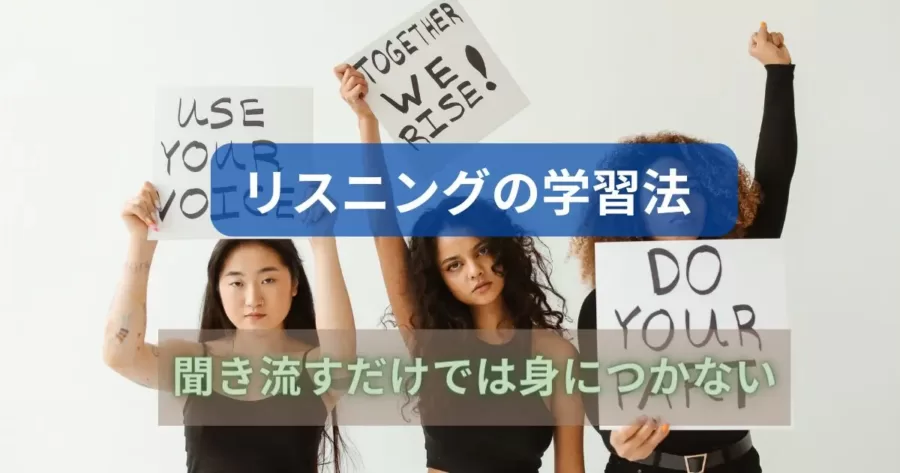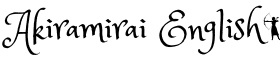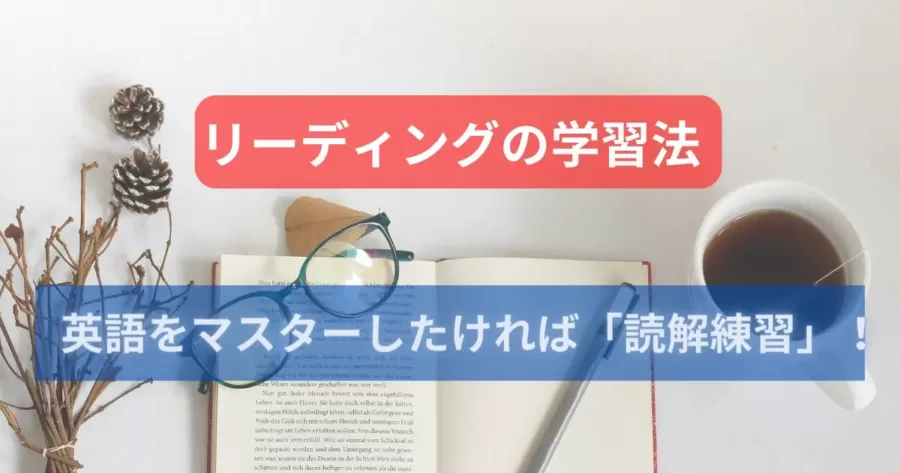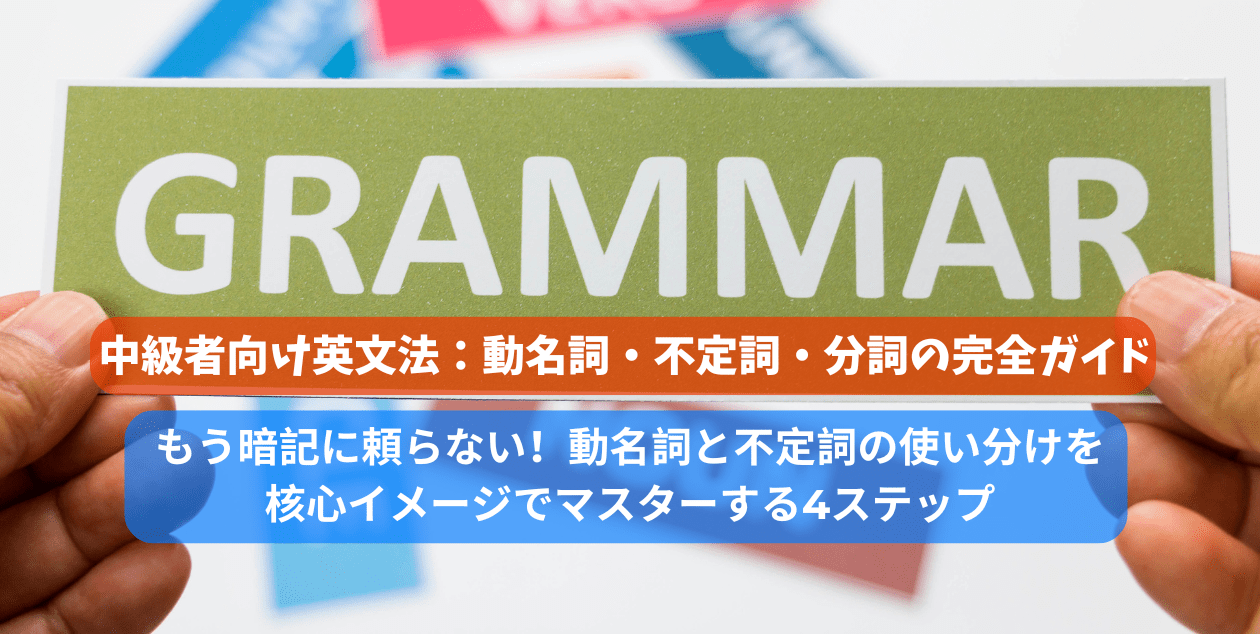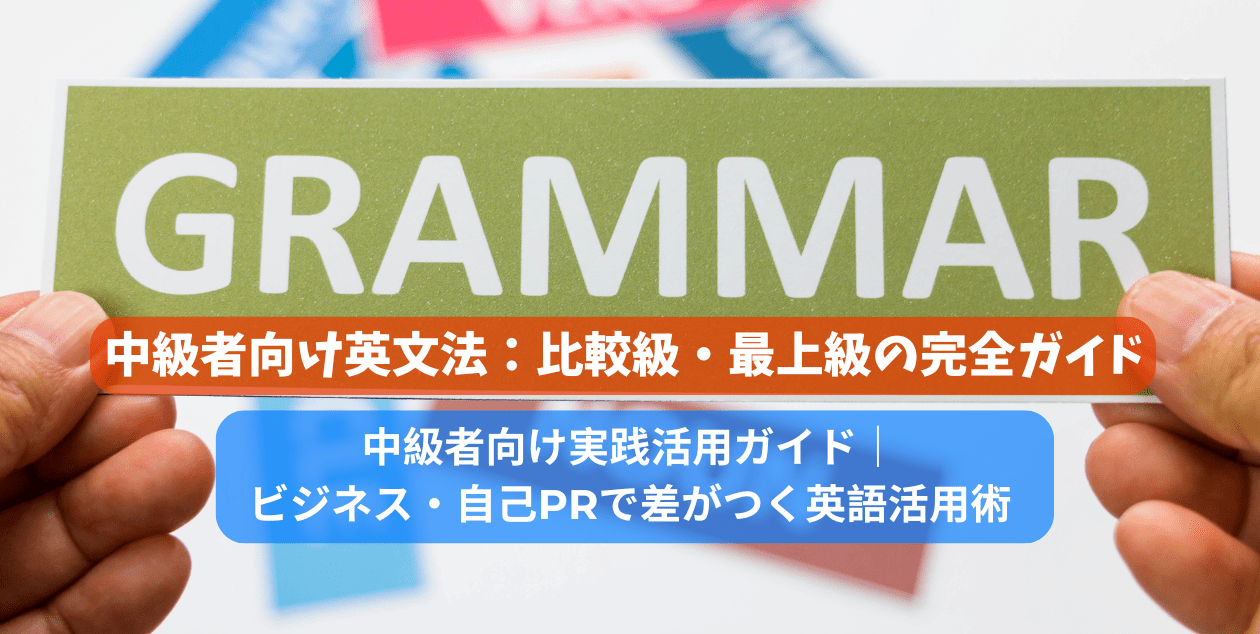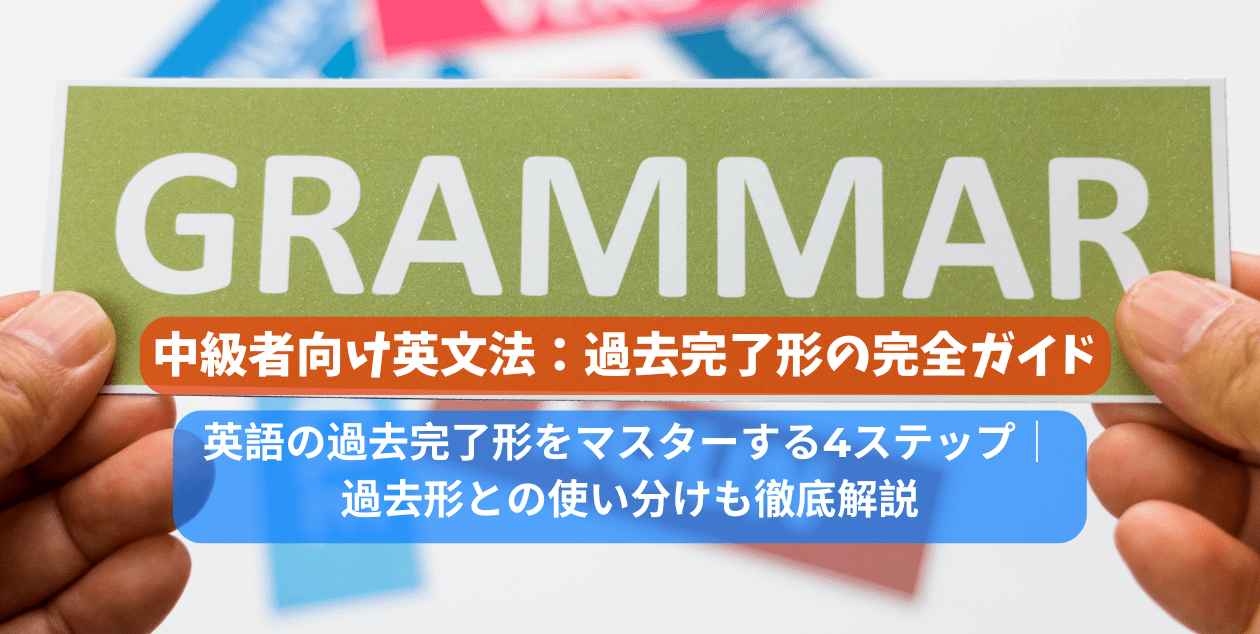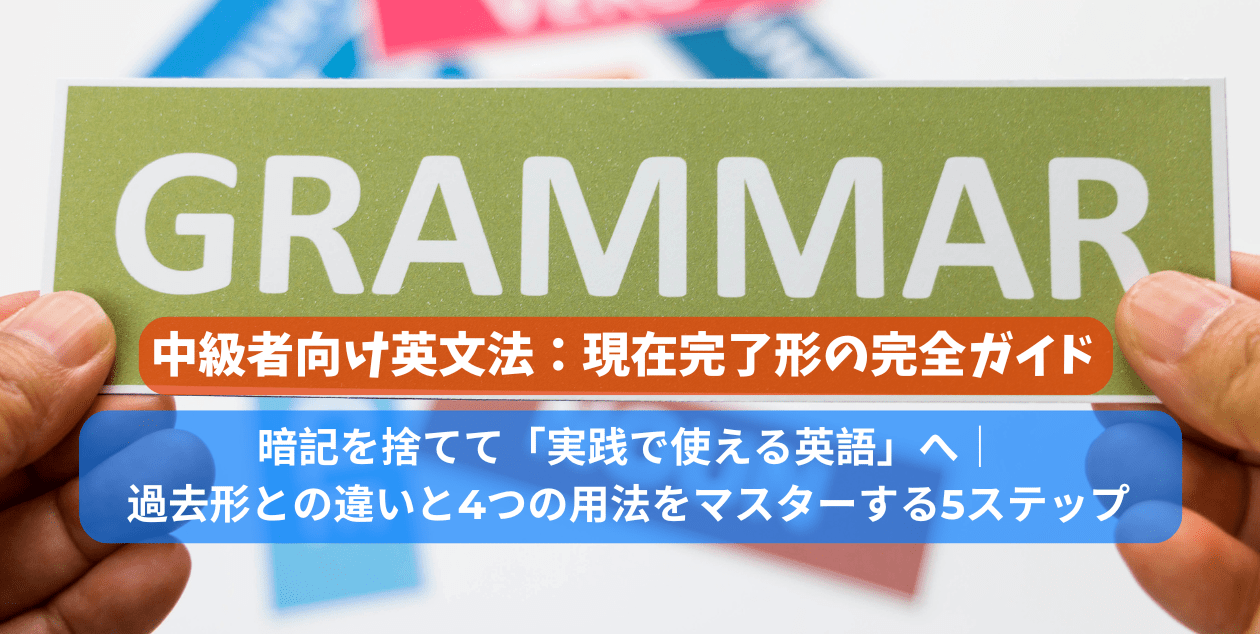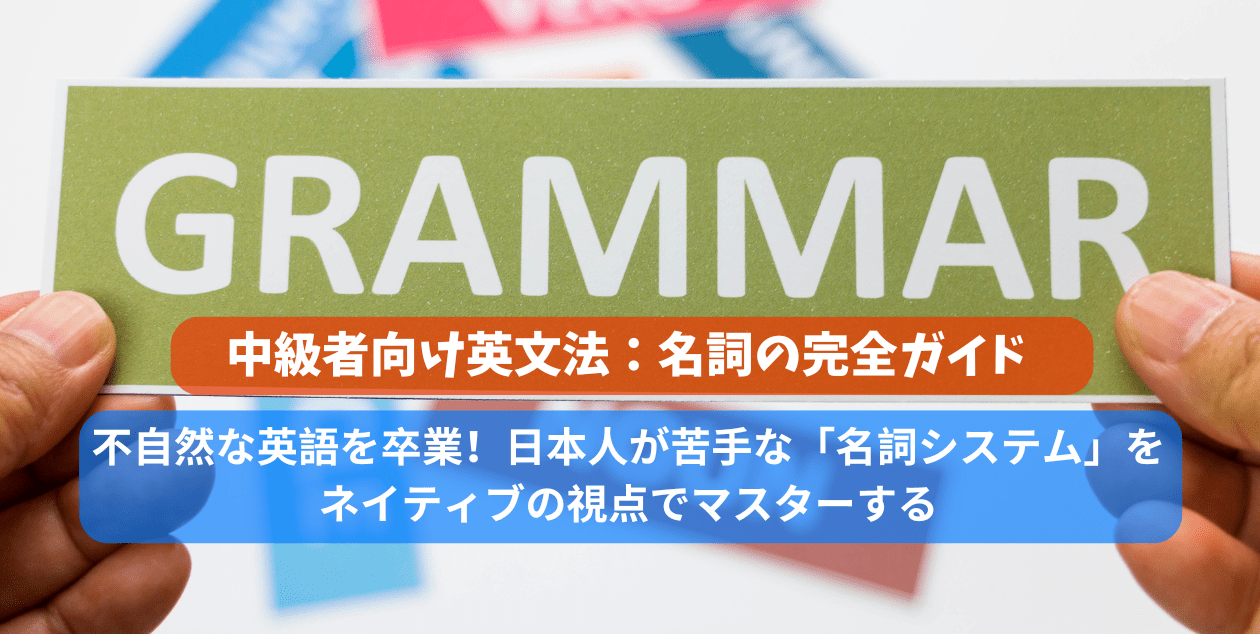「読解」「リーデイング」は語学学習において、非常に大切な練習になります。初心者の方で、「英会話」と「英語」が別の物と考えている方には理解しにくいと思いますが、語学学習の中で「読解」「リーデイング」が最も大切と言っても過言ではないと思います。外国語として語学を身につけた人の多くは、その学習において「読解」「リーデイング」に多くの時間と労力を割いています。
いつも例に挙げる「正規留学」の場合を考えてみるとわかりやすいと思います。英語圏の4年生大学に「正規留学」をして卒業した人の多くは高い英語力を身につけています。それは必ずしも「英語圏で生活をしたから」だけではありません。大学の授業のために、毎日毎日大量の「読解」が課せられます。その積み重ねが英語力向上に寄与しているのです。「読解」を通じて、大量にインプットし、語彙力を強化しているのです。
もし高い英語力を身につけたいと思っているのであれば、「読解」に時間を掛けることをお勧めします。反対に、もし「旅行に行った時、ちょっと使えたら良い」くらいの目標設定なら、無理して「読解練習」する必要ありません。こちらの記事を参考にしてください。
中学校1年~3年のテキストをマスターする

いきなり「読解練習」に入っても良いのですが、効率よく「読解練習」するために、まず下準備をした方が効果的です。少し時間をかけて、中学校の教科書を復習してみましょう。
なぜ中学校のテキストなのか?
英語学習に関してよく言われる事の中に、「中学英語をマスターすれば英語は話せるようになる」と言う表現があります。ちょっと誤解を与える表現なので、こう言い換えた方がいいでしょう。「英語を話せるようになるには、中学英語をマスターする必要がある。」
まだ誤解を与えてしまう可能性があるかも知れません。この表現を聞いて、「ひたすら中学校の教科書をノートに書いて丸暗記する」みたいな行動に走ってしまうと、思うような結果が得られないかも知れません。
「中学英語をマスターする」と言うのは、必ずしも「中学校の英語教科書を丸暗記する」と言う事ではないのです。(ただし「中学校の英語教科書を丸暗記する」と言う勉強法は無駄ではありません。)「中学英語をマスターする」と言うことは、「中学校で学ぶ基本文型、単語、熟語、表現、文法などを身につける」と言う意味です。
「中学校で学ぶ基本文型、単語、熟語、表現、文法などを身につける」と言うことが出来れば、中学校の教科書である必要はありません。このサイト内での「初心者、中級者、上級者」の定義を書いた部分で、それぞれの文法レベル、語彙レベルは簡単に説明しました。初心者、中級者が使えるべき文法事項や語彙力を身につけると言うことです。
もし中学校時代の英語の教科書にあまりいい思い出がなければ、他のテキストでも構いません。要するに中学校レベルの基本的なテキスト、それも文法、語彙・表現など、幅広くバランスの取れているテキストであれば何でも構いません。ただし、もし中学校の英語の教書に抵抗がないのであれば、教科書を使ってみてください。やはり非常にバランスの取れた良いテキストですので。
中学校のテキストをどのように使って勉強するのか?
非常にシンプルな方法です。まず音読してください。可能であれば音声教材も活用してください。教科書準拠のCDなどが販売されているはずです。音声教材があればこんな順番を試してみてください。
教科書を閉じて音声を聞く
まず、文字を見る前に「音から」入ります。
教科書を目で追いながら音声を聞く
文字を見て、視覚と聴覚を一致させます。
教科書を閉じて音声を聞く
一度目で文字を見て安心出来たと思いますので、音に集中してください。
(時間に余裕があれば)センテンスごとに止めてノートに書き留めてみてください。
出来れば、書き取ってみてください。どのくらい正確に聞き取れているか確認できます。
教科書を見ながら、センテンスごとに止めてリピートする
焦る必要ありません。ゆっくりと正確にリピートしてみてください。
教科書を閉じて、センテンスごとに止めてリピートする
文字を見ずに、音に集中して正確にリピートしてください。
教科書を閉じて音声を聞く
この段階で、確実に聞き取れるようになっているはずです。聞きながら、意味が頭の中でイメージできれば完璧です。
英語が苦手だと思っている人も、おそらく中学校1年生の教科書であれば、それほど難しく感じないでしょう。人によって、2年生の教科書に入る頃から難しく感じ始め、3年生のテキストになるとかなり難しく感じるかも知れません。わからなくなってしまっても、あまり気にせず、先ほどの7つのステップを繰り返してください。
語学学習で非常に大切なことは、「100%の習熟度を求めない」と言うことです。今分からなくても、そのうち分かるようになります。非常に無責任な言葉に聞こえるかも知れませんが、語学学習ってそう言うものです。
例えば、「数えられる名詞」「数えられない名詞」、「単数、複数」、「定冠詞と不定冠詞」とか、中学校1年生の教科書から出てきます。よく分からないかも知れません。これらは、日本語にないコンセプトなので、あまりピンとこないからです。中学校の教科書に全てが詰まっているとは言え、まだまだ絶対数・絶対量、サンプル数、が足らないのです。
もし知っている単語数が50語とか100語と言うレベルであれば、「数えられる名詞」「数えられない名詞」に関して、その違いを理解するのが、あるいは体感するのが難しいでしょう。それが、学習を続けるうちに、知っている単語数が3000語とか5000語くらいのレベルになると、数多くの「数えられる名詞」「数えられない名詞」に出会ってきているので、サンプル数が増え、自然と「数えられる名詞」「数えられない名詞」の違いが理解できるようになるのです。
なので、「なんかよく分からないなぁ」と思っても、あまり気にせずに先へ先へと学習を続けてください。数ヶ月経つ頃には、以前分からんかった事が、「なんであんなにむずかしく感じたんだろう」と思えるようになります。
中学校の教科書は、「英語を話せるようになるには、中学英語をマスターする必要がある。」と言う非常に大切なものなので、粘り強く、最後まで続けてみてください。わからない事があっても気にしない、気にしない。気にせず、「先へ、先へ」と進めていってください。
ある程度復習できたら、いよいよ「読解練習」の始まりです。
学習者向け初心者用Reading教材を多読する
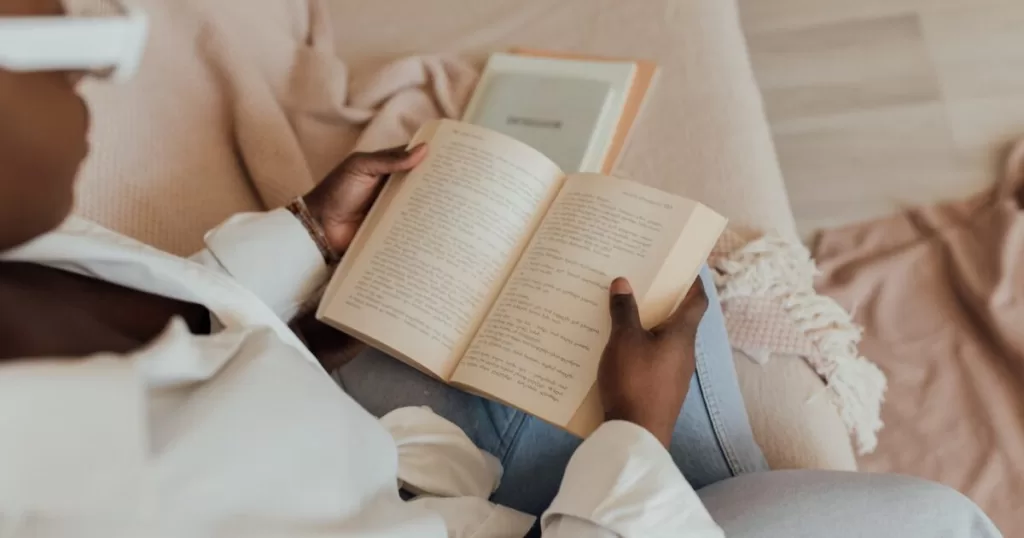
なぜ多読なのか?
これは、「中学校1年~3年のテキストをマスターする」とは大きく異なります。「中学校1年~3年のテキストをマスターする」は、基本中の基本になる土台作りのために全てを吸収していく、と言う意味合いが強く、文型や語彙・表現力を身につけていく、そのために「しっかりじっくり身につけていく」と言う位置付けです。
それに対して、「学習者向け初心者用Reading教材を多読する」は、覚えた表現、文型を色々な状況で、体験し、語感を身につけ、定着させていく、と言うことが一番の目的になります。少し分かりにくいかもしれないので、簡単な例で説明するとこんな感じです。
“What’s your name?”
これを聞いて分からない人、いないですよね?
まぁ、実際にこの、“What’s your name?”って表現を使うこと滅多に無いとは思うんですが、どんなに英語が苦手でも、嫌いでも、恐らくの子の表現は聞いたことあるし、何も考えなくても意味がわかると思います。
なぜですか?
理由はシンプルです。中学校(あるいは小学校)で初めて英語を勉強してから今に至るまでの期間で、この“What’s your name?”という表現を、何回も何回も見聞きしたからです。
“What’s your name?” のwhatが疑問詞で、isが動詞で、nameが名詞、そのnameをyourという代名詞所有格で限定している、なんて考えるまでもなく、聞いた瞬間に、「あなたの名前は何ですか?」という意味が頭に入ってきます。また、whatもisもyourもnameも、これまでに何回も何回も、別の使われ方で出会ってきているので、「思い出そう」と言う努力をするまでもなく、聞いた瞬間に意味が頭に浮かんできます。
これは、全て「その単語、文型、表現、に出会った回数」の問題です。いろいろな状況で、いろいろな場面で、いろいろな表現と組み合わせて、何回も何回も、その表現、文型、単語に出会っていけば、言葉の本質を感覚的につかむことができます。
「中学1年から3年の教科書」や、「ラジオ講座」などで、覚えた(学んだ)表現などは、勉強しっぱなしだと、すぐに忘れてしまいます。一夜漬けのテスト勉強と同じです。どれだけ無理やり詰め込んでも、すぐに忘れてしまいます。覚えた事を定着させるためには、覚えた事を繰り返し思い出す必要があります。
いろいろな方法があると思いますが、「日本で日本語を使って生活している環境」であれば、「覚えた表現、文型を色々な状況で、体験し、語感を身につけ、定着させていく」と言う目的のためには、「読む」と言う方法が一番効率的になります。そして、この目的に一番大切なことは、「量」です。とにかく、「量」が一番大切なのです。“What’s your name?”の例をもう一度思い出していただければわかると思います。
そのためには、「難しい内容をゆっくり時間をかけて解読する」と言う方法は全く効果がありません。「易しい内容の文章を、早く大量に、英語のままインプットしていく」と言う読み方が必要になります。
「難しい内容をゆっくり時間をかけて解読する」と言う読み方をしてしまうと時間が掛かってしまいます。高校の英語の授業を思い出して貰えばわかると思いますが、1時間に1-2ページしか進みません。これでは、「量」はこなせません。
また、「難しい内容をゆっくり時間をかけて解読する」と言う読み方をしてしまうと、日本語で考えてしまいます。難しいので、日本語で意味をとらえようとします。そうすると英語で読んだ内容を頭の中で、「日本語で理解」し、その結果、「日本語で記憶」されてしまいます。
一生懸命勉強して、日本語で覚えてしまっては全く意味がありません。
日本人の場合、どうしても「難しい内容を一生懸命努力して勉強する」と言う習慣が身についてしまっているので、テキストを選ぶときにも、「圧倒的に難しすぎるテキスト」を選んでしまいます。
ここでの多読の方法は、「学習者向け初心者用Reading教材を多読する」です。とにかく、簡単なものを選んでください。「簡単すぎて、役に立っているのかどうか分からない」と言うくらいでちょうど良いレベルです。基本的に知らない単語が1ページに2-3語以下のレベルということを目安にしてください。
この多読の方法を簡単にまとめます。
- 難しいものは選ばない
- 知らない単語は1ページに2-3単語まで
- 日本語に訳さない
- 細かいことは気にしない
- 選んだ本がつまらなかったら無理せず他の本に移る大体わかれば大丈夫
とにかく、気楽な気持ちで続けてみてください。とにかく、「量」を追い求めて「量」を最優先してください。
半年も続けていると、「英語を英語のまま理解できる」になります。これが出来るようになれば、もうこっちのものです。「読解練習」をすればするほど、インプットが加速します。徐々にリニスニング力が強化され、話せる力も伸びてくるでしょう。
「多読」の練習方法
① 選び方のポイント
では「何を読めばよいのか」と言う事ですが、最初の数カ月は何でも構いません。好きな物を読んでください。しつこいようですが、「基本を復習」したことを前提に説明します。必要に応じて英英辞典を使い、学習者用のReadersであれば、和訳することなく(頭の中でも)英文が読めるはずですので、ペーパーバックに進んでください。読む事が苦にならないジャンルを選んでください。面白くないと思うものを読んでいても続きません。あくまでも英語の勉強なのでジャンルは選びません。(少なくとも最初の数カ月は)以下、選び方のポイントです。
- 興味ある分野を選ぶ
- 知識のある分野を選ぶ
- 辞書を使って意味を調べない
- 無作為に開いてみて、知らない単語の数が1ページに5語以下
- 最初のうちは、薄めの本を選ぶ
以下、簡単位説明します。
- 興味ある分野を選ぶ
-
興味のない分野は読んでいて面白くないと思います。1日6時間の学習時間のうち、毎日3時間程度Readingに費やすので、楽しく感じられないと続きません。
- 知識のある分野を選ぶ
-
基本的に多読の一番の目的は、「語彙力強化」です。ただし、中級者の場合圧倒的に語彙力不足ですので、全く知らない分野の書物だと意味が分からないと思います。「知識のある分野」であれば、知識を頼りにかなり意味を推測できるはずです。「日本語で読んだことのある作品」を選ぶのも一つの手段です。
- 辞書を使って意味を調べない
-
ここで言うReadingは、「多読・速読」の類です。速く大量に読む事で「インプットの貯金」を蓄えます。いちいち辞書を使って調べているようでは時間が掛かって仕方がありません。基本的に辞書は使わずに読み進みます。
- 無作為に開いてみて、知らない単語の数が1ページに5語以下
-
一般的に「知らない単語の数が1ページに5語以下」であれば、辞書を引いて意味を調べなくても読み進められます。そこまで細部にこだわって読む必要はありません。日本語で小説を読むときも、知らない単語は読み飛ばしているはずです。いまいちピンとこない方は、小中学校の国語の教科書に出てきた、夏目漱石や芥川龍之介の小説を開いてみてください。知らない単語がたくさん出ている事に驚くと思います。
- 最初のうちは、薄めの本を選ぶ
-
とは言え、中級者の人にペーパーバックはハードルが高いと思います。途中で挫折してしまうといけないので、最初のうちは薄い本を読むようにしてください。1冊2冊と続けていくと自信がついてきますので、厚めの本を選んでも大丈夫です。
② 注意点
題材を選んだら「速読・多読」を始めます。以下、何点か注意点があります。
- 辞書を使わない
-
既に説明した通りです。辞書を使わずにどんどん読み進んで下さい。
- 速度を測る
-
本を選んだら、まず最初に1ページの単語数を確認しましょう。1行に16単語あるのであれば、6行で約100単語です。1ページに30行あるとすると1ページあたりに500単語ですね。目安は1分100単語です。最初のうちは1分100単語を目標にしてみてましょう。1ページ500単語の本であれば、1時間に12ページ読めるはずです。慣れてきたら、1時間に20-30ページくらい読めるようにしましょう。アナウンサーがニュースを読むときに話す速度が1分間に120-150単語程度と言う話を聞いたことがあります。つまり1分100単語のペースで読めない限りは、同じ内容の英文を聞いても理解できません。
- 同じ作家の作品をいくつか読む
-
作家にはそれぞれ文章の癖があります。1冊読み終えるころには、その作家の癖にある程度慣れてきているので、読みやすいと思います。何冊か同じ作家の作品を読んでみてください。
③ 多読・速読の効果
「辞書を使わないで読む」と言う話をすると、「それでは語彙力増えないんじゃないですか?」と質問されることがあります。
増えます!
主な理由は以下になります。
- 1. 自然と増える
-
非常に無責任に聞こえるかもしれませんが、読んでいるうちに自然と増えます。知らない単語に出会った時、文脈からその意味を推測します。最初にその単語に出会った時には意味が分からないかもしれませんが、同じ単語に2回目3回目に出会った時にはある程度意味が分かるものです。また、違う文脈で出会っているので、その単語に対する理解度が高くなります。語彙の覚え方としては、非常に自然なプロセスであり、無理やり詰め込んでいる訳ではないので定着度も高くなります。
この例を見てみて下さい。
●●●は非常に困る。生活必需品が毎月毎月上がってきている。賃金上昇が●●●に追いつかないので、実質的には収入減だ。●●●の影響で買い控えが進み、企業の業績も悪化している。
●●●=物価高
少しイメージ湧きましたか?
自然と意味を推測するので知らない単語を覚えていきます。
- 2. PassiveからActiveへ
-
Passive Vocabularyとは、「見覚えのある単語」と言う意味です。しばらく考えてみてなんとか思い出せるようなレベルの単語です。それにたいしてActive Vocabularyとは「自分の言葉として使いこなせる単語」です。当然ながら、どんな人でもPassive Vocabularyの数の方が、Active Vocabularyより多くなります。ペーパーテストならPassive Vocabularyで対応できるのですが、コミュニケーションの実践の場で必要になるのはActive Vocabularyの方です。
多読・速読を続けていくと、これまでPassive Vocabularyだった単語がActive Vocabularyに昇華します。これはシンプルな理屈です。単純にその単語に出会う回数が増えるからです。
簡単な例で説明します。
“What’s your name?”
実際にこの表現をどんな場合で使うかは別として、この表現をしらない日本人はほぼゼロだと思います。英語が苦手な初心者でも、聞いた瞬間に意味がわかると思います。
何故ですか?
単純にこの“What’s your name?”という表現を聞いた回数が多いからです。更に一つ一つの単語、what, is, your, nameについても、そして疑問詞を伴うBe動詞の疑問文という文型も含めて、出会った回数が多いのです。
なので、この“What’s your name?”という表現を聞いた瞬間に意味がわかります。文法的に解読する必要ありません。この表現は、完全にActive Vocabularyのレベルになります。
なので、どんなに難しい語彙・表現でも、その単語に「出会った回数」が多くなれば、Active Vocabularyに昇華します。多読・速読を続けていくとPassive Vocabularyが、Active Vocabularyに変化し、昇華します。
- 3. 英英辞典
-
多読・速読の場合は、基本的に辞書を使って意味を調べません。しかし、何回も出てきて意味が分からずに、「気になって仕方ない」という状態であれば、辞書を使って調べても構いません。その際、必ず英英辞典を使ってください。英英辞典を使うと、一般的に基本3000単語程度でその意味を説明します。この基本3000単語にも繰り返し出会うので1-2年英英辞典を使い続けると基本3000単語も自分の言葉として使えるようになります。
多読・速読は非常に大切な学習方法です。特に「中級者から上級者にステップアップ」する上で一番最初に取り組むべき事項になります。まずペーパーバック100冊を突破しましょう。その後、分野を拡大していきます。
基本的にこの方法で多読を進めていけば良いのですが、もう一歩踏み出したい方は、「精読」も併用してください。
精読
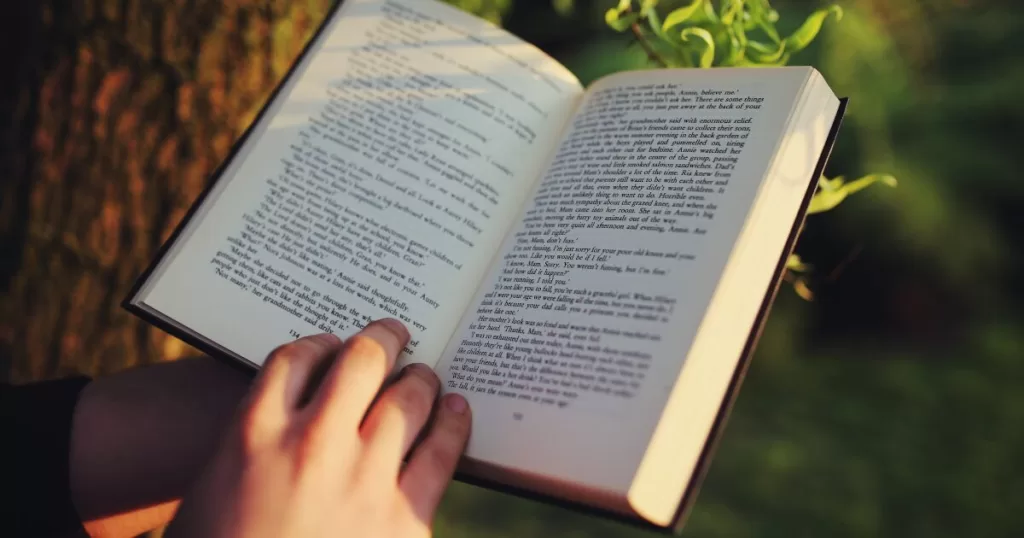
精読は、「多読・速読」とは異なり、「正確に読み取る」作業になります。イメージしやすいのは高校の英語の授業や大学入試ですね。まぁ、そのまんまです。大学入試の受験勉強をすると思ってもらえれば大丈夫です。
特に説明の必要ないかもしれませんが、一つ例を出します。
On my way home, I saw a woman that I met at the party my boss held a few weeks ago, which I should not have gone to in the first place.
この場合であれば、
主語:I 動詞:saw 目的語:a woman
このS+V+Oがこの文の核になります。 これを見た瞬間、「SVOか…」と拒否反応を示す人が出てくるかもしれませんが、避けては通れません。
関係詞が修飾 関係代名詞:a woman that ~ 関係代名詞:the party (which) my boss held 関係代名詞:which I should ~
副詞句が修飾 副詞句:on my way home
その他に、代名詞などがあれば、それが何を言い換えているのか、など、文の構造を正確に理解する練習です。
和訳する必要はありませんが、文の構造を理解するのが目的なので、最低限、S,V, O, C, OO, OCなど記入し、修飾語句がどの言葉を修飾しているのか分かるように記入していきましょう。難しい文章もあるかもしれませんが、隅から隅まで100%理解できるまで、頭を絞り考え抜きましょう。考えるプロセスが大切なのであきらめずにひたすら考え抜きます。
ただし、「多読・速読」と異なり、精読に関しては誰か英語力の高い人にチェックしてもらった方が良いでしょう。理想的には英語の先生とかに見て貰えれば良いのですが、環境的に難しい場合は、詳しい解説付きの読解練習問題集のような物で勉強すると良いでしょう。
もし、大学入試レベルの読解問題集が難し過ぎる場合は、高校入試長文問題集から始めてください。その場合でも、最終的には大学入試(難関校レベル)の長文読解問題集を使用してください。
大学入試レベルになると語彙レベルも高くなるので語彙力も付きます。語彙もしっかりと増やしていってください。この場合の語彙レベルはPassive Vocabularyで構いません。大学入試で語彙を増やしておくと、今後練習するニュースや雑誌記事、本格的な文学作品を読む時非常に役に立ちます。
この精読で一番身につくのは文法力です。文法力強化が目的です。「中級レベル」の特徴として、「なんとなく大雑把に理解」してしまう傾向があります。それはそれで良いのですが、上級レベルにステップアップするためには、相手の言う事を正確に理解する力を伸ばす必要があります。これが出来ないと、正確なコミュニケーションは成り立ちません。読んで理解できない事は、聞いて理解できませんので、精読をする事で「正確に理解する」力を伸ばしていきます。
速読・多読の場合は、「辞書を使わないで読み進む」と説明しましたが、精読の場合は、知らない単語、あやふやな単語は全て辞書で調べてください。辞書を使う場合は、「単に意味を調べる」と言う使い方ではなく、その単語の項目を隅から隅まで読んでください。必ず、以下の点をチェックしましょう。
- 品詞
- 意味
- 例文/用例
- 派生語
- 類義語
例えば、attorneyと言う単語の意味を調べるのであれば、少なくともこのくらいは辞書に出ていると思います。
attorney noun
/əˈtɜːni/
/əˈtɜːrni/
- (especially US English) a lawyer, especially one who can act for somebody in court
- The prosecuting attorney began with a short opening statement.
- More About
lawyers
- Lawyer is a general term for a person who is qualified to advise people about the law, to prepare legal documents for them and/ or to represent them in a court of law.
- In England and Wales, a lawyer who is qualified to speak in the higher courts of law is called a barrister. In Scotland a barrister is called an advocate.
- In North American Englishattorney is a more formal word used for a lawyer and is used especially in job titles:
- the District Attorney
- Counsel is the formal legal word used for a lawyer who is representing someone in court:
- counsel for the prosecution
- Solicitor is the British English term for a lawyer who gives legal advice and prepares documents, for example when you are buying a house, and sometimes has the right to speak in a court of law.
- In North American Englishsolicitor is only used in the titles of some lawyers who work for the government:
- the Solicitor General
- A notary is a person, often but not necessarily a lawyer, who has official authority to be a witness when somebody signs a document and to make the document legally acceptable.
SEE ALSO district attorney
Extra Examples
- Acting on the advice of his attorney, he remained silent.
- Consult an attorney whenever you make a major decision affecting your estate.
- Her attorney filed a motion for an injunction.
- Attorneys argued that prosecutors never proved who sent the email.
- He fired his court-appointed attorney and began representing himself.
- Army attorneys argued for a general discharge.
- He hired a high-profile defense attorney to represent him.
- He is a practicing family law attorney with years of experience.
- Your attorney may advise you to accept a cash settlement.
- an attorney specializing in entertainment law
- He had a meeting with a leading Washington criminal defence attorney.
- TOPICS JobsC1, Law and justiceC1
Oxford Collocations Dictionary
adjective
- defense prosecuting district…
- verb + attorney
- hire retain appoint…
- attorney + verb
- represent somebody practice something specialize in something…
- See full entry
- a person who is given the power to act for another person in business or legal matters
- She was made her father’s attorney when he became ill.
- SEE ALSO power of attorney
TOPICS BusinessC1- (South African English) a solicitor (= a lawyer who prepares legal documents and advises on legal matters)
- Word Origin
See attorney in the Oxford Advanced American Dictionary
Check pronunciation: attorney
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
自分なりに単語帳を作っていくと良いでしょう。品詞の区別が難しい様でしたら、文法書で確認してください。文法の勉強の仕方はこの後説明しますが、品詞と文型は必ず最初に把握しておく必要があります。あまりピンと来なくても、派生語を確認する癖をつけていくと数ヶ月程度で品詞の感覚もついてくると思います。
また、面倒くさがらずに例文にも全て目を通してください。できれば例文も単語帳に書き写し音読すると良いでしょう。英英辞典の場合、単語の定義で意味が取りづらくても例文をいくつか確認しているうちに、意味がつかめてくる場合があります。単語にはそれぞれ相性の良い語句がありますので、例文を読むとその単語と良く一緒に使われるタイプの語句を把握することができます。
「単語の意味を調べる」と言う作業の中で、この一連の流れを実行するかしないかで、数ヶ月の語彙力、英語力に大きな違いが出てきます。必ず、精読を始める初日から実行しましょう。
仕上げ
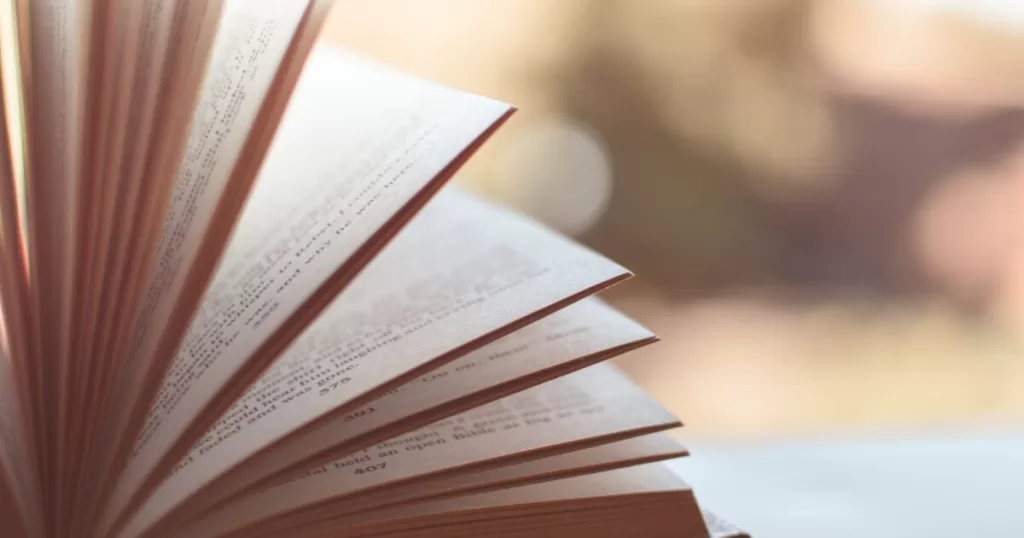
ここまで来ると、とにかく「学習量」の問題になります。ひたすら「量」を追い求めましょう。
そして徹底的に語彙力強化に努めてください。
単語帳を増やすこと、曖昧に感じた文法事項は放置せずに勉強し直す事など、これまで説明した通りです。
「速読」と「多読」に関しては以下を参考にしてください。個人差があると思いますので、必ずしもこれにこだわる必要はありません。ただし、自分の好きな分野に留まらないようにしましょう。と言っても、常識の範囲以内で大丈夫です。
- 小説:名作、推理小説、ベストセラー小説、映画の原作など
- ノンフィクション:やはりベストセラーが良いでしょう
- ニュース・雑誌:Web SIteで大丈夫です。
「精読」に関しては、「速読」と「多読」で使った題材の一部分を「精読」すると言う方法でも大丈夫です。大学の課題図書などもお勧めです。ニュース記事はそれほど文型的に難しくはないので、どちらかというと雑誌記事の方が「精読」の題材には向いているでしょう。また、所謂「名作」と言われる文学作品もお勧めです。
「ディクテーション」もニュース、テレビドラマ、Youtube、Websiteなど、何でもトライしてみてください。特に、インタビュー系の物が実践向きです。
ここまで実践できれば、かなりのインプット量が確保できます。「読解力」を進化させ、高度な「英語コミュニケーション力」に昇華させたい場合は、「リスニングの学習方法」「文法の学習方法」「話すためのライティング」の記事も是非参考にしてください。また、レベルや目的別にまとめた学習方法の記事もありますので、気になる記事を参考にしてください。