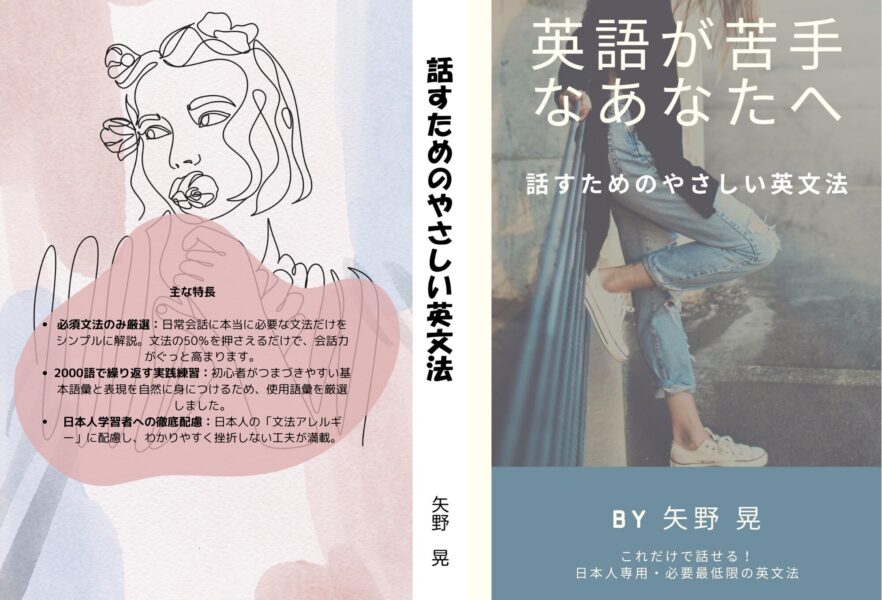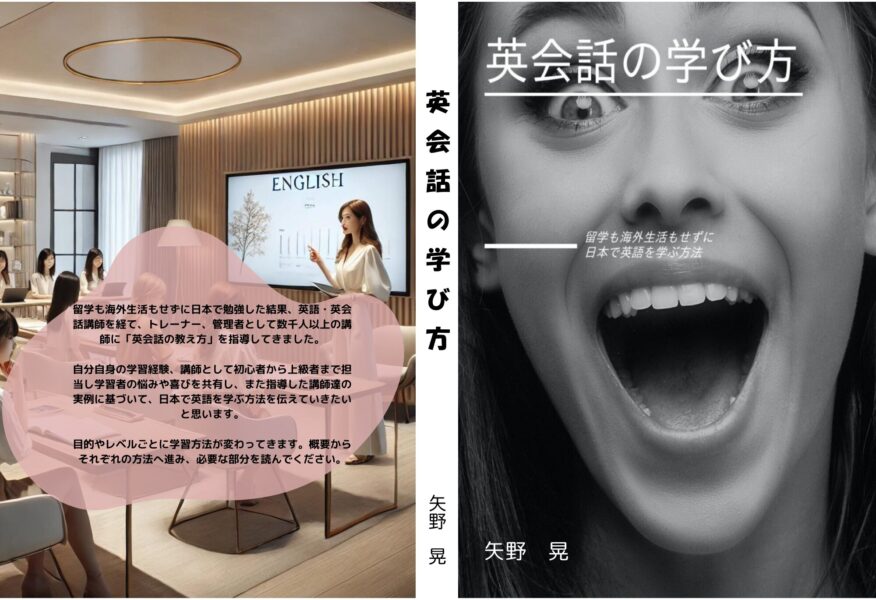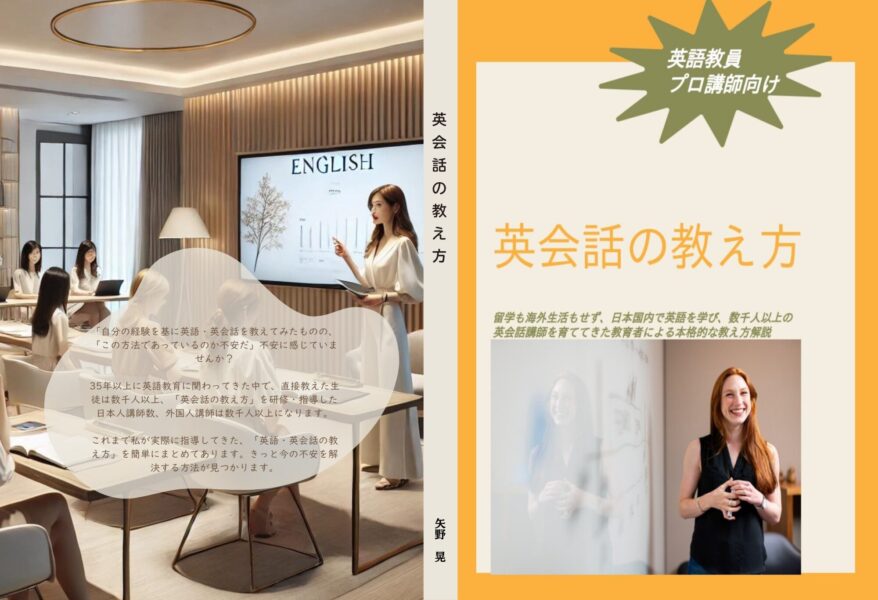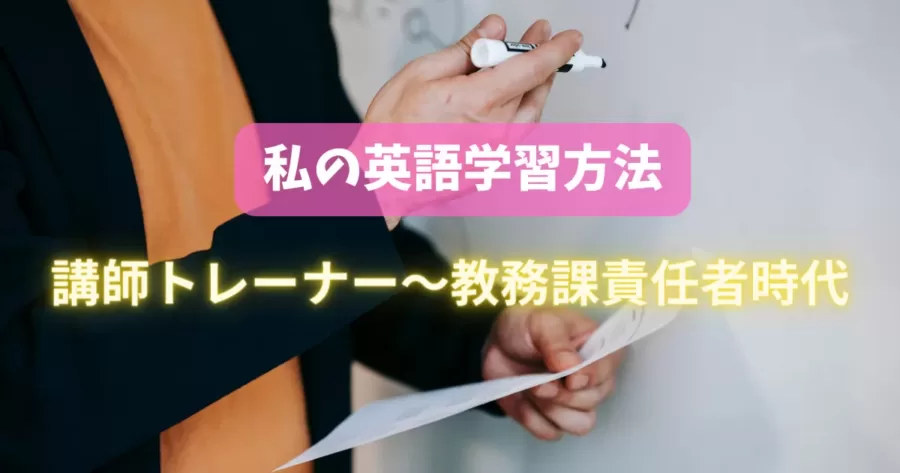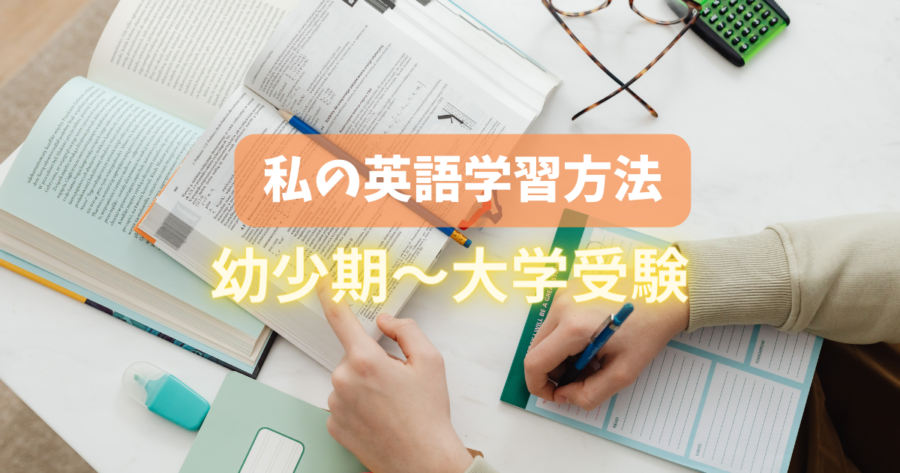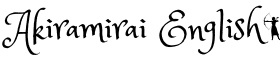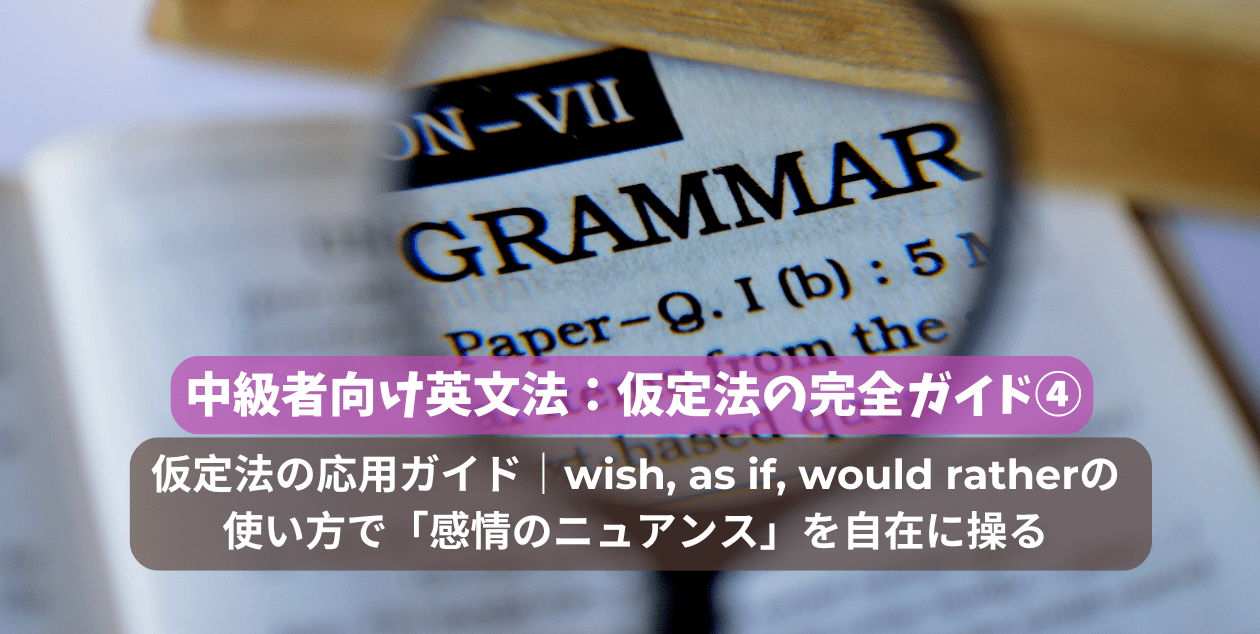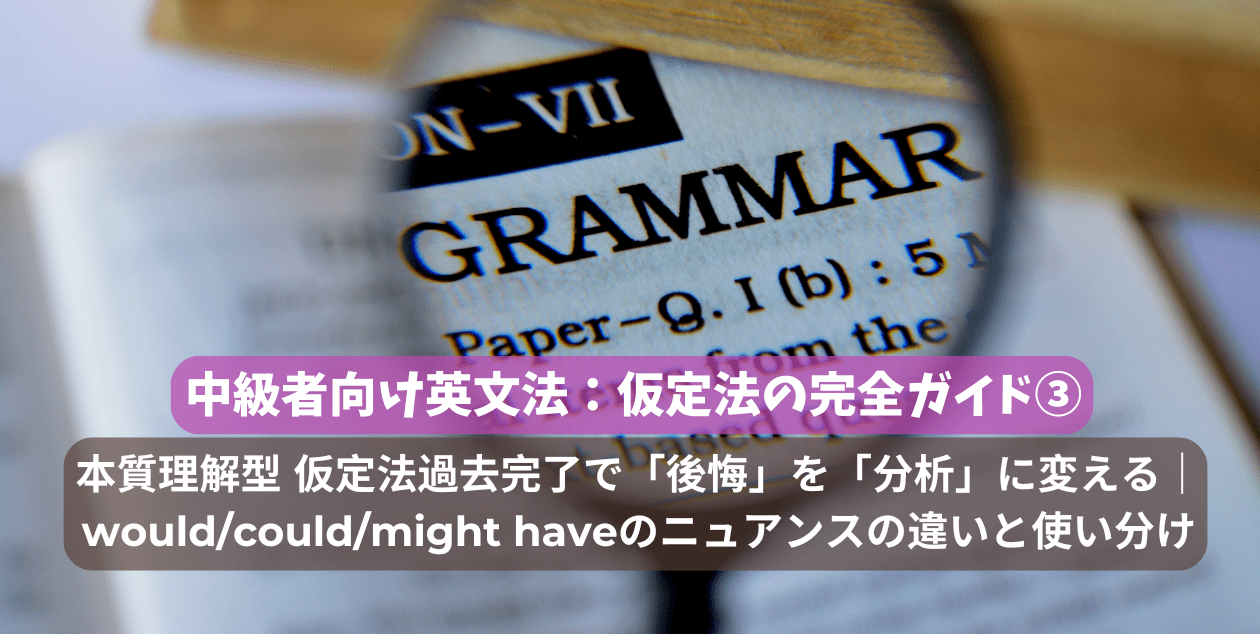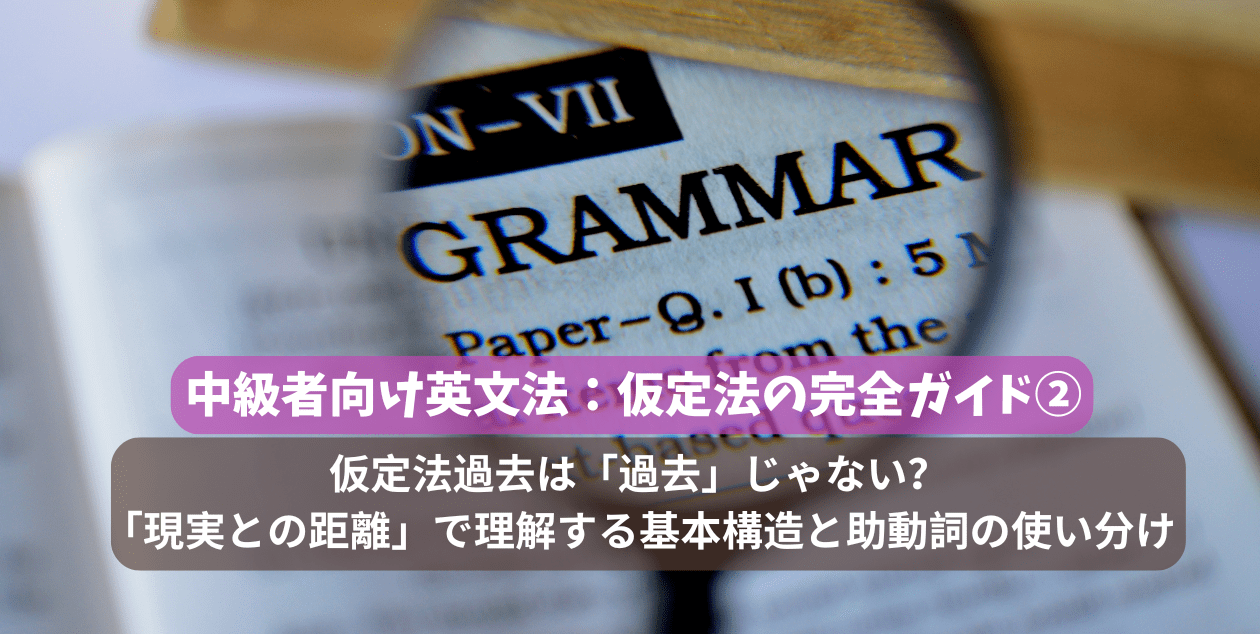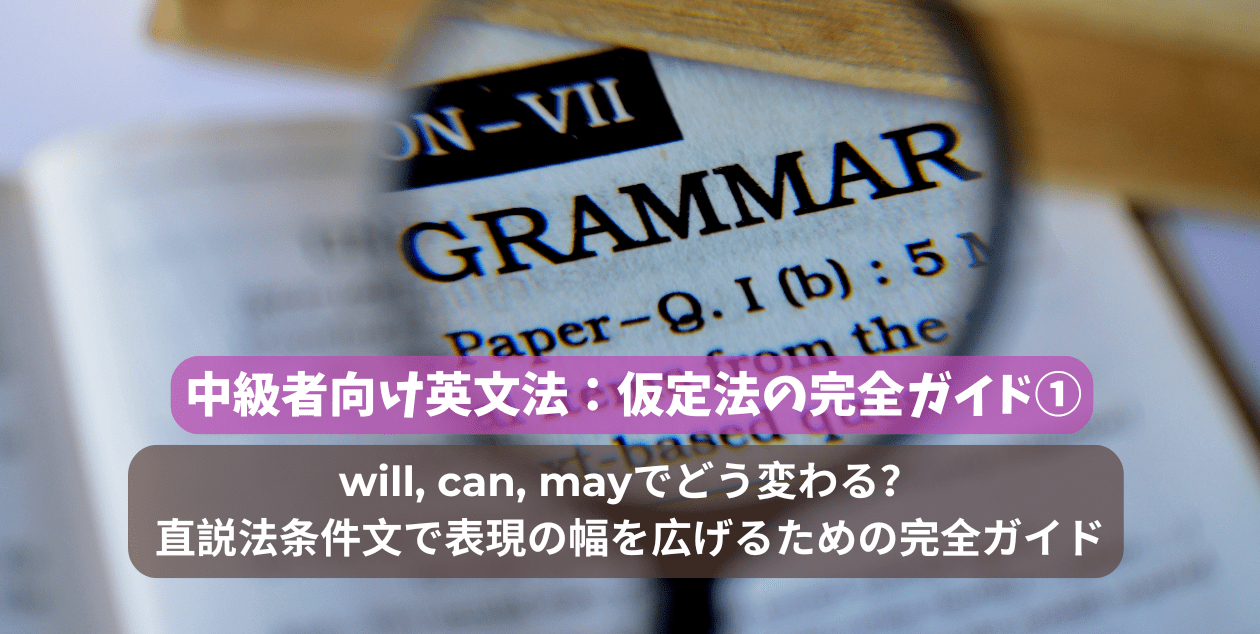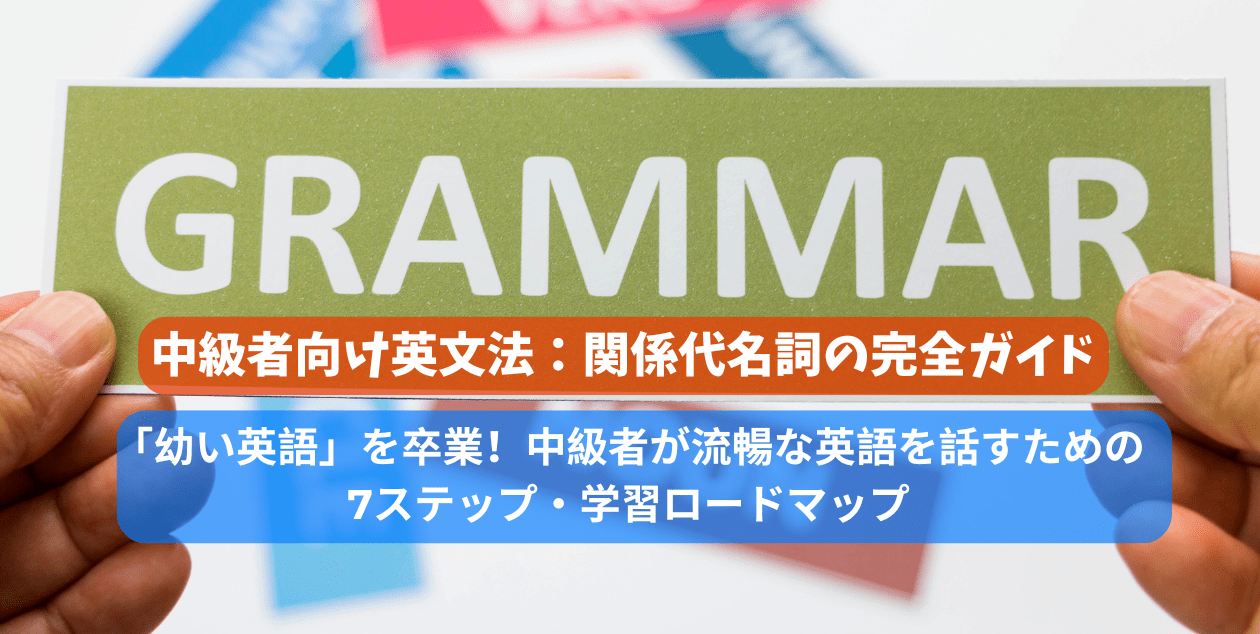- 「どうやって英語を勉強したんですか?」
- 「どうやって英語を身に付けたんですか?」
- 「どうやって英語が話せるようになったんですか?」
- 「海外に行かなくて、日本で勉強して英語が話せるようになったんですか?」
私が外国人講師の面接をしたり、研修をしたり、ミーティングをしたり、出版社など海外の取引先とのやり取りを見聞きしていた、スクールスタッフや日本人講師は、私の英語力を過大評価し、また私が留学経験も海外生活経験も無いことを知った時に聞いた質問です。
実際には英語圏で何年も勉強し、働き、生活してきた人達のような英語力があるわけではありません。何十年も同じ分野で英語を使って仕事をしていれば、仕事上の定例的なコミュニケーションに困ることはありません。バリエーションはあるものの、似たようなパターンの(コミュニケーションパターン)の繰り返しです。おそらくこれは、仕事で英語を使ってきた人であれば、感覚的に分かることだと思います。
ただし、留学や海外生活をせずに、日本国内で自分で英語を勉強し、その英語力で40年近く仕事をして、数千人以上の外国人講師に「英語・英会話の教え方を教え」、「数十名のトレーナーに講師研修の方法を教え」、「数千人以上の英語学習者に英語を直接的・間接的に教え」、「カリキュラム・シラバス・テキスト・スクールシステムを開発し」、「ビジネスとして英会話スクールビジネスを経営した」、経験を持つ人は日本国内ではあまりいないのではないか、と思い、これ前の経験をまとめ、英語を身につけたい、あるいは、教えたい、という方達に、少しでも役立てばと言う思いで、このサイトを作りました。
私が日本国内で英語を学んできた中で、大学生〜アルバイト時代という時期が一番英語力が伸びた時期だと思います。「どうやって、日本国内で英語力をつける事ができるのか?」という事に関して、明確な方法論があった訳ではありません。何となく試行錯誤しながら、継続していくうちに結果的に役に立ったのではないかと、後になって振り返ってみて理解できた事ばかりです。
「英語力向上」と言う面では、恐らくこのチャプターが一番参考になるのではないかと思います。
1. 大学生時代

「歴史は繰り返す」とは名言です。まさにその通りのことが起きました。大学生になった私は、受験勉強から解放され、高校1年生、2年生時と同様に全く勉強しなくなりました。「英語を身につけたい」と言う気持ちはあったものの、当時の一般教養過程で学ぶ英語はあまり面白いものではなく、また、ロックギタリストとしての炎が燃え上がり、音楽中心の生活に戻りました。音楽の話は、別のサイトで書くので英語の話に戻ります。
1)当時の大学の英語関係の授業について
当時の大学の主な英語関係の授業はこんな感じだったと思う。
- 読解:高校の授業とほぼ同じ、人数は20人くらい
- 音声学:発音記号ごとの発声・発音の仕方、人数は20人くらいで個別ブース
- オーラルコミュニケーション:所謂会話クラス、人数は20人くらい、レベル分け10レベルくらいだったかな
- その他:覚えていないけど、文学史とか、文法学とか
- 文学:個別の作家・作品について。大教室講義形式
- 通訳:逐次通訳の基本、20人くらい
- その他:覚えていない
この中で印象に残っているのは、2.専門過程 1)文学のクラス
もう50人とか100人とか入る大教室で、教授がマイクを持って講義していたけど、1番英語力が伸びたと思う。今でもよく覚えている、ボーシャって名前の教授だった。サリンジャーとかスタインベックとかだったかな。
とにかく1回の授業のために1週間に30-50ページくらい読んで来ないといけない、当たり前だけど作品も授業もレポートも全部英語、でも講義してくれる作品の解釈とかが、本当に「目から鱗」的な感じで、「文学作品ってこうやって読むものなんだ!」って毎回感じて、この教授の授業は真面目に受けていた。この時は、本当に「アメリカの大学に行って勉強してみたい!」って思った。
あとは、音声学かな。
ブースに入って、発音記号ごとに音の出し方を練習していくんだけど、口の開け方とか力の入れ方みたいな事を理屈で理解し実践していく、の繰り返し。やはり、大人が発音を覚えるのは、「耳から自然に」と言う訳にはいかなくて、頭で理解して、それを繰り返し練習し、体に覚えさせるのが大切ってこと。
そして、オーラルコミュニケーション。
20人くらいのクラスで、所謂英会話のクラスだけど、全然面白くなかった。先生は一生懸命教えてくれるんだけど、講義形式で表現を教わっても、会話力はついてこない。当時は理屈がわからなかったけど、後に自分が英会話を教えたり、講師に教え方の指導をするようになってから、この当時のオーラルコミュニケーションの内容を思い返すと、根本的に内容、クラスの進め方が間違っていると思う。
英語の会話力とかコミュニケーション力を伸ばすためのレッスンというと、どうしても「少人数」が前提になるけど、大学時代の経験に限っていえば、一番コミュニケーション力が伸びたのは、100人大教室の英文学の講義という結果になる。
これはずっと後になってから気づくんだけど、「英会話」って特別なものではなくて、あくまでも「英語力」の問題。「英語力」とは、「読む・書く・聞く・話す」に「文法力」とか「発音」とか「コミュニケーション力」とか「異文化理解」とか、場合によっては「教養」とか、全てが密接に関係した「総合力」と言うこと。その「総合力」が一番身についたのが、100人大教室の英文学の講義だったと言うこと。
でも、大学時代は、正直言ってあまり勉強していなかった。やはりバンド活動中心で、芝居やったりもしていたので。
2. 塾講師・英会話講師アルバイト

せっかく英米文学科に進んだのに、大学時代にあまり熱心に勉強しなかったのは、やはり音楽と芝居。1980年代当時は当たり前だった、「大学4年生~就職活動~サラリーマン」と言う選択肢はなかった。単位わずか2単位残して大学は中退し、アルバイトしながらバンド活動の道を選んだ。この辺りは、音楽関係の話なので、英語の話に戻ると、日本で英語力を高められたいくつかのポイントがある。特に大きかったのはこの3つ。
- 塾講師・英会話講師・通訳のアルバイト
- セルフスタディ
- 日本国内での交友
まずは、アルバイトしながら英語力が大幅にアップした例。
1)塾講師・英会話講師・通訳のアルバイト
大学中退した当時、最初の1年間はトラックの運転手のアルバイトをしながらバンド活動した。生活費稼ぐ目的と、当時ジャズに目覚めはじめたのでジャズの専門学校に行きたくて、その学費を稼ぎたかったから。今は閉校してしまったけど、池尻大橋にあった「メーザーハウス」と言う学校に行きたかったので、入学金と1年分の学費を貯めた。この辺りは、やはり音楽の話になってしまうので端折ると、20代は朝築地の魚市場でアルバイトして、バンド活動をしつつ、週に2-3日塾講師とか、英会話講師のアルバイトをしていた。後になって振り返ってみると、このアルバイトが英語力向上に大きく役立っていた。
① 塾講師
築地のアルバイトで生活費は稼げていたけど、なんかのきっかけで塾講師のアルバイトを始めた。恐らく時給が良かったからだろう。今で言う個別指導の走りみたいな進学塾だった。担当していたのは中学1年から高校3年までの英語。20人くらい入る教室に中学1年から高校3年までバラバラに座っている教室で、一人5分位ずつ隣に座って、順番に見ていく。
近所の子供が集まって基本的に学校で使っている教科書メインで教えていく。近所の子供が集まっているとは言え、皆学校が違うので1学年につき3-4種類の教科書がある。中学校1年生の英語の教科書なんて簡単に思えるかもしれないけど、教える時は隅から隅まで120%把握していないと教えられない。その場で質問に答えられないといけないし、説明したり例を出したりしないいけない。
最初のうちは結構焦ったりした。特に高校生の教科書になるとかなり難しいし、入試問題の過去問とかは、所謂早慶上智レベルになると、冷や汗もんだった。でも3年くらい経つと、ほとんど頭に入ってしまって、中学1年から高校3年、大学受験の英語なら、初見でもあまり驚くことは無くなっていた。
この経験で一番身についたのは「文法力」だと思う。英語に関してよく言われている、「中学英語をマスターすれば英語は話せるようになる」と言うこと。実際にNHKラジオ講座の歴代先生方も皆実践されていたことを、アルバイトをしながら学んでいた。
中学校・高校・大学受験から大学の授業を通しても、「可算不可算名詞」とか「現在完了形の使い方」と「定冠詞不定冠詞」とか、恐らくわかっていなかったのだと思う。それが、アルバイトしながら、基本的な事を教科書を何回も何回も読み、教えることによって定着させることが出来たのだと思う。
また、「読解力」の面でも、大学時代は基本的に「多読」の傾向が強く、たくさん読んだけど、ある意味「大雑把」に読んで、「なんとなく理解」していたのだと思うが、塾で教えるにあたり、「和訳」それもかなり正確に訳さないといけない。と言うのも、テストとか入試で「英文和訳」させるのは、「文の構造」を理解しているかどうかを試すためだから。「和訳」する時に、「文の構造」を見せる訳し方をしないといけない。つまり、文の構造をしっかりと説明し、訳し方を教えないといけないから。
なので、この塾講師のアルバイトをしながら、中学~高校・大学入試レベルの文法と語彙力を徹底的に身につけることが出来た。だから、後に英会話学校で教えるようになっても真剣にビジネスレベルの会話力を身につけたいと思っている人や日本人英会話講師には大学受験レベルの文法力を徹底的に見つける練習をさせていた。
② 英会話講師
塾講師を3年くらいやった時、たまたま短期の通訳のアルバイトをする機会があったので、スケジュールの都合で塾講師を辞めた。通訳の仕事は短期だったのでまた講師のバイトをしようと思ったけど、何か違う仕事をしようと思い、バイト情報誌を見ていたら英会話講師のアルバイトがあることを知った。
留学経験も海外生活の経験も無いし、当時は英語の資格というと英検くらいしかなく、あまり英会話力を示せるものは無かったので、落ちるだろうなと思いつつ、応募してみた。面接では筆記テストと英会話レッスンのデモレッスンをさせられた。塾講師で散々テスト対策の経験をしているので、筆記テストは全然難しくなく、よく覚えていないけど、多分TOEICと英検を足して2で割ったようなテストだったと思う。
英会話のデモレッスンは流石にどうしたらいいか分からなかった。「日本語は使わずに教えてください」と言われてテキストを渡されて、外国人教師相手に10分くらいのデモレッスンをした。どうしたら良いか分からないので、取り敢えずテキストに出ている表現を英語で解説して、会話をリピートして役割練習をした。後に自分が本部で働くようになり、採用面接をするようになって理解したのだけど、面接のでのデモレッスンは、「教え方をみたい訳ではなく、筆記テストでは分からない英語のコミュニケーション力と講師としての適正」を見るもの。
とにかく、面接には受かって英会話のAEONでパートタイム講師として働き始めた。今でこそ「英会話AEON」と言うと最大手って感じだけど、当時はまだTVCMもやっていなくて、それほど有名では無かった。と言うか、「英会話学校」とい業界が出来始めた頃。なので、軽くみていたのだけど、勤務開始する前に大宮のセミナーハウスで泊まり込み1週間の採用研修があった。詳細は割愛するけど、ここでテキストや教え方について学んだ。
当時のAEONは、まだクラスの大半が市販の教材、「Side by Side」とか「Interchange」とか「Coast to Coast」みたいなテキストを使っていた。当然ながら、それぞれ数レベルある訳だから、1週間に2-3日のアルバイトでも、10種類以上のテキストを使うことになる。塾講師の時と同様に、「教えるとテキストを丸暗記するぐらい覚えられる」。だから初級から中級レベルのテキストを徹底的に練習した感覚だった。また、レッスンはすべて英語で教えるので、週に3日間、毎回4時間ずっと英語を話している事になる。
日本で生活し日本語で生活している環境の中で、毎週12時間英語を話すと言うことは、内容は限られているとは言え、「話す力」や「日常的な語彙・表現力」の向上には非常に役に立った。塾講師として、中学1年~高校3年・大学受験レベルまで徹底的に身につけたとは言え、いわゆる「学校英語」と「生活に密着した日常英語」では語彙の種類が違う。日常的な語彙力向上にほ非常に役に立ったと思う。
また、「教える」と言う面では、社会人の場合、現在進行中の過程で英語を学んでいる中学生や高校生とは根本的にそのバックグランドが異なるので、個人差が非常に大きい事、動機づけの難しさを実感した。もう一つ、これは「教える」と言う話だが、当時のAEONは、「市販の教材~オリジナルテキスト」への転換期だった。
どんどんオリジナルテキストが導入されているんだけど、当時のオリジナルテキストのレベルはお世辞にも良いと言えるものでは無かった。(今は非常に良く出来たテキストを開発されています。)例文が10個あるだけみたいなテキストもあったので、毎回自分で工夫して50分のレッスンをしないといけない。ある意味、毎回教材制作していたようなものだった。これも「英語力」や「教え方」を向上させる上で非常に役立った。
そしてもう一つ大切な要因が外国人講師の存在。当時の日本は、まだまだ外国人が少なくかなり特別な存在だった。大学にも外国人講師、教授がいたが、日常的に接点が多かった訳ではない。留学も海外生活もしたことがない自分にとっては、日常的に外国人講師とコミュニケーションを取る、職場で同僚として一緒に働く、と言う経験は、語学力向上という意味以上に大きな経験だった。とは言え、当時はAEONではパートタイムの講師だったし、外国人講師との関係も休み時間に話し、時々一緒に飲みにいく程度、という関係だったので、後述する「インターナショナルパーティー」ほどは大きな影響はなかったかもしれない。
③ 通訳のアルバイト
どういうキッカケだったか覚えてないけど、1時期通訳のアルバイトをやったことがある。多分「外タレの通訳探してるんだけど、やってみない?」みたいなノリだったような気がする。たしか、本牧のアポロシアターでのR&Bグループの通訳、多分キョードー横浜かなんかで頼まれたんだと思う。
なんか、「初めて英語を使って仕事している!」みたいな感じがしてすごく嬉しかった気がして、東京駅のカフェかなんかで「英語のスケジュール表」見ながらビールを飲んで悦に入っていた気がする。多分していたと思う。実際には、そんなに大した事していた訳ではなくて、「ここで待っていてください。」とか「15分後に戻ってきてください」とか「明日は9時に集合してください」とか言っていただけ。恐らく、所謂「芸能通訳」ってこんなもんだと思いますよ!
ただし当然、完全外国人だから、(つまり日本に住んでいる外国人のように日本人とか日本人の話す英語に慣れていないという意味)、それなりにコミュニケーションが難しい時もあった。それよりも難しかったのが、「ほかの人が話す/言おうとしている」日本語を英語にする、という事だった。最初のうちは、その手加減がわからない。つまり、「その人が言っている日本語をそのまま英語に直訳するのか」あるいは、言おうとしている意図を汲み取って「コミュニケーションが成立するように意訳するのか」の加減が難しい。
この経験は、当たり前だけど、「言葉は”単語力”や”文法力”だけの問題ではない。」と言う当たり前のことに気づいた。それからリスニングの難しさ。やはり、日本に、と言うかノンネイティブと話すことに慣れていない英語圏の人の話す英語を聞き取るのは、特に初めて会った人の場合、非常に難しい。
これは、英語力だけの問題ではなくて、相手のコミュニケーション力とか、考え方とか、いろいろな要素が関係してくる。日本人同士で日本語でコミュニケーションしている時でも、「何言ってんだかわかんない人」とか「何考えているんだかわかんな人」とかいるでしょ。それと全く同じ。それは、通訳頼んでいる日本人も一緒で、「こんなこと言ったら相手怒るでしょ?」とか、「それはそのまま英語にしても意味わかんないよね?」みたいな事も英訳しないといけない。「通訳って自分には向いてないなぁ」って思ったのであった。
2)セルフスタディ
大学中退した後、アルバイトをしながらバンド活動を続けた訳だけど、(当然ながら収入源のメインは築地の魚市場だったが)、やはり塾講師や英会話講師、通訳などをしていると自分の英語力不足が気になった。今思い返すと、この英語関係のアルバイトを始めた当時はかなり英語の勉強をしていたのだと思う。その中でもやはり役に立ったのはこの3つ。
- リンガフォン教材
- 多読
- 聞く
① リンガフォン教材
この話をすると、”作り話”みたいな捉え方をする人が多かったけど本当の話です。と言うのもAEONを退職した後の勤務先の英会話スクールでは、リンガフォン社の教材を使っていたから。リンガフォンと言うのはイギリスの出版社で、設立1902年とかの歴史の古い会社。
語学教材に初めて音声教材を使った会社で、恐らく1970年代くらいまで世界中の人が「外国語学習用教材と言えばリンガフォン」と言うくらいメジャーな存在だった。日本では書店に特別なコーナーを設けていて、立派な箱に入った教材、当時はカセットテープが20本くらい入っていて値段も当時で3-4万円くらいの高額教材。
高校生くらいの頃から欲しかったけれど、とてもじゃないけど買ってもらえるような金額じゃなかった物だけど、築地でアルバイトしていて多少自分で自由になるお金があったので一念発起して買った。当時の英語関係の雑誌、ラジオ/テレビ講座のテキストには、必ず大きく広告が出ていた。そこに書いてあったのは、確かこんなこと。
- 1日30分毎日続けると、3ヶ月後には英語が聞き取れるようになる。
- 更に1日30分、もう3ヶ月続けると英語が話せるようになる。
こんな内容のコピーと、体験者の声が出ていた。
ある意味、この教材の仕組みはシンプル。ごく自然な日常会話がナチュラルスピードで録音されている。これをひたすら聞く練習から始める。
まず音から入る。外国語学習の基本中の基本です。
日本人学習者は、文字を見る事で安心します。内容理解のための第一歩です。
一度文字を見て概要を理解したので、再び音だけで捉えようとします。
知らない単語・表現は聞いても当然分からないので、確認します。
文字を見ながら、内容理解します。
内容理解したら、音声のスピードで音だけで理解できるように、スピードについていく練習をします。
理解できた事を練習することで、聞き取れるようにしていきます。
もう語学学習の王道中の王道的な練習方法。でも、最初は全然聞き取れなかった。大学で外国人講師の授業も取ったし、会話クラスもあったけど、やはり学生向けに分かりやすく話していたんだと言うことに気づいた。今と違って、当時、1980年代では、あまりナチュラルスピードで話されている英語を聞くことはあまりなかったので、このスピードについていくのは難しかった。
特に文が長くなったり、関係代名詞や関係副詞が使われた文になると頭がついていかない。テキストを見ないでリピートするのは更に難しかった。しかし、不思議な事に3ヶ月程度続けていくと、「本当に聞き取れるようになっていった」。これはいくつかのポイントがあって、(もちろん後になって英語を教えるようになってから思い返して客観的に理解した事)
- 文字として認識していた単語を音だけで認識できるようになる
- 英語を文頭からその語順で、センスグループごとに捉えられるようになる。 (浪人生時代に「同時通訳式速読法」で学んだ読み方で聞き取ること)
- 日本語に置き換えていくと間に合わないので、英語のまま理解する
そして、このリスニング練習に次いで、大きかったのがカセットテープと行う口頭練習(ドリル練習)。いわゆるオーディオリンガルメソッドですね。文字で見ると、ものすごく簡単なことだけど、テキストを見ずに音だけでナチュラルスピードですると全然出来なかった。
テキストの最初の方はこんなシンプルな練習。(Tは講師、Sは生徒。)
 講師
講師She has a book. “ Question”
 生徒
生徒Does she have a book?
 講師
講師Did Mary go to school yesterday? “Yes”
 生徒
生徒Yes, she did. She went to school yesterday.
この”生徒”の部分が、無音になっているので、そのスペースで答えないといけない。この無音部分が意外と短い。考えているうちに、(と言うか”講師”のセリフの意味を考えているうちに)、正解が流れてきてしまう。この練習をテキストを見ないで言えるようになるまで、ひたすら繰り返す。自分は負けず嫌いな性格なので、出来ないことが悔しくて、出来るまで繰り返した。
当時、アルバイトしていた塾講師で中学~高校の教科書を繰り返し教えていた時期でもあったので かなり正確な文法力と即答力がついたのだと思う。語彙的にも、大学の文学作品や塾で教えていた教科書とは異なる日常的な表現が多く 出てきたので基礎力が身についたのだと思う。また、当時使っていた教材は「米語スタンダードコース」と言うだけあって、いかにもアメリカンな発音で、テキストのイラストとかもなんとなくアメリカンな感じがして、「英語を勉強している感」が感じられた。
② 多読
この時期は非常に多く読んだ気がする。日本国内で外国人の友人が数人出来たので、彼らと映画や音楽、小説の話をする機会が増えてきていた。話題に出てきた小説や映画の原作、歌詞などを読み、よく話をした。話した内容は後で書くとして、読み方については、この3つ。
- とにかくストーリーを読む読み方
- 語彙力や語感を見につける読み方
- 正確に読み取る力を身につける読み方
- ① とにかくストーリーを読む読み方
-
割合的にはこれが一番多かったと思う。ペーパーバックを1ヶ月に5-6冊くらいのペースだったかな。よく読んでいたのが、スティーブン・キング。単にその頃仲がよかったイギリス人がよく読んでいたのと、映画化された作品が多かったから。知らない単語とかも全く調べずに、単にストーリーを追うだけ。ただし不思議なもので同じ作家の作品を3-4冊読んでいると結構わかるようになってくる。
当時TV化されていたBill Cosbyの本とかはすごく平易な英語で書いてあって読みやすかった。その他には、ヘミングウェイ、フィッツジェラルド、サリンジャーみたいな米文学の有名どころから、ディケンズみたいなイギリス作家、シャーロックホームズも大好きだった。
でも読み方は、細かいことは何も気にせずに、知らない単語があっても無視、ひたすらストーリーを追う!みたいな感じ。良く、「読んでるだけで語彙力増えるんですか?」と聞かれるけど、「増えます!」使用頻度が高い単語・表現は繰り返し出てくるので、違う状況で5-6回その単語に出会えば何となく意味は推測できる。10回以上出会えば、ほぼ間違いなく意味が頭に入ってくる。
また、単語力には、次の3つのレベルがある。
- 自分の言葉として使えるレベル
- 読んだり聞いたりすれば意味はわかるけど自分では使えない
- なんとなく見覚えがある
辞書で意味を調べなくても、この②読んだり聞いたりすれば意味はわかるけど自分では使えない、③なんとなく見覚えがある、と言う次元の単語に繰り返し出会うことによって、①自分の言葉として使えるレベル、まで進化していく。そして、こうやって覚えて、というか身について行った単語は、そう簡単に忘れるものじゃない。テスト前に無理やり詰め込んだ単語はすぐ忘れるけど。
とにかく、大量に読む。
英語は、と言うか外国語は、インプットが基本。効率的にインプットするには、多読が一番!
- ② 語彙力や語感を身につける読み方
-
とにかく語彙力不足を実感していたので、なんとか語彙力を強化しようと思った読み方。選んだのは文学作品とかではなくて、学習用の読み物。書店の語学コーナーなどに置いてある、「表現解説付き」とか「対訳付き」の本。
海外生活をしたことがなかったので、日常的な語彙力不足を痛感していた。学校の教科書や文学作品に出てくるような表現ではなく、身の回りの物を表現する単語。例えば、「洗濯する時の一連の動作」とか「車を運転する時の一連の動作」とか。だから出来るだけ、こう言う表現が出ていそうな本を探し、と言うか、立ち読みしながら選び、繰返し読んだ。
多分本当につまらない内容の本だったんだと思う。確か「ドビーの青春」みたいな本があって、知らない単語はほとんどない感じだったけど、良く意味が掴めなかった。多分まだまだ「rich=金持ち」みたいなレベルの語感しか持っていなかったので、基本単語の意味を表面的にしか理解しなかったんだと思う。
「表現解説付き」とか「対訳付き」だったので、意味がわからない時は、日本語を見ればわかるので、意味がわかったらひたすら音読の繰り返し!以前、「英英辞典」を使う事の意義を書いたけど、ここはある意味正反対。日本語で見れば一目瞭然なので非常に便利。ただし、日本語を見て意味を理解して、そこで安心して終わってしまったら、ほぼ意味がない。と言うのも、記憶されるのは日本語訳だから。英語が頭に残らない。インプットされない。
この辺りの理屈は後付けです。当時、意識していた訳ではない。後に講師経験を積んだ上で、振り返ってみて理解できたことなので、
この場合のポイントは、
STEP読んでも意味が良くわからないある意味、よく分からない題材を選びます。とにかく日常的な表現。
STEP意味を理解する「表現解説付き」とか「対訳付き」を使って、日本語で理解してOK。
STEP繰り返し音読繰り返し音読して、英語でインプットします。
ほぼ丸暗記するくらいの勢いで音読していた。やっぱり音読は基本です。
- ③ 正確に読み取る力を身につける読み方
-
これは所謂学校教育の英文読解と一緒。「ノートに写して和訳!」みたいな事はしなかったけど、細部まで曖昧にせず、しっかりと読むと言う読み方。「しっかりと読む」と言う表現が既に曖昧すぎるけど、「多読」の場合は、大雑把にストーリーを追う読み方をするので、「多読」の対局にある「精読」と言う読み方。
具体的には、
1. 文の構造を把握する:所謂SVCとかSVOみたいな事です。- 主語と動詞を把握する
- 代名詞が何を指しているのかを把握する
- 修飾語句の修飾関係を把握する
- 時制を正確に把握する
- 仮定法、関係詞、分詞、不定詞、比較などがあれば、用法を正確に把握する
2. 文章の構造を把握する- 段落の組み方
- 話の展開の仕方
- 事実を述べているのか、意見なのか、例を出しているのか、など
この読み方をしていた時に気に入ってたテキストがこれ。
The Expanding Universe of English (東京大学出版会)
「トビーの青春」は見つからなかったけど、この本は今でも販売しているみたい!
(その後色々と検索してみた結果、「トビーの青春」見つかりました。「トビーの青春」 ではなくて、「ドビーの青春」だったみたい。と言うことで実際には、”The Many Loves of Dobie Gillis”と言う作品で映画化、テレビドラマ化されていたみたい。)
これまでに多くの日本人講師、スクールスタッフで英語力の高い社員、と働いてきたけど、非常に多かったタイプとして、聞く話すを中心とする英語コミュニケーションは得意だけど読解力が低い。多くの場合、「意味はわかるんだけど、どう日本語にしたら良いかわからない」と言っていた。でも実際に一緒に英文を読んでみると、文の構造が捉えられてなかったり、代名詞が何を指しているのかわかっていなかったり、英文の意味を取り違えていることが非常に多かった。読む書く聞く話すの4技能をバランス良く伸ばしていく事は非常に難しいけど、全体的に読む書くが苦手な子が多かった気がする。
その影響で、聞く話すのコミュニケーションも実際にはかなり誤解したまま進んでいた事があった。この「正確に読む取る力を身につける読み方」に関しては、当時かなり意図的に練習していたんだと思う。と言うのも、メインは「多読」の読み方で単にストーリーを追っていただけなので、「これで本当に英語力がついているんだろうか?」と言うような不安感を感じていたんだと思う。なので、意図的に、語彙も文章も難しめのテキストで、細部まで正確に読む練習をしようと思っていたはずだ。
③ 聞く
リンガフォン教材をひたすら練習して、無事に「米語スタンダードコース」を終了した後、聞く練習として活用したのが、この3つ。
- FEN(AFN)
- テレビドラマ
- 洋楽
- ① FEN(AFN)
-
当時、早朝から築地の魚市場で働いていたけど、仕事の前半は市場場内で「競落ちた魚を店まで運び仕分けする」、そして後半は「仕分けした魚をトラックで飲食店へ配達する」と言うルーティン。後半のトラック配達時には、いつもFEN(Far East Network)、今で言うAFN(American Forces Network)を聴いていた。
FENでは最新のヒットミュージックが1日中掛かっていたので、基本的には音楽を聴いていたんだけど、毎時0分から3分くらい ニュースが流れる。それからDJが曲間に話しているので、トラックを運転しながら毎日聴いていた。リンガフォン教材でリスニング力が飛躍的に伸びたとは言え、当時の語彙力と理解力ではネイティブ向けの番組は到底理解できない。
ニュースはほとんど分からず、スポーツもほとんど分からず、DJの話す言葉も所々しか分からない。ただし、多読や精読を続けて、また塾講師や英会話講師をしながら基礎力が付いてくると少しずつ付いていけるようになっていった。
シャドーイングしようと試みた事あるけど、トラック運転しながらでは、とてもじゃないけど無理だった。それよりも、ラジオから聞こえてくるのは、紛れもなくアメリカそのもの。「塀の向こうのアメリカ」じゃないけど、「ラジオの先のアメリカ」が、とにかく光り輝いていて眩しかった。「いつかそこに行ってみたい。そして大成功したい。」と改めて感じていた。
音楽中心の生活しながら、英語の勉強を続けられたのは、やはりこの純粋は「憧れ」だったんだと思う。
- ② テレビドラマ
-
これまた当時の状況は今と違って、毎日テレビで海外ドラマを放映していた。当然吹き替えだったけど、この頃ビデオデッキが普及し、主音声と副音声が聞けるようになったので副音声で英語原盤の音声が聞けた。
当時良く観ていたのが、Family Ties, Cosby Show, Sherlock Holmes. その他にもたくさんあったはずだけど、覚えてない。
他のTVドラマは、所謂「ストーリーを追いながら楽しんで見る」と言う見方。「多読」のTVドラマヴァージョンという感じ。映像を見ながら、所々に聞き取れる表現を頼りにストーリーを追って行く。とりあえず楽しめる。役者の実際のセリフが聞ける。英語で見てる感を味わえる。が、しかし、あまり英語力向上には役立たない。
と言うことで、英語力向上に大きく役立ったのが、この3つのテレビドラマ。Family Ties, Cosby Show, Sherlock Holmes. (記憶が間違っていなければ)難易度的には、Cosby Show → Family Ties → Sherlock Holmes の順かな? とにかくSherlock Holmesは難しかった!
やり方は極めてシンプル。
STEP30分番組を録画しておく。テレビドラマの良いところは、「30分番組が多い」と言うこと。やはり2-3時間の映画はリスニングよう教材としては使いにくい。しかもテレビドラマの場合、「30分番組が多い」の中にコマーシャルのブレークが入るので、10-15分区切りだし、シーンの切り替えも見えやすいので、2-3分のセクション単位で区切りやすい。学習用としては非常に使いやすい。
STEPノートとペンを持つアナログだけど、やっぱり手で紙に書き留めないと効果は半減する。ただし、PCやタブレットで入力しても全く問題ない。
STEP1センテンス/1フレーズ毎にビデオを止めて、1字1句かき取っていく根気強く、根気強く、分かるまで、聞き取れるまで繰り返し聞いて書き落としていく。ここで手を抜いたら効果は半減する。
Sherlock Holmesなんて、「もう永遠に終わらないわ!」って感じだった。最初はほとんど聞き取れなかったものが、何回も繰り返し聴いて書き取った後にもう一度見てみると、嘘みたいに頭に入ってくる。達成感も半端なかった。
こうやって書き取ってみると
- 知らない単語は聞き取れない
- 文法的にあやふやなものは、聞き取れない
- 文系的に定着していないものは、速さに付いていけない
- 文字だけで覚えた単語は聞き取れない
- 音の連結で別の単語と誤解してしまう
この「聞き取れない理由」がはっきりと認識できるだけで、全然違う。そして大切な事は「聞き取れない理由」が分かって、何を言っているのか、とりあえず理解できた段階で、出来るだけ正確に真似してみることだった。発音、イントネーション、抑揚を、丁度歌の練習をするようにビデオと一緒にセリフを言ってみる。同じような感じで言えるようになるまで繰り返す。
これが出来るようになると、聞いているだけ、見ているだけで、一語一語はっきりと聞き取れ、自然と頭に意味が入ってくる。そして、一度この段階までしっかりと練習すると同じTVドラマの他の回も、凄くわかりやすくなる。役者の話し方の特徴を掴んでいる訳だし、そのドラマに繰り返し出てくる表現も身につけているから。
ただし、この練習方法はすごく難しい。何が難しいかと言うと、自分のレベルに丁度いい題材を見つけることが英語学習者には難しい。レベルが丁度良くても、好きでもないドラマを繰り返しみるのは苦痛だ。また、セリフが表示されなければ、正解かどうか確認できない。(現在は恐らくセリフ表示できるのだろうが、当時は全く不可だった)
ドラマだけでなく、ニュースでも時々やっていたかなぁ。まぁニュースには別の難しさがあるけど、それはもっと後の章で書くことにします。
- ③ 洋楽
-
洋楽は昔から聴いていたけど、中学生・高校生の時は意味をわからず、歌詞カード見ながら歌ってた。歌詞カード見ても意味が全然掴めなかった。表現的にも教科書に出てこないようなものがあるし、歌詞はやはり「詩」なので、所謂教科書や英会話テキストに出てくる文章とは違うものもある。
この時期は、大学で少し勉強したし、セルフスタディもそれなりに続けていたし、塾講師や英会話講師として教えながら学んでいた部分もあるので、少しずつ歌詞が理解できるようになってきていた。と言っても、曲を聴いてすぐに理解できるなんてレベルではない。歌詞カードを見ながら何回も聞いて少しずつイメージが掴めてくる感じ。
音楽は不思議なもので、歌詞カードを一生懸命英文読解のように勉強しても分からない場合でも、何回も歌っているうちに自然と意味が掴めるようになってくることがある。所謂ヒットチャートを賑わすようなラブソング的な曲、わかりやすい例だとBilly Joelの ”Just the Way You Are”のような曲、であれば、すぐに理解できるようになっていた。
それよりも当時はもう少し手の込んだ曲、やや難解な歌詞に傾倒するようになった。音楽的にも、これまでのロック一辺倒からブラックミュージックに傾向が変わってきていて、特にPrinceには完全にノックアウトされた。
当時は、Prince と David Bowie の曲をひたすら分析する日が続いた。当然ながら、曲そのものコード進行、構成、アレンジがメインだったけど、歌詞も必死に理解しようとしていたけど、歌詞カードを眺めていてわかる次元ではなかった。当時AEONで一緒に働いていた外国人講師に歌詞の意味を聞いてみたけど、あまり満足のいく答えは得られなかった。この頃少しずつ、気づいてきたんだけど、「英語の事はネイティブに聞けばなんでもわかるし、ネイティブが言うことが正しい。」 という事は事実ではないって事。
良く考えてみれば、当たり前のこと。日本語で考えてみれば良くわかる事。自分も含めて日本語のネイティブスピーカー。簡単な日本語なら何が正しいかはわかるけど、ちゃんとした挨拶文を書こうとすると悩んでしまう。まして、夏目漱石とか芥川龍之介のような有名な作家の作品の細かい部分をいきなり質問されても答えられるものではない。なので、外国人講師に聞くのは諦めて、辿り着いたのが、インタビュー記事。
今ならYoutubeとかですね。PrinceとかDavid Bowie本人が「どういう状況でどういう心境で歌詞を書いたのか」答えてくれている。Princeの場合は、こういう質問に答えたりしないので、正確には当時のバンドメンバーのWendyとかが答えていたんだけど。
一例としては、Princeの”Starfish and Coffee”と言う曲。凄くいい曲だけど、歌詞カードを見ても全然意味がわからない。きっと薬でラリっていたんだろうと(死語ですね)、思っていたんだけど、インタビューで読んでみると、当時Princeが付き合っていたスザンナの小学校時代に出会った変な子の事をそのまま表現したらい。素直な気持ちで歌詞を読んで見れば、「あ、そう言うことなんだ」って納得できるけど、背景を知らない限り全く理解できない。
David Bowieとかもそうだけど、歌詞ってそう言うもの。とにかく、歌詞でも小説でも、単語の意味を調べて文法的に理解して、という基本的な事から、一歩進んで(自分の中では確実に一歩進んだ)、作者、著者がどういう意図で書いたのか、想像しながら、解釈していく、と言うことに真剣に取り組んでいた。
どちらかと言うと、これは音楽的な話でしたね。
3)日本国内での交友
留学も海外生活もせずに英語力を伸ばしてきた中で、大学、アルバイト、多読やセルフスタディを続けていて圧倒的に足らなかったのが、実践の場。観光客や日本で仕事をしている外国人、日本に住んでいる外国人がそこら中に存在する今(2023年)と違い、当時(1980年代~1990年代)は、まだまだ外国人の存在が珍しい時代。
AEONで英会話講師としてアルバイトしてたとは言え、所詮週2-3日のパートタイムなので同僚の外国人講師とは、職場で挨拶して少し雑談して時々飲みにいく程度。それほど深いコミュニケーションを取っていた訳ではない。まぁ、セルフスタディの延長線上くらい。
この中で特に「コミュニケーション力」が大きく成長した機会がこの3つ。
- インターナショナルパーティー
- 音楽活動
- モデル事務所
① インターナショナルパーティー
今でもまだ存在するのだろうか? 多分1980年代後半から1990年代前半だったと思う。まだ、早朝築地でアルバイトして、夜AEONでもアルバイトしながら、バンド活動をしていた時期。インターネットなど存在しなかった当時は、「英語を使った仕事を見つける」とか、何かしら英語に関係した情報を得るために一番活用していたのは、Japan TimesのClassified Ads. 要するに、英字新聞の3行広告。(実際には3行ではない)
AEONの英会話講師とか芸能通訳とかのアルバイトもここで見つけたんけど、当時毎週出ていた広告に、”International Party”があった。所謂「飲み会」「合コン」の類だけど、”International Party”って言うだけあって、「外国人参加者が多く、英語が共通語の飲み会」。さらにわかりやすく言うと、「外国人の男が日本人の女の子をナンパする集まり」って事。
まぁ、「なんとなく面白いかも!」って思って軽い気持ちで行ってみたら、その後数年間毎週通うことになった。1990年前後のバブル景気真っ只中の六本木。飯倉片町交差点の付近のビルの2階か3階のある店、というか部屋、で夜な夜な飲み会が繰り広げられていた。平日は、英会話レッスンとかフランス語レッスンとかがメインだったけど、金曜と土曜の夜は毎週パーティ。「外国人の男が日本人の女の子をナンパする集まり」なので、自分の場合本来であれば邪魔者的存在のはずだけど、いつの間にか中心人物になっていた。理由はいくつかあって、おそらくこんな感じ。
- 当時の日本人は英語が話せる人少なかった、特に男は。なので珍しい存在だった。
- しかも、当時の日本人男性は、「所謂サラリーマン」ばかりだったので、「魚市場バイトしながら「音楽活動している面白い奴」と言う存在だった。
- しかも当時の自分は日本人の女の子に全く相手にされていなかったので、「外国人の男が日本人の女の子をナンパする集まり」の主人公の彼らにとってバッティングする相手ではなかった。むしろ役に立つヘルパーだった。
- 主催のフランス人にとって「共感できる仲間だった」(フランス映画が好きで、フランス文学が好きで、初心者レベルだけどフランス語も話せた。)
このパーティー、と言うか、この団体/会社のオーナーだったフランス人と非常に仲良くなったので、毎週金曜日と土曜日は「六本木~新宿」のオールの日々が続いた。オーナーの友達的な存在だったので、パーティー中はヘルプをしたり、片付けをしたり、自然と外国人の友達が増えていった。
この時代は本当に楽しかったんだけど、英語学習の点で考えるとやはり「異文化理解」。全て書いていくと1冊の本が出来そうなくらいなので、端的にまとめるとこんな感じ。
- 1)コミュニケーションスタイル
-
恐らくこれが一番大きい。大学の勉強、セルフスタディ、英会話講師として働きながら学んだことなどで、「語彙・表現力」「文法力」「リスニング力」とか身についていて、所謂「日常会話」的な事は出来たんだけど、「深いコミュニケーション」は出来なかった。当然ながら、「語彙力不足」が大きな要因だったけど、一番の問題は、「考え方」「コミュニケーションスタイル」
当時の自分は、「日本文化的発想んで日本語で考えた内容を英語にして話していた」だけ。だから話し相手の欧米人に「結局何を言いたいの?」「お前の意見は?」などと、逆に聞き返されていた。これは、かなり打破するのが難しかった。要するに日本的教育、躾、とかで「空気を読む」とか「阿吽の呼吸」とか、男の場合は「余計な事は言うな」とか「理屈は言うな」的な教育を受けてきていたから。(昭和の場合です)
所謂日本的コミュニケーションは、「共通点を見つける」。「共通点を見つけたらお互いにハッピー。」それ以上の理由や説明は要らない。しかし、英語圏、欧米の文化では、「自分の意見を言ってその理由を言葉で伝えないといけない」。意見を言う前に、「相手の顔色を伺って、忖度して自分の意見を調整する」必要はない。
これが、当時の自分では物凄く難しかった。どうしても「自分の意見を相手が受け入れてくれるか」気にしてしまう。「意見や考え方が違うからと言って嫌われるわけじゃない」「怒る訳じゃない」「違いをわかる事によって、お互いにもっと良く理解できるようなる。」「もっと親しくなる。」少しずつ、そんなふうに考えられるようになった。
その中で、強烈に印象残っているのが、こんな例。ある時、いつものように金曜日の夜、と言うか、夜中、六本木から歌舞伎町へタクシー移動した。なぜかその日はボーリング場へ行った。恐らく7-8人居たと思う。仲の良かったフランス人の男は、モデル系の日本人の子と仲良くしていて、他にも「外国人の男と日本人の女の子」の組み合わせが出来ていた。
マジョリティは「外国人の男と日本人の女の子」だったんだけど、少数派に外国人の女の子がいた。必然的に自分のテリトリーになるんだけど、(詳細省略)、その中にすごく綺麗なドイツ人の子がいた。でもその子には当時一緒に住んでいるパートナーが居たので手を出さなかったんだけど、フランス人オーナーに怒られた。

だからお前は駄目なんだ!

付き合っている相手がいるとか、結婚しているとか関係ない!

どうするか決めるのは女の子だから、お前が気にする必要ない!
この発想には、心の底から驚いた。彼の考え方が、フランス人とか、欧米人の一般的な考え方かどうかを別として、自分の考え方、発想などが、「狭い日本での特殊な価値観、考え方、発想」なのかと言うことを考えさせられた。インターナショナルパーティーに毎週通っていたこの数年間で、コミュニケーション方法について大きな変化を実感した気がする。
- 2)日本に住んでいる”外国人”のカースト
-
もう一つ大きな出来事があった。毎週通っていたインターナショナルパーティーは
フランス人オーナーが主催していて、親友的な存在だったので自然とフランス人の友人が増え、パーティーに呼ばれるようになった。これは、「外国人の男が日本人の女の子をナンパする集まり」ではなく、フランス人の友人達の集まり。この集まりに行くようになって気づいたのが、「外国人」とひとまとまりにしてしまうけど、日本に住んでいる外国人にはいくつかの種類があると言うこと。これはものすごくGeneralizationしてしまうので、例外は多々あり、誤解してほしくないけど、当時の自分にとっては大きな発見だった。あくまでも1990年当時の話です。当時日本に居た外国人は大きく次の3つのカテゴリーに分けられる。
- 在留米軍人
- 英語・英会話講師
- 海外赴任で日本に来ている企業人
*もちろん、その他に外交官やスポーツ・文化系在留人もいる
インターナショナルパーティーに来て日本人の女の子をナンパしていたのは、1)在留米軍人と、2)英語・英会話講師がほとんど。詳細は割愛する。で、当時初めて出会ったのが、3)海外赴任で日本に来ている企業人。当然、会社負担で来ているので生活水準が全然違う。
初めてパーティーに行ったときは本当に驚いた。広尾の有栖川公園の近くのマンションでリビングに50-80人くらい人が入る。「余裕のありそうなフランス人、イギリス人」がメインで大音量の音楽かけてみんなで踊ってた。1フロア上にバスルームがあって、天井に窓があった。あんな大きなバスルームは見たことない。
でもあまりに騒ぎていたので、警官が注意しにきた。そうしたら、みんなで素直に大人しく飲み始めた。アメリカに憧れて英語を勉強してきたけど、「ヨーロッパって凄い!」って意味もなく感動し、「絶対に行ってみたい」、「生活してみたい」、って思うようになった。
② 音楽活動
多分このインターナショナルパーティーの流れからだったと思うけど、イギリス人の子と一緒に音学活動するようになった。一応肩書きは「女優・歌手」みたいな感じだった。「女優」と言ってもNHKのテレビ英会話講座にちょい役で出ている程度だった。音楽の話になってしまうけど、自分の場合、作曲・編曲・演奏(ギター)には自信があったけど、作詞の才能はなかった。まして自分で歌えるほどの歌唱力は微塵もなかった。当時はまだ「絶対にアメリカに行って成功する!」的な若気の至り的無謀な夢を持っていたので、歌詞を書ける外国人と一緒に音楽活動をしたかった。で、どう言うきっかけか覚えてないけど、そのイギリス人の子と一緒に音学活動をするようになった。バンドと言うより、ユニットとして2人でやっていたんだけど、大雑把な流れはこんな感じ。
- 曲を作る
- 音源(カラオケ)を録音し、メロディーラインも入れる
- イギリス人の子が歌詞を書く
- 編曲し直し、再度オケを録音する
- イギリス人の子が、歌とコーラスを入れる
毎回、こんな流れでやっていたんだけど、当然お互いに意見を言うことになる。まず曲を渡した段階で、構成やメロディーラインに対して、イギリス人の子から意見が出る。
歌詞に関しては、自分から注文をつける事はほとんどなかったけど、歌入れの時はかなりダメ出しをする。このやり取り、この時点ではインターナショナルパーティーでの経験もあるのでかなりはっきりと自分の意見を言おうとする姿勢はできていた。しかしながら、結局毎回喧嘩していた。と言うのも、(これは外国語中級者あるあるなのだが)、今思えば恐らく「意見を言う=直接的に何でもかんでも言いたいことを言う」と言う事態に陥っていたのだと思う。
英語は日本語に比べれば、「自分の考えをはっきりと言う」言語であり文化であるとは思うが、だからと言って、「意見を言う=直接的に何でもかんでも言いたいことを言う」と言うわけではない。
当時の自分は、「意見を言う=直接的に何でもかんでも言いたいことを言う」事によって、「英語でコミュケーションができる!」と独りよがりの状態だったんだと思う。今考えると彼女に悪いことをしたと思う。随分と言いたい事をズケズケと言ったものだ。
でも、これは非常に貴重な経験で、「英語はコミュニケーションのツール」として使った初めての経験だったのかもしれない。とにかくいい曲をつくりたくて、お互いに言いたい事を言った。そして、この目的のためには、「自分の英語力不足を痛感」した。やっぱり圧倒的に語彙力不足だし、直ぐに反論できないことが多かった。いつも別れた後に、「あの時こういえば良かった」とか、「きっと彼女はこう言う意味で言っていたんだ」とか思うことが多かった。
インターナショナルパーティーもそうだけど、こう言う経験は、後に仕事上外国人社員を管理し、時には裁判をするようなケースになった場合にも非常に役に立った。
③ モデル事務所
この頃、築地の魚市場を辞めて、外国人モデル事務所で働いていた時期があった。恐らく1年程度だったと思う。海外のモデル事務所から3ヶ月契約で日本に呼んで、広告代理店に紹介して仕事を取る、みたいな仕事。これは、30歳くらいの頃、20代を「魚市場でバイトしながらバンド活動」してきたものの、売れる気配が見えず。将来のことを考えて、とりあえず「魚市場からは離れよう」と思ってフルタイムの仕事としてモデル事務所で外国人女性モデルのマネージャーを始めた。
毎日青山のオフィスからモデルの子を連れてオーディションに行って、夜は六本木のディスコ(死語か!)に行って、(と言うのも当時は外国人モデルはフリーパス、マネージャーもタダで飲食できた!)、三軒茶屋にあった寮に連れ帰ってって生活だった。まぁ、それなりに色々あったけど、英語学習の観点に絞って考えると、「あまり教養のないネイティブスピーカーとコミュニケーションを取る」経験かな。「教養のない」と言うのは表現の仕方が悪いかもしれない。大多数のモデルは15-6歳くらいなので「子供」。だから大人としてのコミュニケーションが成立しないことがある。
とは言え、小学生ではないし、ちゃんと仕事もしている社会人。仕事をすると言う面では非常にプロフェッショナルでもあった。何だろう。段々と「英語」とか「外国」と言う憧れ、それに伴う幻想が無くなってきて、人間対人間としてコミュニケーションとして考えられるようになったのだと思う。
この経験も、後に上司として多くの外国人講師を管理する立場になった時に役に立った。と言うのも、多くの日本人が、「英語」とか「外国」と言う憧れ、それに伴う幻想、を持っているので、職場で外国人と一緒に働くときに自分の意見を言えずにフラストレーションを抱えることが多い。「英語学習者」としてのメンタリティーが強く、「外国人/ネイティブスピーカー=全て正しい」みたいな発想に陥ることが多い。早い段階で、この発想を払拭できた事は非常に役に立ったと、今振り返ってみて改めて実感している。