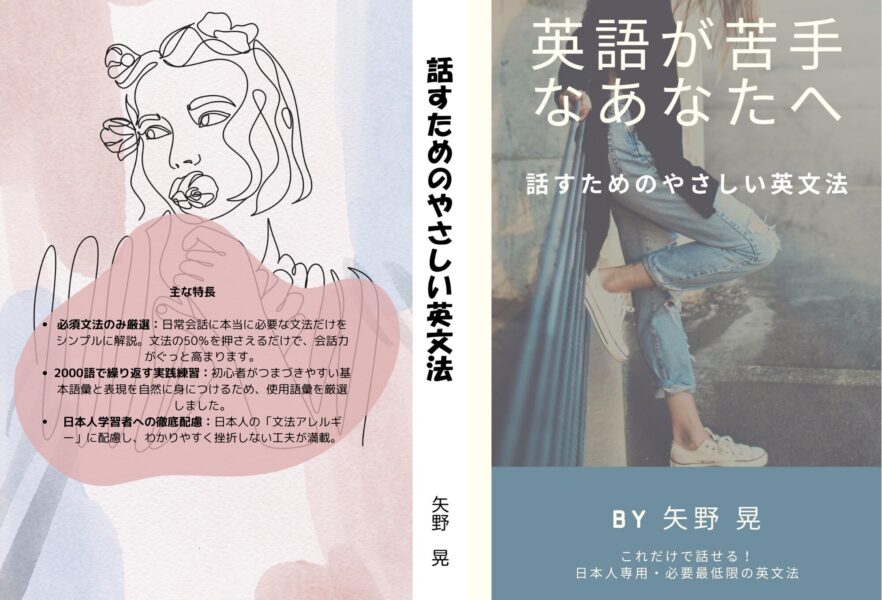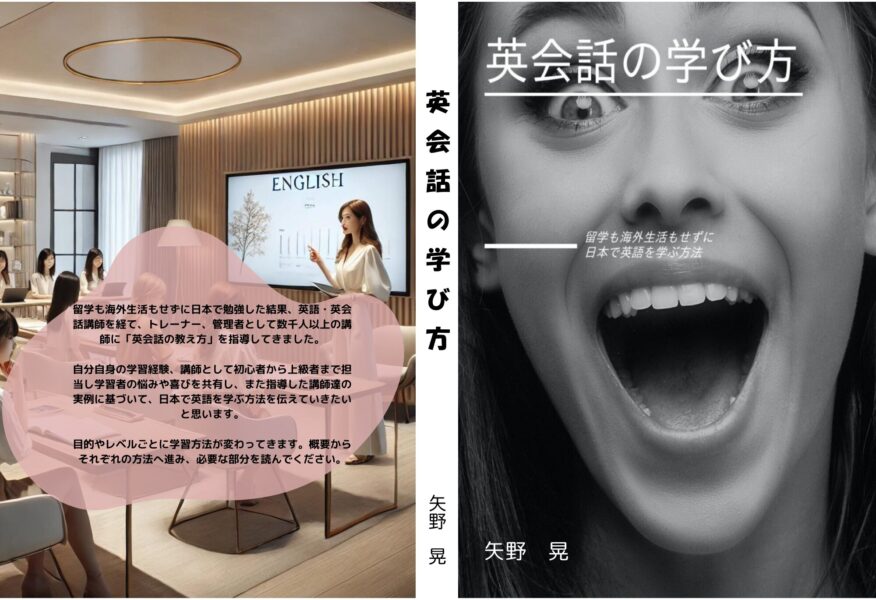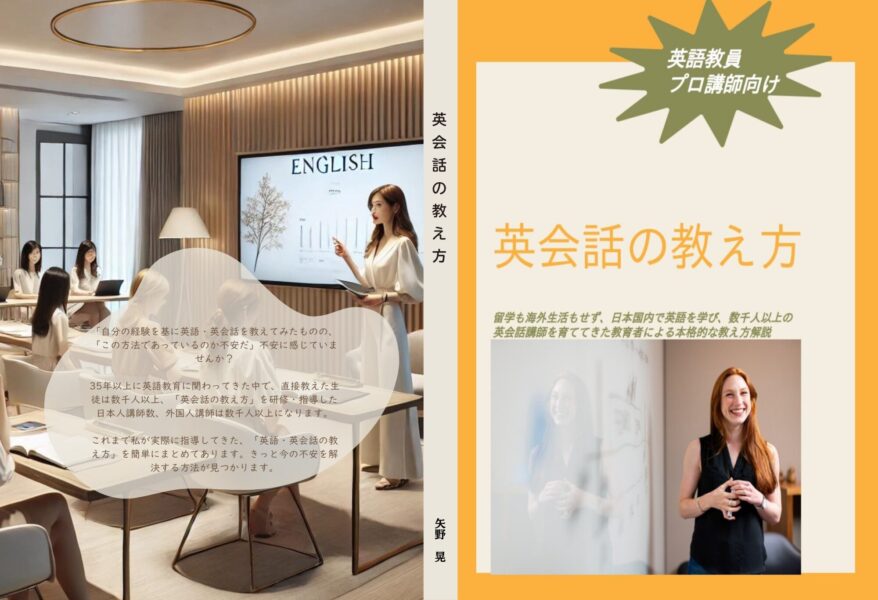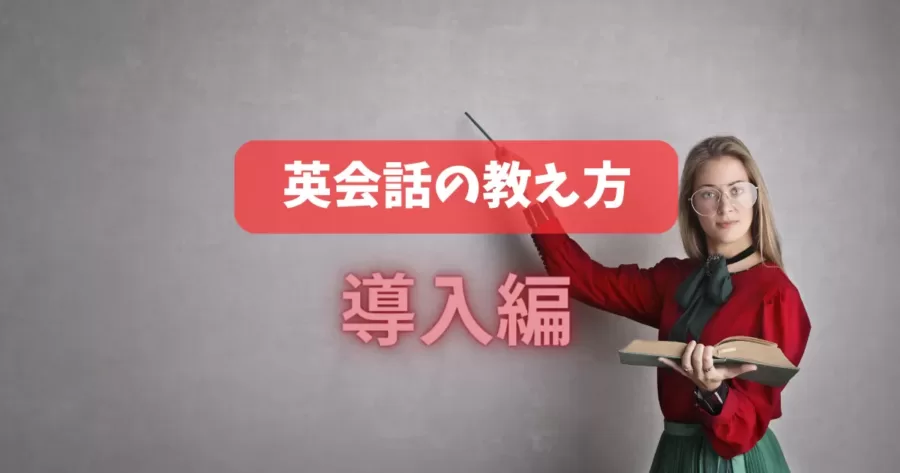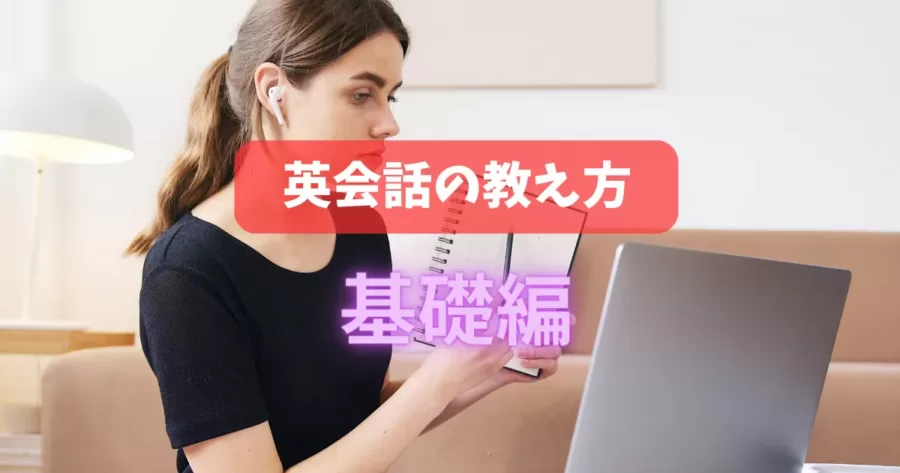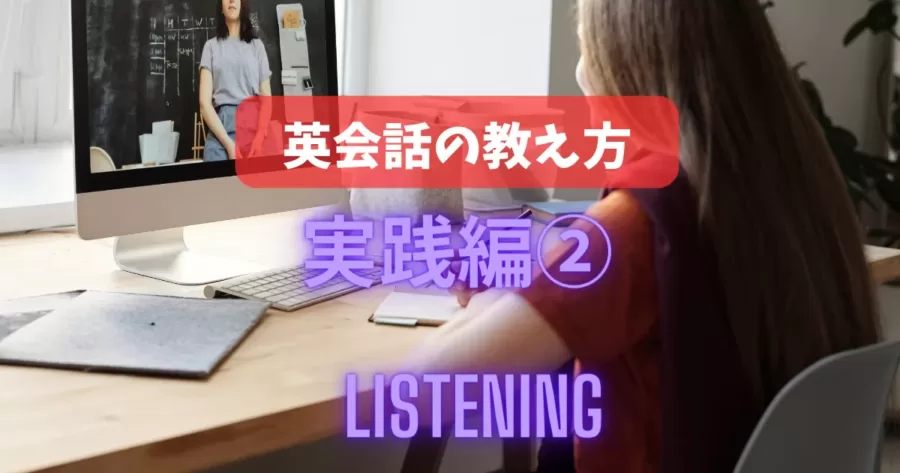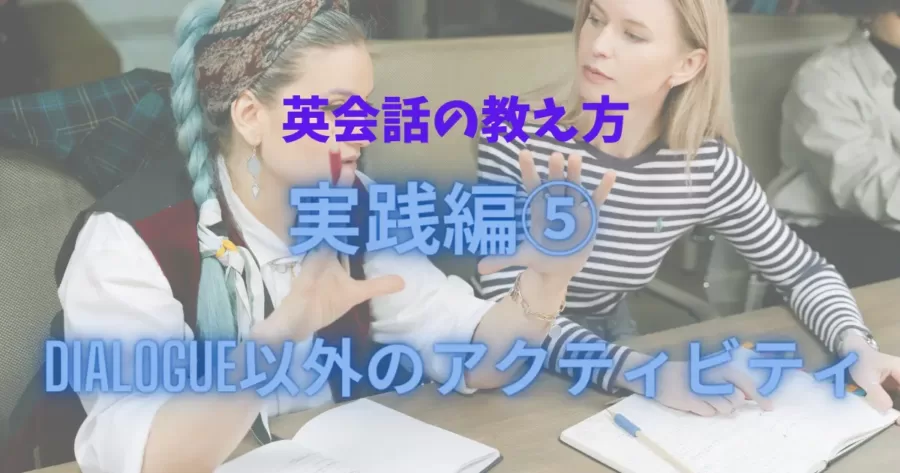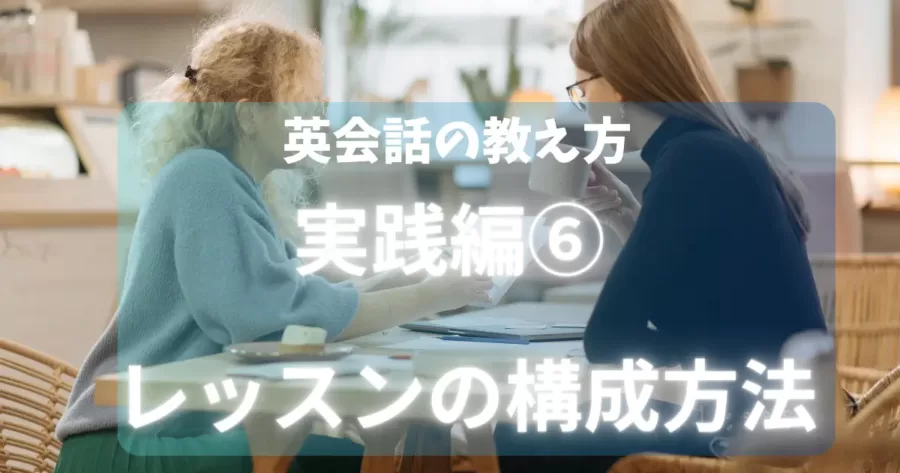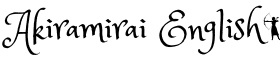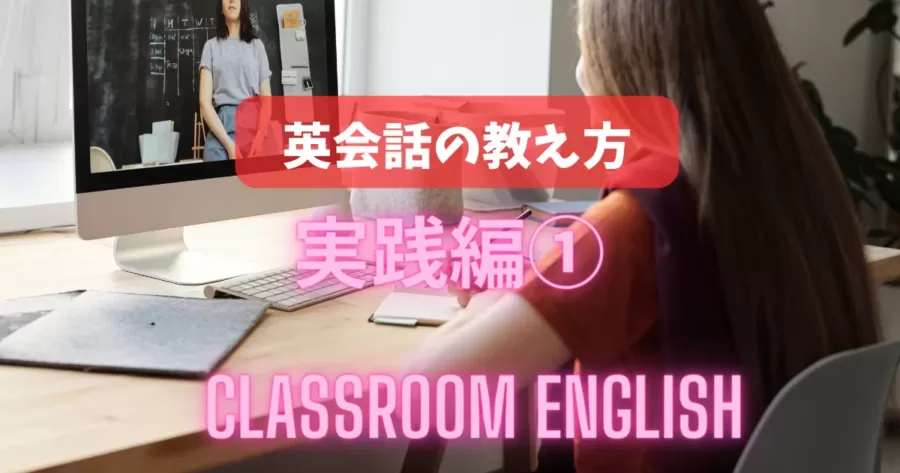「英語を教えてみたい」「英会話を教えてみたい」と思ってみたものの、いざ教えてみようとすると、「どうやって教えたらいいのか」「どんなテキストを使ったらいいのか」迷ってしまう。あるいは、実際に自分の経験を基に英語・英会話を教えてみたものの、「この方法であっているのか不安だ」、「生徒とうまくかみ合わない」などと不安に感じていませんか?
私は留学も長期間の海外生活を送ったこともありませんが、20代前半から英語・英会話を教え始め、その後英会話スクールで、講師トレーナー、教務課責任者、事業部長などを務めながら35年以上にわたり、英語教育に関わってきました。その間に直接教えた生徒は数千人以上、「英会話の教え方」を研修・指導した日本人講師数千人以上、同様に研修・指導した外国人講師数千人以上になります。
これまで私が実際に指導してきた、「英語・英会話の教え方」を簡単にまとめてあります。「英語・英会話の教え方」に関しては、ある「一つだけの正解」はありません。あくまでも、一つの例として参考にしてください。
1.良いレッスンとは

まず、英会話のレッスンとしてどんなレッスンが、「良いレッスン」なのか考えてみましょう。
当然ながら、いろいろな考え方があると思います。「とにかく楽しければ良い!」とか「ひたすらストイックにスパルタに!」とか、以前にもお伝えしたように、「ただ一つの正解」はありません。
この中で私の考える「良い英会話レッスン」とは以下になります。
- T/Lがacquireできる
- Student-centered
- Challenging
一つ一つ見ていきましょう。
① T/Lがacquireできる-
T/Lとは、Target Languageと言う意味です。私がAEONで研修していた時は、Teaching Point と言っていました。AEONのレッスンは比較的文法的な項目をレッスンのポイントとして扱っていた事が多かったのでしっくりきたのですが、その後AEONを退職した後に別のスクールで英会話スクール事業をしていた時に、少し考え方が変わり、レッスンのターゲットが必ずしも文法的な項目とは限らなくなってきました。そのため、なんとなくTarget Languageの方がしっくりくるように感じたのです。特に深い意味はありませんが、一つ一つのレッスンで何を身につけてもらうか、と言う事になります。
なので、「文法的なポイント」かもしれないし、「Function」かもしれないし、「語彙・表現」かもしれません。テキストのところでも説明しましたが、教える前に自分自身でこの「Target Language」を正確に把握する必要があります。講師の指導をしていた時に、この点を何回も何回も注意してきました。多少経験を積んでくると、テキストをよく理解せずに自分の思い込みで教えてしまう人がいます。なんでも身につけば良いじゃないかと思うかもしれませんが、レッスンは1回1回のレッスンだけでなく、6ヶ月とか1年間のコースとして考える必要があります。
1年のコースであれば、1年後に次のレベルに上がれないといけません。そのためには、1回1回のレッスンで、「そのレッスンで身につけるべき事」を定着させないといけません。しかしながら、「そのレッスンで身につけるべき事」を講師が把握してなければ、レッスンの目的は達成できません。それを1年間続けたところで次のレベルに上がれなくなってしまいます。
分かりやすい例で例えると、あるレベルの到達目標が、「現在・過去・未来の基本3時制をマスターする」であるのに、ずっと「食事の話」ばかりしていたのでは、次のレベルに上がれません。個人で教えているプライベートレッスンで、その生徒がそれで満足しているのであれば問題ないのですが、(これも「しばらくのうちは」と言う条件付きです)、英会話スクールに入学して1年間のコースを受講するのであれば、そう言うわけにはいきません。必ず次のレベルに、レベルアップさせるのが講師の仕事です。
この「Target Languageを正確に把握する」に加えて、もう一つのポイントは、「acquireできる」です。この「acquire」はちょっと大袈裟なのですが、英会話のレッスンは必ず「Productive Level」で考えます。「どれだけ理解したか」ではなく、「自分の言葉として使いこなせる」と言うレベルです。
「導入編」「基礎編」から読んでくれてる方にはわかると思いますが、「Productive Level」を意識してレッスンが出来るようにならないと、生徒は上達しません。学習環境も大きな影響を持ちます。週1回のレッスン以外は、毎日日本語の生活をしているのです。その生徒が週1回のレッスンで練習した内容を実際に使う機会が来るのは、数ヶ月後に海外旅行に行った時です。その時に実際に使えれば、「英会話のレッスンを受けて良かった!」と言う事になるし、使えなければ、「英会話のレッスンを受けても役に立たなかった!」と言う事になります。
そのためには、毎回毎回のレッスンで、「Target LanguageをAcquire」させる事が必要になります。その結果として、海外旅行に行った時に使えるし、1年後にレベルアップできるのです。
② Student-centered-
その名の通り、「生徒中心」です。「講師中心」ではありません。新人講師はどうしても「教えよう!教えよう!」として頑張ってしまいます。しかしながら、講師が頑張れば頑張るほど、つまり「熱心に説明すればするほど」、生徒は聞き役になります。と言っても、初心者の場合、講師が一生懸命英語で説明していることは50%も分かりません。
英会話のレッスンは、学校の授業のような「レクチャータイプ」ではありません。週1回40分-50分のレッスンは、基本的には「話す練習」が中心になります。講師が説明する場ではなく、生徒が練習する時間と言う意識を明確に持ちましょう。
乱暴な言い方をすれば、「講師が説明して10個の事を理解する」よりも、「生徒が繰り返し練習して、1個の事を実践できるようになる」方が、ずっと「良いレッスン」です。ここで誤解して欲しくない事は、「説明するな」、「生徒中心にせよ」と言うと、何も言わずに生徒の発話を待ってしまう講師がいます。生徒が話せるように「お膳立て」するのは講師の大切な役目なので誤解しないようにしてください。具体的な方法は後述します。
Student-centeredにするために出来る事を二つほどあげておきます。まず1点目は、コミュニケーションラインを増やす事です。具体的には、ペアワークとグループワークを使います。
グループレッスンの場合、講師が一人の生徒と話している時間は、他の生徒は待ち時間になります。例えば、定員4名のレッスンであれば、残り3人は待ち時間になります。この「講師が一人の生徒と話す」と言うパターンを続けてしまうと、1回40分のレッスンであれば、生徒一人の持ち時間は10分と言う事になってしまいます。この理屈は「マンツーマンレッスン専門の英会話スクール」が「グループレッスン中心のスクール」を貶めるために良く利用していました。
これが生徒2人1組で練習するペアワークを実施すると、2組のペアが同時進行で話すので、計算上は40分間練習する事になります。実際には色々と工夫しないといけないのですが、生徒の発話時間は増える形になります。
ペアワークやグループワークは生徒の発話時間を増やすために非常に有効な方法ですが、やり方を間違えると、「初心者の日本人生徒同士が練習しても話せるようにならない」と言う印象を生徒に与えてしまいますので注意が必要です。
もう一つ大切な事は、「レッスンのテンポ・スピード」です。どんなにペアワークやグループワークを使っても、レッスンがゆっくりとノロノロと進んでいくのでは、結局発話量は増えません。「レッスンのテンポ・スピード」が良ければ発話量は増えます。
分かりやすいように数で説明すると、A先生はレッスンを進めるのが非常に遅くて1回のレッスンで3つの練習しかできません。B先生のレッスンは非常にテンポが良く1回のレッスンで12個の練習ができます。この差は一目瞭然です。
では、どうしてこの「レッスンのテンポ・スピード」の差が出てしまうかというと、技術の差です。「レッスンのテンポ・スピード」が良いのは、テンポ・スピードが良くても生徒がついてこれるからです。
なぜ生徒がついて来れるかというと、講師がよくレッスンを準備して、レッスンの構成がいいので生徒にとって受けやすいレッスンなのです。一番大きいのは、指示の出し方です。講師が練習内容をよく把握していて、生徒に明確な指示を出していれば、テンポ・スピードが良くても生徒がついてこれます。
反対に、講師が練習内容をよく把握しておらず、生徒に出す指示も不明瞭で「生徒が何をしていいかわからない」状態に陥っている場合、非常にゆっくりとレッスンを進めないと生徒がついてこれません。
この、「ペアワーク・グループワークを使う」、「レッスンのテンポ・スピードを上げる」と言う二つのことを意識し実践できれば、Student-centerdなレッスンに近づきます。
③ Challenging-
これは1回1回のレッスン、一つ一つの練習の進め方の話です。レッスンは、「難しすぎ」ても「易し過ぎ」ても効果が半減します。「易し過ぎる」とレッスンに物足りなさを感じ、上達実感が得られません。やる気も半減します。反対に「難し過ぎる」と何をやっているのか分からなくなり、レッスンを受ける事を苦痛に感じます。
この「難し過ぎる」と「易し過ぎる」の中間点である、「少し難しい」程度を設定することが理想的です。「少し難しい」ので上達実感が得られるし、「難し過ぎる」ほど何をやっているのか分からなくなることもありません。
この「少し難しい」程度を把握する事が非常に難しいようです。私の場合、海外生活をせず日本で英語を勉強したし、塾講師をしていたので学校教育の英語を熟知していたので、生徒のレベル、「何を理解していて、何が分からないのか」をかなり正確に理解していました。そのため、レッスンを「難し目」に進めたり、「易し目」に進めたりというコントロールが比較的容易にできたのです。
ただし、これから「英会話を教えてみよう」と思っている人は少し状況が違うと思います。恐らく、留学(短期留学含む)をしたり、海外生活を送ったりしながら、英語コミュニケーション力を身につけて、その英語力を活かして「英会話を教えてみよう」と思っているのでしょう。実際に、過去に私が採用し、研修した英会話講師のほとんどが同じようなタイプでした。
「レッスンをChallengingにする」という事は、つまりその前提として「生徒の英語レベルを正確に把握する」という事です。そのためには、中学校の英語の教科書や問題集などを研究するのが最適です。是非、週末の時間を使って研究してみてください。これをするかしないかで、その後のティーチング力に大きな差が出てきます。
ちょっと抽象的な話になってしまいましたが、簡単にまとめると以下にようになります。
- 生徒のレベルを正確に把握する
- レッスンのレベルを「少し難し目」に設定する
「少し難し目」というのは、「頑張れば出来る」というレベルです。例えば「腕立て10回出来る」と言う人にとっては、「腕立て3回」は簡単過ぎますし、「腕立て1000回」は難し過ぎます。「腕立て15回」は「少し難しい」と言うレベルでしょう。出来ないことはないけど、頑張らないといけない、と言うことです。
その際、必ず「生徒の頭」で考えてください。特に初心者を教える場合、講師の目から見ると、テキストも練習内容も非常に簡単に見えます。しかし、初心者の「生徒の頭」で考えると決して、簡単ではありません。
また、練習方法そのものも難易度に影響してきます。講師の後についてリピートする事はそれほど難しくないかもしれませんが、自分のことについて話すのは難しいでしょう。練習に掛ける「時間」も大切なポイントです。同じ練習を、「3分掛けて行う」のと「20秒で行う」のでは全く難易度が変わってきます。
使用されている語彙・文型のレベル、練習内容の難易度、練習するスピード、などを総合的に判断して、各アクティビティの難易度を把握し、その難易度が「生徒の頭」で考えた時に、「少し難し目」に設定していくのです。
最初のうちは難しい作業だと思いますが、このことを常に意識していくと数ヶ月で身につける事ができます。反対に何も考えないでレッスンしていると、いつになってもこの「非常に大切な感覚」を身につける事はできないでしょう。
是非最初の段階で頑張ってみてください。
2. クラスルーム・イングリッシュ

1)クラスルーム・イングリッシュとは
Classroom Englishとは、レッスン中に講師が話す英語の事です。「英会話のレッスンを英語で行う」場合、Classroom Englishは最も大切な技術の一つです。そして、「英語でレッスンを教えたことのない人」や「講師初心者」にとって、最も難しい技術になります。
「英会話のレッスンを英語で行う」場合、Classroom Englishが上手く使えるか、的確にコントロール出来るかどうかによって、レッスンが分かりやすくなるか、テンポよく進むかが決まってきます。
何故、Classroom Englishを的確に使う事が難しいのか、それは以下の2つの理由です。
- 自分の話している英語のレベルを客観的に判断できない。
- 生徒の英語レベル、特に「聞いて理解する」レベルを把握できていない。
この2つの事は非常に密接に関係しています。どちらの場合も、生徒レベルの観点から、語彙・表現、文法・文型、などの難易度を把握できているかどうかと言う事です。この、語彙・表現、文法・文型の難易度が把握できている場合、つまり「2. 生徒が効いて理解する事の出来るレベル」を把握できている場合は、「1. 自分の話している英語レベルを客観的に判断」できるように、「常に自分の話す英語をモニターする」習慣を身につければ、比較的に短時間で、Classroom Englishを的確に使えるようになります。
反対に、語彙・表現、文法・文型の難易度が把握できていない場合、「2. 生徒が効いて理解する事の出来るレベル」が理解できていないと、非常に難しくなります。単に「教える練習」をするだけでは、Classroom Englishを的確に使えるようになりません。日本人の英語学習過程をしっかりと理解するところから始める必要があります。「導入編」や「基礎編」で書いたように、中学校・高校の英語のテキストを見直す事が最短距離です。
恐らくこの記事を読んでいる人は、日本の学校教育を受けてきている人がほとんどだと思うので、あまり心配する必要はありません。学校で英語を勉強した時の記憶が残っているので、多分、感覚的に英語の難易度を理解できると思います。
実際に、どのようにClassroom Englishを使うのかは、次のコーナーで説明しますが、具体例があった方が分かりやすいと思うので、簡単な例を出します。初心者に英会話のレッスンをしていると思ってください。
- ① 文法レベル
-
- 過去形 vs 現在完了形
一目瞭然ですよね?
何故だかわかりますか? 非常に簡単な理由です。過去形は中学校1年後半から2年に学びますが、現在完了形は中学校3年生くらいです。英語の好き嫌いは、過去形が出てくる中学2年くらいに一つの波が来て、現在完了形や関係代名詞が出てくる中学3年生で決定的になります。
所謂「英会話スクール」で「今年こそ英会話!」的な感覚でレッスンを受講始める初心者の場合、中学校3年くらいから英語が嫌いになっているタイプが非常に多い気がします。
分かりやすくするために「時制」を例に挙げましたが、時制に限らず、文法時刻や文型がレッスンを受けている生徒のレベルによって、「何が理解できて、何が難しいのか」を把握し、自分の話す英語をコントロールする、と言う事がClassroom Englishの基本です。
- ② 語彙レベル
-
- tired vs bored
恐らくこれも感覚的に分かると思います。(あくまでも極基本的な意味で考えてみてください)
所謂、英会話スクールの初心者クラスで受講している生徒にとって、tiredの方が簡単ですよね? 理由は先程と同じです。tiredは恐らく中学校1年生で学び、boredが出てくるのはずっと後です。だいたいにおいて、学校の教科書に出てくる順番で難易度が決まってくると思ってください。当然ながら、数えられる名詞・数えられない名詞とか、可算・不可算名詞とか、冠詞とか、日本人にとって理解しにくい項目は、教科書に出てくる順番と関係ありません。
この文法事項のレベルにしても、語彙レベルにしても、自分で日本の学校教育を受けてきている人にとっては、少し復習するだけである程度把握できるようになると思います。把握出来たら、自分の話す英語を常に客観的に判断する癖をつければ大丈夫です。
それに対して、外国人講師のトレーニングする時は非常に大変でした。彼らにとって、「過去形と現在完了形」とか「tiredとboredの違い」とか、全く理解できない事だからです。私達日本人が、「連用形と未然形」とか「“楽しい”と“優しい”の難易度」とか言われても、全く理解できないのと同じことです。なので、外国人にClassroom Englishを教える時は、「短い文でゆっくり話せ」と非常に簡略化したトレーニングをしていました。
2) Classroom Englishの基本
では、Classroom Englishの基本です。Classroom Englishの基本はこのキーフレーズに集約されます。
SSC = Short, Simple, Clear
これは、私自身が英会話講師としてAEONで勤務開始する前に受けた新人採用研修で教わった事です。その後、AEONで講師トレーナーとして自分で講師研修をするようになったり、教務課責任者になって講師研修マニュアルや研修計画を作成する際に使い、その後、別の英会話スクールで事業をする時に使ってきました。
- Short = 簡潔に
- Simple = 簡単な構文で
- Clear = 発声をクリアに滑舌良く (正確には、Clearlyです)
具体的な例を挙げます。ここでは、初心者に対してレッスンを行う場合の例を挙げます。
- ① 命令文を使う
-
〇 Open your textbooks.
✕ I’d like you all to open your textbooks.
✕ Could you please open your text books?
日常生活で友人や同僚と話す時に、いきなり命令文を使う事は多くないかもしれません。英会話講師初心者には、「日常的に友達と話す時の話し方」と「レッスン中で生徒に対して使う、Classroom English」の区別や使い分けが難しいようです。
最初のうちは心理的に抵抗があるかもしれませんが、気にせずに「命令文」を使います。
この場合のポイントは、「スピードでコントロールせずに、文法レベル/文型でコントロールする」と言う事です。
- ② 疑問文は直接聞く(間接疑問文を使わない)
-
〇 Who is he?
✕ Do you know who he is?
✕ I wonder if you know who he is.
やはり日常生活の中では、あまり親しくない人に対して直接的な聞き方はしないかもしれません。英会話講師初心者には、話している最中に違いを見出すのは難しいかもしれませんが、こうやって書き起こした文字を見れば、その違いが一目瞭然だと思います。しつこいようですが繰り返します。「スピードでコントロールせずに、文法レベル/文型でコントロールする」と言う事です。
- ③ 関係代名詞・関係副詞は使わない
-
✕ This is the girl I used to work with back in my hometown.
✕ Do you know someone called Shohei Otani who struck out Mike Trout in WBC?
さすがにこのレベルになると説明する必要ありませんよね?
Short, Simpleからかけ離れています。関係代名詞や関係副詞を使うと文型的に難しいので初心者には分かりづらくなるだけでなく、文が長くなります。初心者には長い文章を理解する事が難しいのです。この例文のレベルくらいの長さになると、「文字を目で見て読んだとしても」直ぐに理解する事は難しくなります。一度文頭から最後まで目を通し、主語や動詞を探し、文型は把握し、文の構造を解読していきます。文字を見ずに音だけで聞いて理解する事は非常に難しくなります。次の原則を覚えてください。
- 初心者が聞いて理解出るセンテンスの単語数は、5単語~7単語。
あまり厳密に考える必要はありませんが、大体自分で使う文の単語数が5単語~7単語以内に収めるようにします。「情報量が多い時はどうしたら良いのか?」と思うかもしれませんが、その時は、ワンセンテンスにまとめずに、複数の文に分けます。
例えば最初の例であれば、
✕ This is the girl I used to work with back in my hometown.
⇒ Look at this girl. She and I are friends. We worked together in my hometown.
- ④ 接続詞は極力避ける
-
✕ Even though I was extremely tired, I managed to do all the work I was assigned to.
✕ No matter how hard I tried, I couldn’t convince her to stay.
もう説明の必要はないですよね?
文型も難しいし、文が長く単語数が多いので初心者の生徒は付いて来られず、文の途中でロストしてしまいます。
レッスン中にこのような文を使って話していて、生徒が全く理解でいないので、困っている講師をよく見ました。(理解できなくて当たり前ですが) 理解できないと、同じセンテンスを何回も繰り返して分からせようという講師もいます。それでも分からないので、極端に話す速度遅くして、異常にゆっくりと話す講師もいます。ゆっくり話しても無駄です。初心者相手にこの文章を何回繰り返してもわかりません。
- ⑤ 仮定法を使わない
-
✕ If you were his girlfriend, how would you feel?
初心者の場合、仮定法のコンセプトは理解していない場合がほとんどです。この例のような文を使うと、
“No, no!” “He not my boyfriend!”
みたいな答えが返ってきます。
このような場合も、生徒が理解できないと、異常にゆっくり話したり、極端に”If”を強調し、何回も”If”を繰り返す講師がいます。何回”if”と言っても、仮定法のコンセプトを理解していなければ、わかりません。
しつこいようですがもう一度繰り返します。「スピードでコントロールせずに、文法レベル/文型でコントロールする」と言う事です。
- 文型・文法レベルは生徒が理解できるレベルで話す
- 語彙・表現も生徒が理解できるレベルで話す
- スピードは極力落とさない
初心者のレッスンだからと言って、話す速度を極端に落とす必要はありません。文型と語彙レベルを調整し、ワンセンテンスの長さを5単語~7単語に抑えれば、普通の速度で話しても理解できます。そうすることで、レッスンのテンポが上がり、練習量が増える事になります。
- ⑥ Clearlyに話す
-
Short, Simple, ClearのClearです。文字で説明するのは難しいのですが、要するに滑舌良く話すという事です。日本語でも英語でも普段家族や仲の良い友人と話しているときのことを思い出してください。
「単語・表現・文型」ではなく、「発声」の面で考えてみてください。どんな話し方をしていますか? かなり「省エネ」的な話し方をしていると思います。恐らくあまり口を大きく動かさずに、どちらかと言うともごもごした話し方でしょう。
家族や友人と話している、その「話し方」のままで、英語でレッスンしてしまうと、生徒には非常に分かりづらくなってしまいます。
どれほど、「語彙レベル」や「文型・文法レベル」、「ワンセンテンスの単語数」に気を使っても、非常にわかりづらいClassroom Englishになってしまいます。
イメージして欲しいのはアナウンサーです。ナチュラルスピードですが、滑舌良くはっきりと話します。多少早口で話してもよく聞き取れると思います。
「Clearlyに話す」とは、滑舌良くはっきりと話すという事です。また話す時の音量にも気を付けてください。生徒の人数が増えれば増える程音量が必要だと思ってください。特にグループレッスンで生徒数4-5人になると大きな声を出す必要があります。
これは日本語でも同じですよね? 1対1で個室で話しているときはそれほど大きな声を出す必要はありませんが、多少大きめの会議室で7⁻8人の同僚とミーティングしている時では音量が違うと思います。
生徒数の数に応じて音量の調整が必要になります。特に初心者が英語で理解しようとしている訳なので、①はっきり話す、②十分良く聞こえる音量で話す、は必要絶対条件になります。
また、この「はっきり話す」「滑舌良く話す」と言う時に、アナウンサーをイメージすると良いと書きましたが、もう一つ意識して欲しい事は、「辞書の発音記号」通りに話すという事です。
これまで研修してきた日本人講師の中に発音記号が分からない人がかなりいました。音声学でも勉強しない限り、あまり意識しないのかもしれませんが、「英語を教える」と言う事を、特に「お金を貰って英語を教える」と言う事は始めるのであれば、発音記号を理解し、その発音記号の音の出し方を言葉で説明できる、と言う事は非常に重要なスキルになります。自信の無い人は是非この機会に勉強してみてください。
3) インストラクションの出し方
Instructionsとは「指示の出し方」です。当然ながら、先程説明した、「Classroom English」の原則が大前提になります。その中でも英語でレッスンを進めていくうえで、インストラクションの出し方は非常に大切な部分になります。
生徒が言う、「分かりにくいレッスン」とか「難しいレッスン」とは、だいたいにおいて、「Classroom Englishが的確に使えない講師のレッスン」、「インストラクションの下手な講師のレッスン」であることがほとんどです。
インストラクションが上手く出来ないと、生徒は「何をどうしたら良いのかわからない!?」状態に陥ってしまい、非常に困ってしまいます。この場合、英語の初心者である生徒は、「何をどうしたら良いのかわからない!?」状態に陥った場合、自分に原因があると考えてしまいます。「自分の英語力が低いから出来ないんだ」とやる気を失ってしまいます。そのままレッスンに来なくなってしまう事にもなりかねません。レッスンがスムースに進むか、生徒がたくさん練習できるかは、インストラクションの出し方に掛かってきます。
まずClassroom Englishの基本を復習しましょう。インストラクションの出し方についてもポイントまでは同じです。
- Short = 簡潔に
- Simple = 簡単な構文で
- Clear = 発声をクリアに滑舌良く (正確には、Clearlyです)
具体的な例を挙げます。ここでは、初心者に対してレッスンを行う場合の例を挙げます。
- ① 命令文を使う (これはClassroom Englishの復習ですが、一番大切です。)
-
〇 Open your textbooks.
✕ I’d like you all to open your textbooks.
✕ Could you please open your text books?
日常生活で友人や同僚と話す時に、いきなり命令文を使う事は多くないかもしれません。英会話講師初心者には、「日常的に友達と話す時の話し方」と「レッスン中で生徒に対して使う、Classroom English」の区別や使い分けが難しいようです。
最初のうちは心理的に抵抗があるかもしれませんが、気にせずに「命令文」を使います。
この場合のポイントは、「スピードでコントロールせずに、文法レベル/文型でコントロールする」と言う事です。
ここまでは大丈夫ですね。
- ② 自分の行動を説明しない
-
✕ I’m going to ask you some questions.
✕ I’m going to erase all of them because we don’t need them anymore.
「あれ、〇が無い」って思いましたか?
必要ないんです。何も言わなくて構いません。” I’m going to ask you some questions.”なんて言わずに、質問すれば良いのです。
“I’m going to erase all of them because we don’t need them anymore.”などと言わずに黙って消せば良いのです。
沈黙の時間が怖いのかもしれませんが、初心者の場合、講師の言う事は全て聞き取ろうとします。大切な事や必要な事と、そうでない事の区別が難しく、何か一つでも聞き取れないと不安に感じます。
余計な事を言えば言うほど、生徒が付いて来られなくなるし、レッスンのテンポが悪くなります。
- ③ インストラクションは一度にひとつ
-
✕ Now, let’s move on to the next practice. First, I will read the example sentences, next you will repeat after me altogether and then we will make some groups and work together.
クラスルームイングリッシュの箇所で説明したのでわかりますよね?
単語レベルは難しくないし、文型もそれほど難しくはありません。ただし、これほど長々とまとめて話されると、初心者の生徒は途中でロストします。
思い出して下さい。
- 初心者が聞いて理解出るセンテンスの単語数は、5単語~7単語。
また、たとえ聞き取れたとしても、「最初に~、次に~、その後に~、最後に~」と言われても、聞き終わった段階で、「最初に~、次に~」の部分を忘れてしまっています。結局、もう一度同じインストラクションを出す羽目に陥ります。
インストラクションの原則は、「一度に一つ」です。
先程の例であれば、
✕ Now, let’s move on to the next practice. First, I will read the example sentences, next you will repeat after me altogether and then we will make some groups and work together.
〇 Listen.
Repeat.
You are A and you are B. Work together.
“Listen”と指示を出し、生徒に聞かせる。
“Repeat”と指示をだし、生徒にリピートさせる。
“You are A and you are B.” と具体的にパートを伝える。
“Work together.” と指示を出して、AとBの役割練習をさせる。
このようにインストラクションは、「一度に一つ」です。
- ④ 見本を見せる
-
✕ Now this exercise can be a little tricky. You will be working in pairs. Student A will ask these questions and Student B will answer them but need to fill in the blanks using these expressions but be careful because sometimes you will have to change some expressions.
もう何だか訳が分からないですよね?
「こんなバカみたいなことはしない!」と思っているかもしれませんが、意外とみんなやってしまいます。
インストラクションの原則はこれです。
- 説明しない!
言葉で説明しようとすると沼にはまります。そもそも相手は英語の初心者で、ワンセンテンスで聞き取れる単語数は5単語~7単語です。説明すればするほどわからなくなります。レッスン中に生徒の顔を見る余裕が出てきたら直ぐに分かります。生徒の目が「????」になっています。
言葉で説明せずに、「見本」を見せましょう。
言葉で説明せずに、生徒と一緒に「試しに一つ」やってみましょう。
1回目は「予行演習」です。2回目からが本番です。
- ⑤ 見せる
-
✕ Now this exercise can be a little tricky. You will be working in pairs. Student A will ask these questions and Student B will answer them but need to fill in the blanks using these expressions but be careful because sometimes you will have to change some expressions.
先程と同じ例です。
実際には次のような練習をしようとしているところです。
A: What did you do yesterday?
B: I ______________________
A: Really? Who did you go with?
B: _______________________
A: Did you have a good time?
- go shopping
- go to the movies
- go to a concert
- mother
- friends
先ほどのように、言葉で説明しようとせず、いきなり始めます。
〇 I will be B and you all will be A.
Start.
余計な説明はせずに、” I will be B and you all will be A” と具体的に役割を指定します。
“Start”と言って、生徒全員にAのパート“What did you~”と聞かせます。
Bのパートの“I” と言ってから、選択肢の”go to the movies”を指さしながら、ゆっくりと“I went to the movies.”と言います。
指でAのパートを指しながら、生徒全員にAのパート” Really? Who~”と言わせます。
選択肢の”friends”を指しながら、”With my friends”と言います。
「百聞は一見に如かず」です。長々と説明するより、目で見せた方がずっとよくわかります。ボードやスクリーンを使い、必ず生徒と同じものを見ながら進めましょう。
4)リアクション
Classroom Englishのセクション最後のパートです。リアクションは非常に大切です。英会話のレッスンとは、その名の通り「会話/話す」練習です。「会話」なので一方的に話すわけではありません。テキストやボードなどは使用しますが、基本的には「言葉のコミュニケーション」の練習です。音声中心のコミュニケーションで、文字が無いので初心者には非常に不安です。その不安を取り除く事がリアクションの第一の目的です。
- ① ほめる
-
- Good!
- Great!
- Excellent!
まぁ何でも大丈夫です。Awesome とか言っても大丈夫です。単語の意味が分からなくても、タイミングとその場のシチュエーションで意味が伝わります。
何故ほめるか、それは意思表示です。
初心者の場合、聞くのも、話すのも、読むのも、すべてが不安です。(なかなか英語だとイメージ掴みにくいと思うので、勉強したことのない言語のテキストを見てみてください。生徒の気持ちが少し理解できると思います)
例えば、How was your weekend?
と聞かれて、何か答えます。
講師が何の反応もしないと、生徒は不安になります。
- 質問の意味を取り違えたんじゃないだろうか?
- 答えが質問にあっていなかったんじゃないだろうか?
- 文法的に間違っていたんじゃないだろうか?
- 発音が悪くて通じなかったんじゃないだろうか?
などなど。
この状態が続くと気持ち悪くて仕方ありません。
なので、GoodでもExcellentでも何でも良いので反応します。
- その答え方で大丈夫!
- ちゃんと通じてます!
など、すべてひっくるめて、Great!なのです。
簡単に出来そうに思えるかもしれませんが、意外と出来ないものです。と言うのも、レッスンを教え始めて、最初のうちは「自分が次に何をするのか」「インストラクションをどう出すのか」「時間が足らなくなったらどうするのか」など、自分のレッスンの進め方の事で手いっぱいです。生徒に質問したら、質問投げっぱなしにして、答えをちゃんと聞いてない事さえあります。
とにかく、習慣的にGoodなどと言葉が出てくるようになるまで、意識的に反応するようにしてください。
- ② 興味を持って反応する。
-
“Great!”などと、習慣的にほめられるようになりました。
次に意識する事は、所謂リアクションです。「興味を持って反応する」これが一番大切です。初心者の生徒が一生懸命英語で話しています。講師が興味を持って反応してくれると、「話せる喜び」「通じた喜び」「たくさん話した実感」を得られます。反対に、一生懸命話しても講師にスルーされると、一気にやる気がなくなります。
「スルーなんてするわけない!」って思うかもしれませんが、意外とやっています。
T(講師): What did you do last weekend?
S(生徒):I went shopping.
T: Where did you go?
S: I went to Ginza.
T: Who did you go with?
S: With my sister.
T: What did you buy?
S: I bought some shirts.
T: What did you do after that?
これで講師の顔の表情や声の調子が変わらなければ、尋問ですね。
講師の中には、何も考えずに自然とリアクション取れる講師もいるようです。生徒もすごく楽しそうに話しています。日本語でも英語でも「一緒に話していて楽しい人」「いくらでも話し続けられる相手」「あっという間に時間が過ぎてしまう相手」などいると思います。当然、同じ興味を持っていたり、気があったりという要素もあると思いますが、リアクションの部分も多いのではないかと思います。
「聞いてんだか、聞いてないんだか、分からない」的な人が相手だとなかなか話が続かないし、面白くないかもしれません。
これが、「英会話のレッスン」と特殊な部分かもしれません。「レッスンが楽しかった」「今日のレッスンはたくさん話した」とか言う、生徒の感想は極めて感覚的な物です。レッスン時間ごとに、「今日は○○回発言した」とか「今日は合計○○語話した」などどカウントしている生徒はいません。(恐らく)
実際には、生徒は、”yes”とか”no”,あるいは、単語だけで、”shopping”とか”sister”とか言っていただけかもしれません。それでも講師のリアクションが良ければ、「たくさん話した気がする」のです。
もし、リアクションが自然にとれる、誰とでもいくらでも話し続ける、と言うようなタイプの人であれば、あまり深く考えずに、そのままの自分のコミュニケーションスタイルでレッスンしてみてください。上手く出来るタイプの講師もたくさん見てきました。
反対に、自分はあまりそういうタイプではない、と思うのであれば、意図的に反応していきます。
- ほめる
- 驚く
- 同意する
- 少しだけ自分の事を話す
例えば、先程の例だと、
T(講師): What did you do last weekend?
S(生徒):I went shopping.
T: Great! Sounds nice. I like shopping too. Where did you go?
S: I went to Ginza.
T: Really? Ginza! Great! I love Ginza! Who did you go with?
S: With my sister.
T: Sister? You have a sister. That’s great! I have a sister too. We often go shopping together.
1)ほめる、2)驚く、3)同意する、4)自分の事を少し話す、など、ある程度自分でリアクションのパターンを決めておきます。「ほめる」事と同様に習慣化してしまえば大丈夫です。この時に、決して「言葉だけの表面上のリアクション」にならずに、本当に生徒の発言に興味を持って、共感し反応していけば、自然と声のトーンや表情からも伝わっていくと思います。
リアクションの話をすると、「レッスンは生徒中心だから講師は話してはいけないと言われた」というような事を言う講師がいますが、英会話のレッスンで「コミュニケーション」の部分が一番大切な部分です。ここで「たくさん話した」「通じた」という満足感や達成感が得られればモチベーションが上がります。生徒中心とはそういう事です。機械的に講師発言量20%で生徒発言量80%なら、生徒中心と言う事にはなりません。
リアクションの取り方は色々なパターンがあるので、映画やドラマなど、あるいは実際に友人と話しているときなど、どのようなリアクションだとどんな感じ方をするのか、考えてみると面白いと思います。