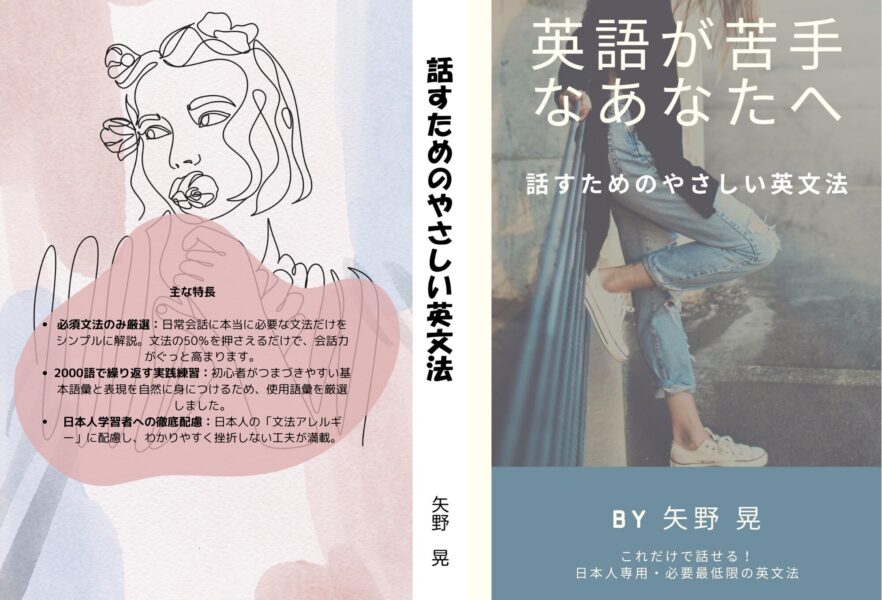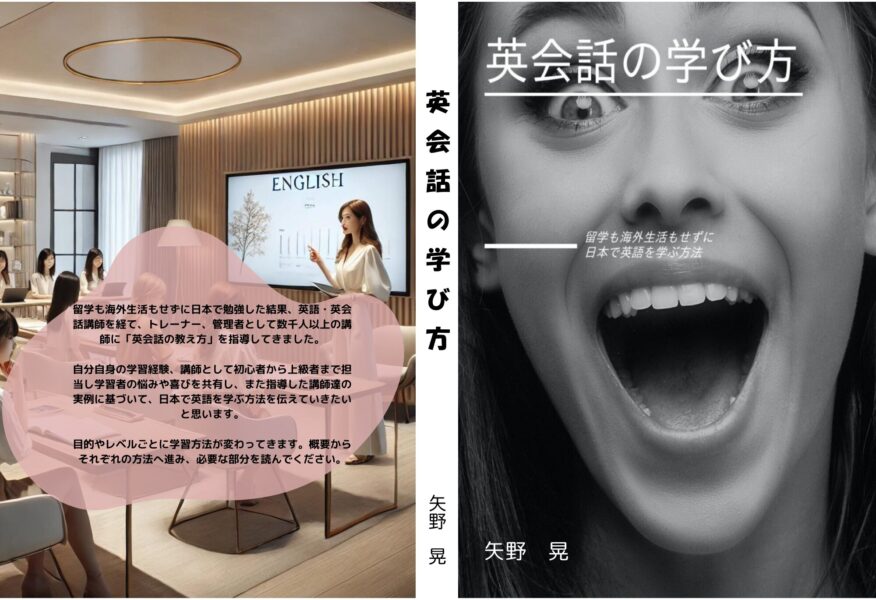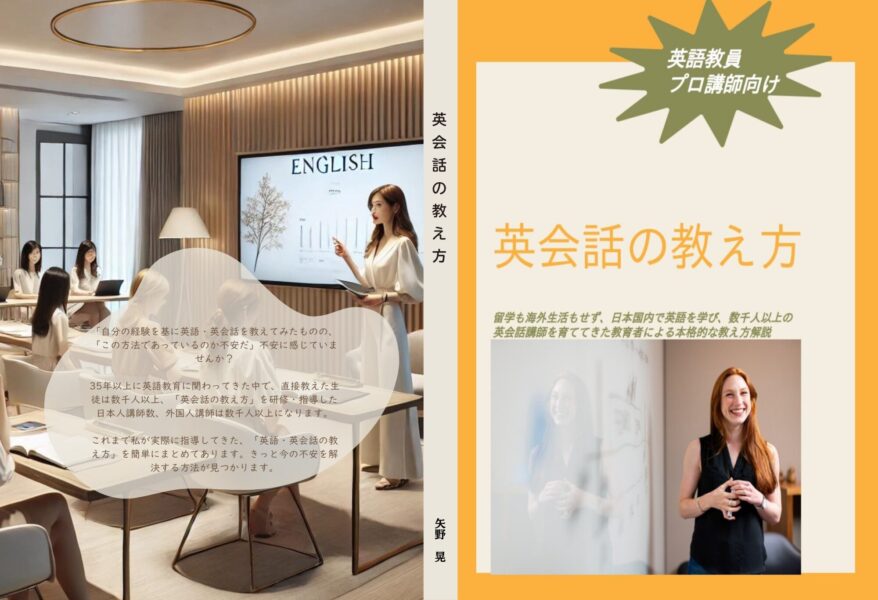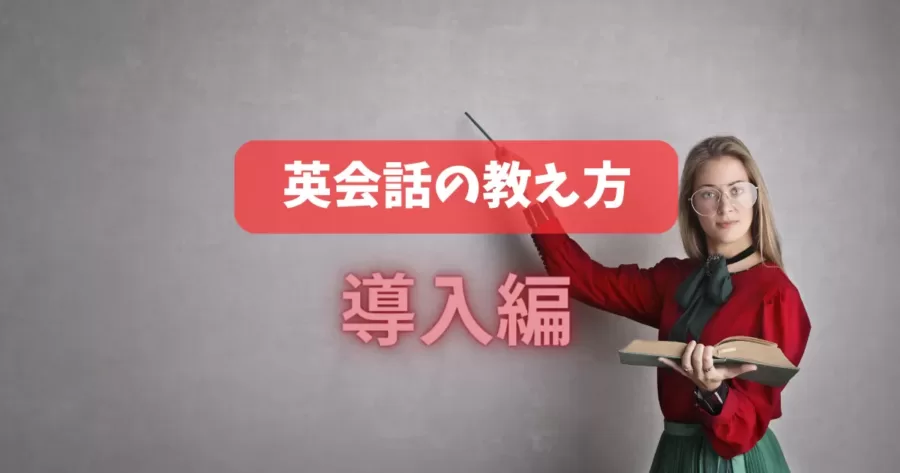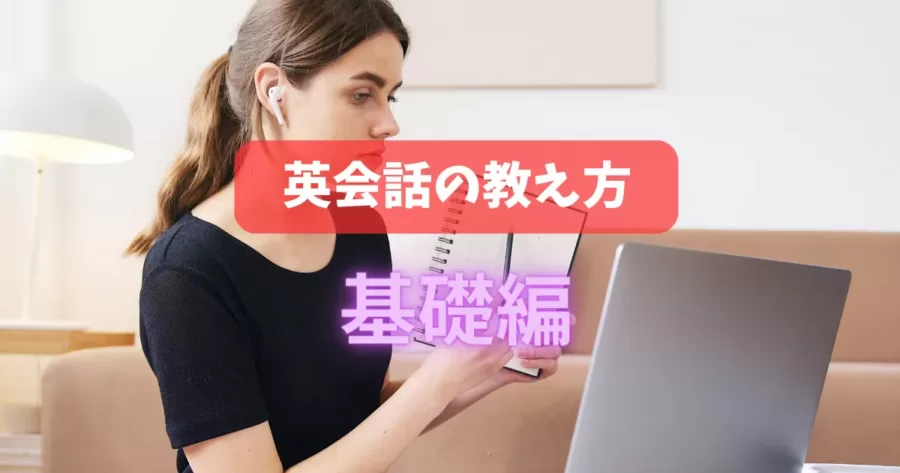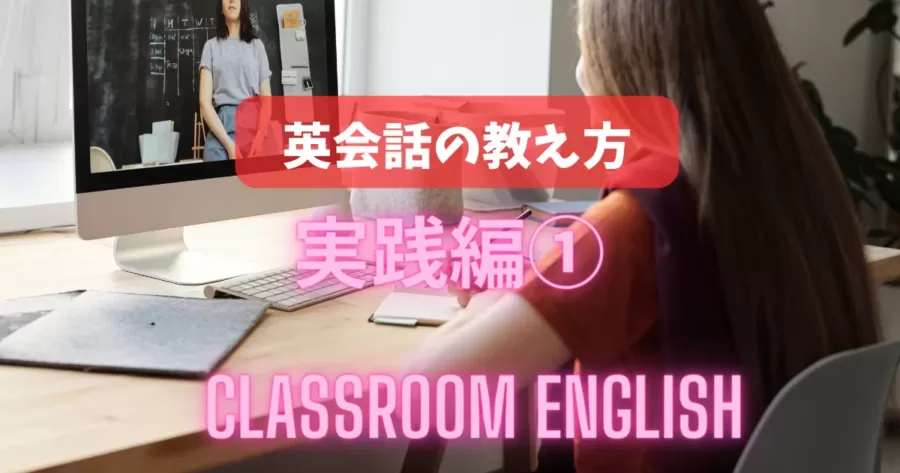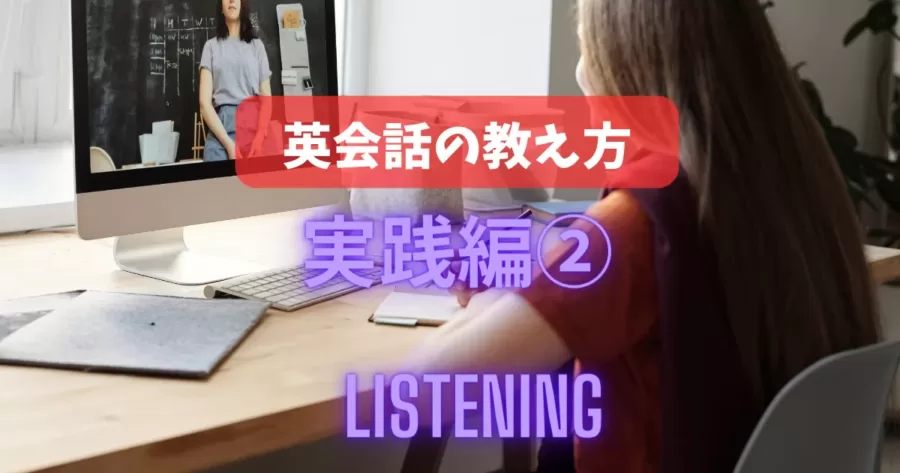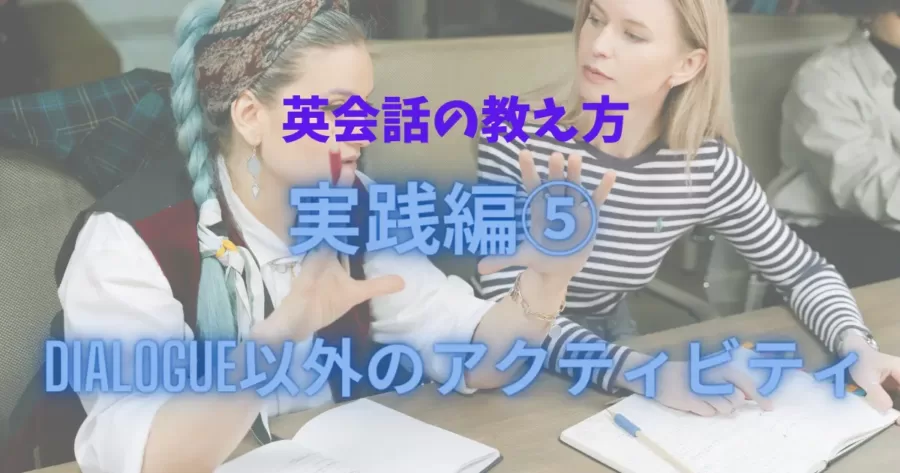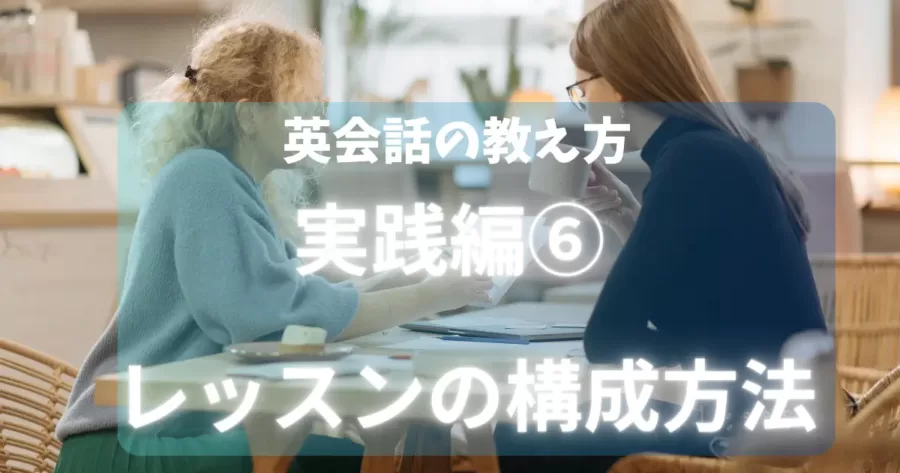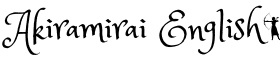「英語を教えてみたい」「英会話を教えてみたい」と思ってみたものの、いざ教えてみようとすると、「どうやって教えたらいいのか」「どんなテキストを使ったらいいのか」迷ってしまう。あるいは、実際に自分の経験を基に英語・英会話を教えてみたものの、「この方法であっているのか不安だ」、「生徒とうまくかみ合わない」などと不安に感じていませんか?
私は留学も長期間の海外生活を送ったこともありませんが、20代前半から英語・英会話を教え始め、その後英会話スクールで、講師トレーナー、教務課責任者、事業部長などを務めながら35年以上にわたり、英語教育に関わってきました。その間に直接教えた生徒は数千人以上、「英会話の教え方」を研修・指導した日本人講師数千人以上、同様に研修・指導した外国人講師数千人以上になります。
これまで私が実際に指導してきた、「英語・英会話の教え方」を簡単にまとめてあります。「英語・英会話の教え方」に関しては、ある「一つだけの正解」はありません。あくまでも、一つの例として参考にしてください
1. ドリルとは

ドリルとは機械的な口頭練習の事です。オーディオ・リンガルメソッドと言う教え方で良く使われていた手法です。1時期はひたすらドリルをするスクールもありましたが、最近はあまり人気がないようです。
とは言え、文型や表現などを定着させるには非常に有効な方法なので原則は覚えていた方が良いでしょう。特に一般的な大人の日本人学習者に教える場合は、レッスンの中で、必要に応じて短時間使用すると効果的です。
1) ドリルの目的
ドリルの目的は、「習慣化」です。有名な例だと、「パブロフの犬」です。「ベルを鳴らし犬に餌を与える」事を繰り返すと、ベルを鳴らすだけで犬がよだれを垂らす現象です。
要するに「ベルの音」と「餌を貰う」と言う2つの事柄が、繰り返しのどこかの過程で結びつくのです。
その段階で「ベルの音」を聞くと無意識のうちに反応するようなる。「条件反射」ですね。

語学学習におけるドリルとは、文型や語彙・表現が、無意識に使えるようになるまで訓練をするという練習方法です。特に一般的な学校教育を受けた日本人学習者には有効な練習方法になります。英語の授業で文法や語彙を詰め込んだものの、あくまでも「知識のための英語」として学んできているために、コミュニケーションで実践できるほどのProductive levelは無いというタイプに効果があります。
簡単に言ってしまうと、「頭の中で文の形を変える、組み立てる」のに掛かる「プロセスの時間を短縮する」と言う事です。
分かりやすい例を出すとこんな具合です。
例:過去形
- T(講師):What did you do last weekend?
- S(生徒):I ….. えーっと…
この「えーっと」の間に、生徒の頭の中ではこんな作業をしています。
「えーっと、買い物に行ったんだから、shoppingで、動詞はなんだったっけ? あ、go shopping か、last weekendは先週末だから、過去形にして….、goの過去形は、あ、不規則動詞だから、wentだったっけ?」
このようなプロセスを経て、数分後に言葉が発せられます。
例えば、中学校の期末テストで、
「次の文の( )内の動詞を適切な形に変えなさい」
I (go) shopping last weekend.
と言うような問題が出たのなら、先程のプロセスで全く問題ありません。1分掛けて答えれば正解できます。正解できれば英語が得意と言う事になります。
しかしながら、残念な事にコミュニケーションの場では、これでは間に合わないのです。
なので、先程の「えーっと…」のプロセスをせいぜい2-3秒程度に抑えられるように短縮していく必要があります。
この「頭の中のプロセルに掛かる時間を短縮する」事がドリルの目的であり、Receptive LevelからProductive Levelへ変換させていくうえで有効な手法の一つになります。
2) ドリルの行い方
それでは、実際にどのようにドリルを行うのか、説明します。
先程の「パブロフの犬」をもう一度思い出してください。「ベルを鳴らし犬に餌を与える」事を繰り返すと、ベルを鳴らすだけで犬がよだれを垂らす現象です。ベルを鳴らすという事を繰り返すと、「ベル=餌」という感覚が定着し、ベルを聞くとすぐによだれが出るようになるという事です。
ドリルをする場合も、この「ベル」に当たる部分が必要になります。何か反応させるための「合図」です。
語学学習でドリルを行う場合、この「合図」の事を”Cue”と言います。
“Cue”は講師が出します。講師が”Cue”を出すと、生徒が反応します。そして、その「生徒の反応」を、講師が「確認」します。つまり、こんな流れになります。
- T(講師):Cue
- S(生徒):Respond
- T(講師):Reward
Rewardと言うのは「餌」ですね。例えば、犬に「お手」を教えるのであれば、犬が上手く出来たら「餌」を与えます。そういう意味の「餌」です。
具体例で説明します。
- T:I go shopping. “Yesterday.”
- S:I went shopping yesterday.
- T:Good.
こんな感じですね。
Rewardと言っても実際に、お菓子のような「餌」を与えるわけではなく、”Good”と言うだけです。また、文字で説明するのは難しいですが、講師の「I go shopping. “Yesterday.”」部分ですが、実際には、I go shopping.の部分と、”Yesterday”の部分の間にある程度の間を取って、I go shopping.が基になる文で、”Yesterday”が”Cue”であることが分かるように進めます。
これが基本形ですが、ドリルの目的は「頭の中のプロセルに掛かる時間を短縮する」事です。
T:I go shopping. “Yesterday.” に対して、S:I went shopping yesterday.の答えが返ってくるまで、最初のうちは時間が掛かってしまいます。「時間を短縮する」事が目的なのであまり時間が掛かってしまっては効果が半減してしまいます。そのため、正解をもう一度ナチュラルスピードでリピートさせる事で、テンポが落ちないようにしていきます。
- T:I go shopping. “Yesterday.”
- S:I went shopping yesterday.
- T:Good. I went shopping yesterday.
- S:I went shopping yesterday.
- T:I watch TV. “last night”
こんな感じで、ナチュラルスピードでリピートさせた後に、次のCue”を出して続けていきます。このリピートのさせ方、タイミング、Cueの出し方が講師の腕の見せ所です。上手い講師は、ほんの数分で非常に効果的なドリルをする事が出来ます。反対に下手な講師はどれだけ時間を掛けても効果的なドリルが出来ません。このあたりは文字で説明するのが難しく、実際に良いレッスンを見る事が出来れば参考になると思います。
2. ドリルの種類

ドリルには色々な種類がありますので、定着させようとしている文型や語彙・表現によって効果的なタイプを選んでいきます。
1) Substitution Drills
恐らく最も一般的なドリルだと思います。文の一部分をSubstituteしていくドリルです。ただし、気を付けないと、あまり意味のないドリルになってしまうので注意が必要です。
まず、悪い例から、(ドリルの種類を説明するのが目的なので、”Reward”部分は割愛します。)
 講師
講師He likes music. “apples”
 生徒
生徒He likes apples.
 講師
講師Good. “hamburgers”
 生徒
生徒He likes hamburgers.
 講師
講師Good. “spring rolls”
 生徒
生徒He likes ………
- T:He likes music. “apples”
- S:He likes apples.
- T:Good. “hamburgers”
- S:He likes hamburgers.
- T:Good. “spring rolls”
- S:He likes ………
Substitution drillsなので、likeの「目的語」部分をsubstituteしています。その意味では正しいドリルです。もし「発音練習」したいのなら、これでも問題ありません。ただし、「文型」のためのドリルだとすると、ほとんど効果がありません。ドリルの目的は「頭の中のプロセルに掛かる時間を短縮する」事なので、ターゲットとしている「文型」の教えたいポイントに意識を向けさせ、頭を使わせないと効果が得られません。
もし三人称単数現在、いわゆる「3単現のs」を練習したいのなら、生徒が”s”を付けるか付けないかを毎回考え、その考える時間を短縮するための訓練をする必要があります。
また、語彙・表現として「目的語」の部分を練習させたいのだとしても、講師が口頭で”apples”とか”hamburgers”と言う”Cue”を出しても、生徒は何も考えずに言われたことをそのまま繰り返しているだけです。
”apples”や”hamburgers”のように、自分が知っていいる単語なら問題ないのですが、”spring rolls”のように知らない単語を言われてしまうと何も出来なくなってしまいます。つまり、知っている単語はリピートできるけど、知らない単語は意味も分からないしリピートもできないとなってしまい、全く効果がありません。
「3単現のs」を練習したいのなら、「3単現のs」に意識を集中させます。つまり「3単現のs」以外を極力シンプルにして、”s”を付けるか付けないかだけに意識を向けさせます。
 講師
講師I like music. “We”
 生徒
生徒We like music.
 講師
講師Good. “Nancy”
 生徒
生徒Nancy likes music.
 講師
講師Good. “Nancy and Tom”
 生徒
生徒Nancy and Tom like music.
- T:I like music. “We”
- S:We like music.
- T:Good. “Nancy”
- S:Nancy likes music.
- T:Good. “Nancy and Tom”
- S:Nancy and Tom like music.
これだと、生徒は毎回”s”を付けるか付けないかだけに集中しています。
Substitution Drillsは非常に効果的なドリルですが、どの部分の何のためにSubstituteするのか、しっかりと考えてドリルを組み立てないと、労力のわりに効果の得られないドリルになってしまいます。
これでSubstitution Drillsがどういうものかわかって頂いたと思いますが、少し続きがあります。ドリルの目的は「頭の中のプロセルに掛かる時間を短縮する」事です。まず、最初は一番シンプルな形で練習し、「即答」出来るようにします。「即答」がポイントです。「考える時間を短縮する」のが目的なので、「考えて文を組み立てている」ような状態では練習が不十分です。
ただし、よほどCueの出し方やRewardのタイミング、リピートのスピードを間違えない限り、この一番シンプルなパターンで出来るようになるはずです。「即答」できるようになったら、次の段階へ進みます。「即答」出来る状態で延々と続けても、生徒が飽きてしまい集中力が落ちてしまいます。
次の段階とは、「ドリルの難易度」を上げていく事です。今の段階は、動詞も目的語もLikeとmusicに限定し、主語を変える事によって、”s”を付けるか、付けないか、選ばせる作業をしています。これが出来るようになったら、動詞や目的語もsubstituteしていきます。
 講師
講師I like music. “We”
 生徒
生徒We like music.
 講師
講師Good. “Nancy”
 生徒
生徒Nancy likes music.
 講師
講師Good. “Nancy and Tom”
 生徒
生徒Nancy and Tom like music.
 講師
講師Good. “play tennis”
 生徒
生徒Nancy and Tom play tennis”
 講師
講師Good. “His father”
 生徒
生徒His father plays tennis.
- T:I like music. “We”
- S:We like music.
- T:Good. “Nancy”
- S:Nancy likes music.
- T:Good. “Nancy and Tom”
- S:Nancy and Tom like music.
- T:Good. “play tennis”
- S:Nancy and Tom play tennis”
- T:Good. “His father”
- S:His father plays tennis.
これも出来るようになれば、副詞句を追加し文の長さを長くしていきます。
 講師
講師Good. “take a walk in the morning”
 生徒
生徒His father takes a walk in the morning.
 講師
講師Good. “my sister and I, every evening”
 生徒
生徒S:My sister and I take a walk every evening.
この場合の注意点ですが、追加していく動詞句や副詞句、”take a walk”や”every evening”は必ず既存のフレーズを使います。あくまでもターゲットは「3単現のs」です。意識をそこに向けつつ、ドリルをchallengingにするために、フレーズを足しています。足したフレーズの意味が分からない状態で口だけ動かしていても意味はありません。
いったん、ここで大切なポイントをまとめます。(Substitution drillに限らず、ドリルの組み立て方全般のポイントです。)
- ドリルは、教えたいポイントで生徒に考えさせる。
- まず一番シンプルな形で、教えたいポイントにのみ意識を集中させる。
- 「即答」出来るようになったら少しずつ難易度を上げていく。
2) Transformation Drills
Transformation Drillsとは「形を変える」ドリルです。主には、文型を変えるパターンが多くなります。
例によって悪い例から、
 講師
講師Did you watch TV yesterday? “go shopping”
 生徒
生徒Did you go shopping yesterday?
 講師
講師Good. “see a movie”
 生徒
生徒Did you see a movie yesterday?
 講師
講師Good. “do your homework”
 生徒
生徒Did you do your homework yesterday?
- T:Did you watch TV yesterday? “go shopping”
- S:Did you go shopping yesterday?
- T:Good. “see a movie”
- S:Did you see a movie yesterday?
- T:Good. “do your homework”
- S:Did you do your homework yesterday?.
そもそも、これTransformationではないです。Substitution Drillsですね。しかも、ただフレーズを入れ替えているだけで、生徒は何も考えていません。
Transformation drillsは「文の形を変えるドリル」です。文型を変える時に何かしらの作業が必要になり、その作業で間違えやすい/時間が掛かりやすい、と言うような問題が発生する場合に効果的です。
この場合は、ターゲットが過去の疑問文です。肯定文で使用する動詞の過去形が疑問文や否定文にすると原型に戻す必要があります。そこで間違える可能性が高いのでTransformation Drillsでトレーニングしていきます。
(主語をTheyにしてあるのは、youだと混乱しやすいからです。過去形の場合、he/sheでも問題ありません)
 講師
講師They went shopping yesterday. “Question”
 生徒
生徒Did they go shopping yesterday?
 講師
講師Good. “They saw a movie yesterday”
 生徒
生徒Did they see a movie yesterday?
 講師
講師Good. “They did their homework yesterday”
 生徒
生徒Did they do their homework yesterday?
- T:They went shopping yesterday. “Question”
- S:Did they go shopping yesterday?
- T:Good. “They saw a movie yesterday”
- S:Did they see a movie yesterday?
- T:Good. “They did their homework yesterday”
- S:Did they do their homework yesterday?
少し端折ってしまいましたが、難易度の調整はしっかりとしてください。例えばこの例であれば、
- 規則動詞:watch TV, study English, play baseball など
- 不規則動詞:go shopping, see a movie など
- 代名詞などその他の要素が入るもの
関係代名詞などもTransformation Drillsが有効です。Cueは長くなりますので中級者向けです。
 講師
講師“I have a friend.” “She speaks Italian.”
 生徒
生徒I have a friend who speaks Italian.
 講師
講師Good. ”She is a woman.” “I met her at the party.”
 生徒
生徒She is a woman I met at the party.
 講師
講師Good. “The boy was her brother. He played my guitar.
 生徒
生徒The boy who played my guitar was her brother.
 講師
講師Good. “This is the book. My girlfriend was talking about.”
 生徒
生徒This is the book my girlfriend was talking about.
- T:“I have a friend.” “She speaks Italian.”
- S:I have a friend who speaks Italian.
- T:Good. ”She is a woman.” “I met her at the party.”
- S:She is a woman I met at the party.
- T:Good. “The boy was her brother. He played my guitar.
- S:The boy who played my guitar was her brother.
- T:Good. “This is the book. My girlfriend was talking about.”
- S:This is the book my girlfriend was talking about.
もし音だけのCueでドリルする事が難し過ぎるようであれば、まずホワイトボードやスクリーンで文字を見せた状態でドリルし、「即答」出来るようになったら、音だけのCueにすることで難易度の調整が出来ます。
3)イラストや写真を使ったドリル
初心者向けの語彙・表現に有効な方法です。ドリル自体は簡単ですが、分かりやすいイラストや写真を探す方が大変かもしれません。今はインターネットでフリー素材がたくさんあるので比較的見つけやすいのだと思います。
悪い例からです。
 講師
講師イラストを見せる
 生徒
生徒Listen to music
 講師
講師イラストを見せる
 生徒
生徒take a shower
- T:イラストを見せる
- S:Listen to music
- T:イラストを見せる
- S:take a shower
これだけ見ていても、良い例なのか悪い例なのか分からないと思います。流れはこれでOKです。写真やイラストを見せて、適切な語彙・表現を言ってもらうというドリルになります。
問題は、このCueになっているプロップです。


❌ 悪い例
⭕️ 良い例
違いが分かりますか?
「悪い例」には文字が入っています。これをCueとして生徒に見せても、生徒は何も考えずに、”Listen to music”と文字を読むだけです。頭を使っていないので直ぐに忘れてしまいます。反対に「良い例」は文字が入っていません。このイラストを見て、これを表現するフレーズを自分で思い出さないといけません。この「表現を思い出す時間」を短縮するのがドリルの目的です。
イラストや写真を使ったドリルは、レベルにもよりますが、比較的単純なので「即答」できるようになったら、直ぐに難易度を上げていきます。イラストをCueにする事は変わらないのですが、イラストに加えて講師が「質問」していきます。このイラスト(良い例)を見せながら、
 講師
講師”What did you do yesterday?#

 生徒
生徒I listened to music yesterday.
 講師
講師Good. “What do you like to do on weekend?”

 生徒
生徒I like to listen to music.
このように、ドリルは必ず一番シンプルなドリルからChallengingな物へと難易度の調整をしていきます。いきなり難しいドリルから始めてしまうと、「考えるプロセス」にかかる時間が非常に長くなってしまいます。効率の悪いドリルになってしまうので気を付けてください。
4)組み合わせ
ドリルのパターンはターゲットにより適切な物を選んでいきます。必ずしも一つのパターンに限定する必要ありません。特に中級レベルになると構文的に複雑な物が多くなってくるので、複数の種類のドリルを組み合わせた方が効果的になります。
例えば、仮定法の場合、
- ① Formのドリル:Substitution
-
仮定法過去完了などは構文的に難しいのでまずシンプルに構文の練習をしてしまいます。(動詞句は生徒が必ず知っている表現を使います。)
- ホワイトボードやスクリーン上に文のフォームを出して置きます。
- If I 〇〇〇〇, I ○○〇〇yesterday.
 講師
講師”know his number”, “call him”
 生徒
生徒If I had known his number, I would have called him yesterday.
 講師
講師Good. “have time”, “join you
 生徒
生徒If I had time, I would have joined you yesterday.
 講師
講師Good. “know she is coming”, “not go to the party
 生徒
生徒If I had known she was coming, I would not have gone to the party yesterday.
- T:”know his number”, “call him”
- S:If I had known his number, I would have called him yesterday?
- T:Good. “have time”, “join you
- S:If I had time, I would have joined you yesterday.
- T:Good. “know she is coming”, “not go to the party
- S:If I had known she was coming, I would not have gone to the party yesterday.
生徒はフォーム、主に動詞の活用に集中して文型の練習をすることが出来ます。「即答」できるようになったら、同じ例文を使い、意味を考えさせるドリル行います。
- ② 意味を考えるドリル:Transformation
 講師
講師”I didn’t know his number”, “so I didn’t call him yesterday”
 生徒
生徒If I had known his number, I would have called him yesterday.
 講師
講師Good. “I didn’t have time yesterday”, ”so didn’t join you yesterday.”
 生徒
生徒If I had time, I would have joined you yesterday.
 講師
講師Good. “I didn’t know she was coming”, “so I went to the party yesterday.”
 生徒
生徒If I had known she was coming, I would not have gone to the party yesterday.
- T:”I didn’t know his number”, “so I didn’t call him yesterday”
- S:If I had known his number, I would have called him yesterday?
- T:Good. “I didn’t have time yesterday”, ”so didn’t join you yesterday.”
- S:If I had time, I would have joined you yesterday.
- T:Good. “I didn’t know she was coming”, “so I went to the party yesterday.”
- S:If I had known she was coming, I would not have gone to the party yesterday.
更に仮定法過去を加えたり、仮定法過去と仮定法過去完了をミックスさせると、かなりChallengingなドリルになります。
3. ドリルの注意点

最後にドリルの注意点をまとめます。
- ドリルの目的を忘れない
- ドリルのフローを習慣化させる
- タイミングが命
- 教えたいポイントで考えさせる
- 易しいドリルから難易度の高いドリルへ
- 無駄に時間を掛け過ぎない
- ① ドリルの目的を忘れない
-
ドリルの目的は、「頭の中で文の形を変える、組み立てる」のに掛かる「プロセスの時間を短縮する」と言う事です。コミュニケーションで使えるProductive Levelに昇華させるためには、「即答」出来るように練習する必要があります。「時間の短縮」が目的です。
- ② ドリルのフローを習慣化させる
-
ドリルはそのターゲットにより、色々なパターンを選んでいきますが、ドリルのフロー/行い方は常に一緒です。
- T:Cue
- S:Respond
- T:Reward
そして、Rewardの後に正しいセンテンス/フレーズをナチュラルスピードでリピートさせる過程を忘れないように。このリピートでスピードを整えていきます。
- ③ タイミングが命
-
Cueを出すタイミング、Rewardのタイミング、リピートのタイミングとスピード、次のCueを出すタイミング。ドリルの精度は、そのタイミングですべて決まってしまいます。あくまでも自分の求めるタイミングで進めましょう。
- ④ 教えたいポイントで考えさせる
-
ドリルの目的は、「時間の短縮」ですが、「時間」とは文を組み立てたり、フレーズを選ぶための時間を指します。その「時間」を短縮するのが目的なので、「教えたいポイントで考えさせる」事をしないと効果が得られません。
- ⑤ 易しいドリルから難易度の高いドリルへ
-
ドリルは「易⇒難」が大原則です。必ず最もシンプルなドリル、教えたいポイントだけに集中できるドリルからスタートし、「即答」できるようになったら、難易度を上げていきます。いきなり難しいドリルからスタートすると「考える時間」が掛かり過ぎて効果的なドリルになりません。また、グループレッスンの場合、レベル差が顕著に出てしまいます。難しいドリルからスタートすると、「出来る人は出来る、出来ない人は出来ない」状態に陥ってしまいますので気を付けてください。
- ⑥ 無駄に時間を掛け過ぎない
-
ドリルは非常に効果的な練習ですが、「飽きやすい」という弱点もあります。レッスンの大半をドリルに費やしてしまうようなレッスンだと生徒が飽きてしまいます。短時間で集中的に行いましょう。生徒にしっかりと考えさせ、難易度の調整さえしていれば、それほど飽きる物でもありません。
反対に練習量が少なすぎる場合もあります。講師が「こんな単純な練習ばかりじゃ飽きるだろう」と思ってしまう場合です。ドリルに限らずですが、必ず「生徒の頭で考える」癖をつけてください。初心者レベルのレッスンを受けている人は、初心者レベルで学ぶ内容が難しいのでレッスンを受けています。講師になる人の英語レベルで考えてしまっては的外れです。レッスン中実際に生徒の表情をよく見ていれば分かると思います。けっして「簡単すぎる」事はないはずです。