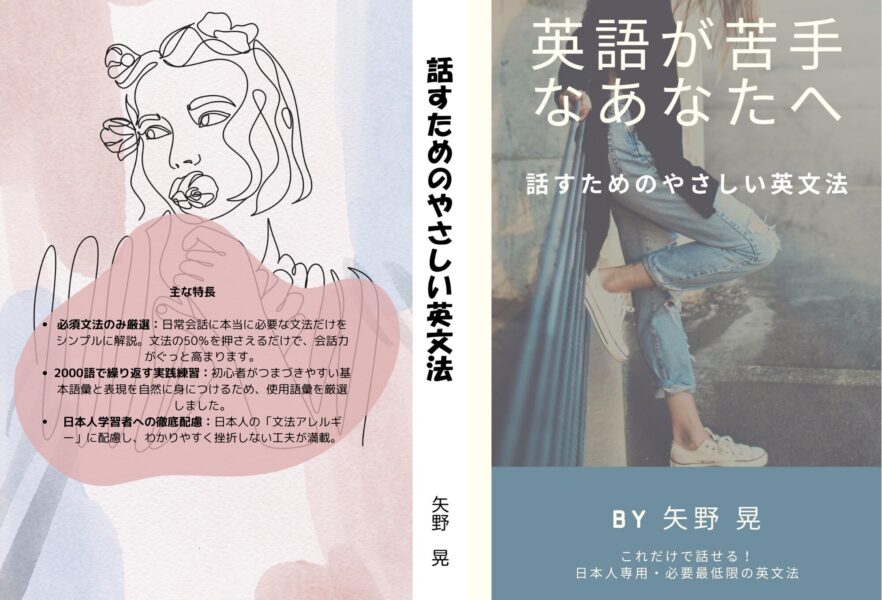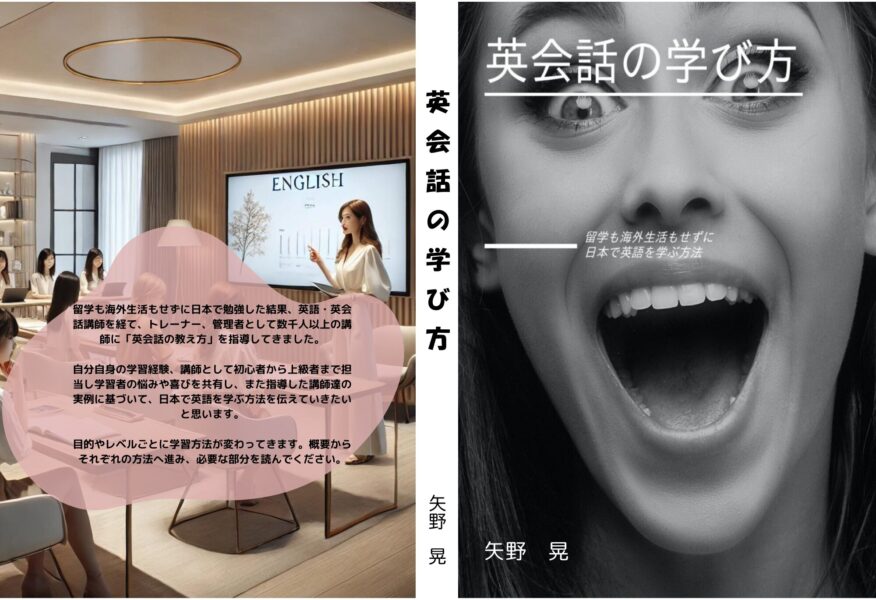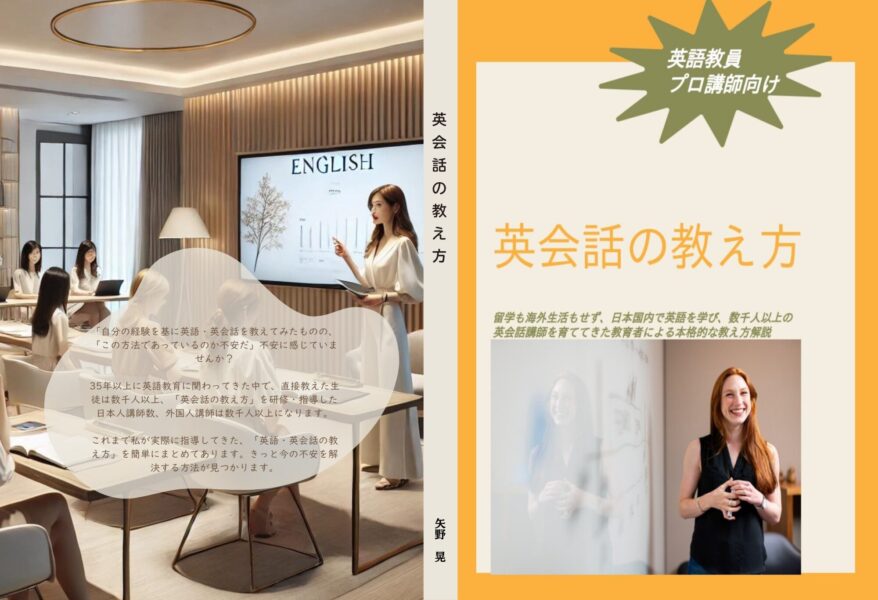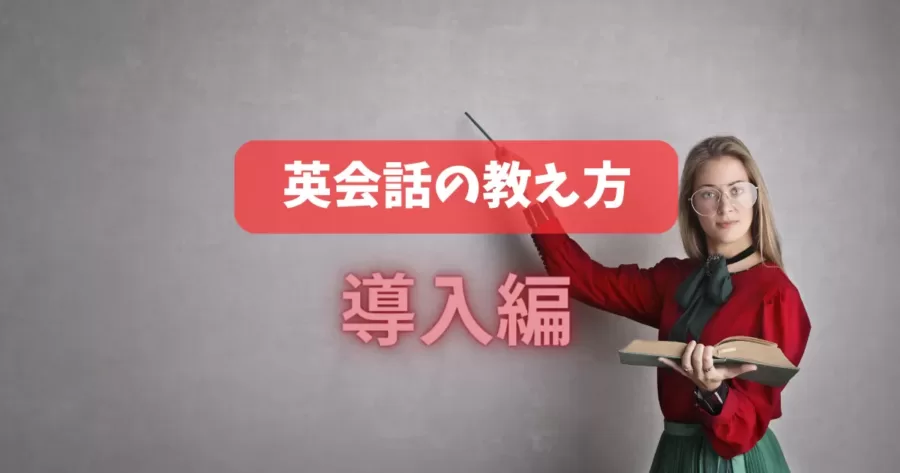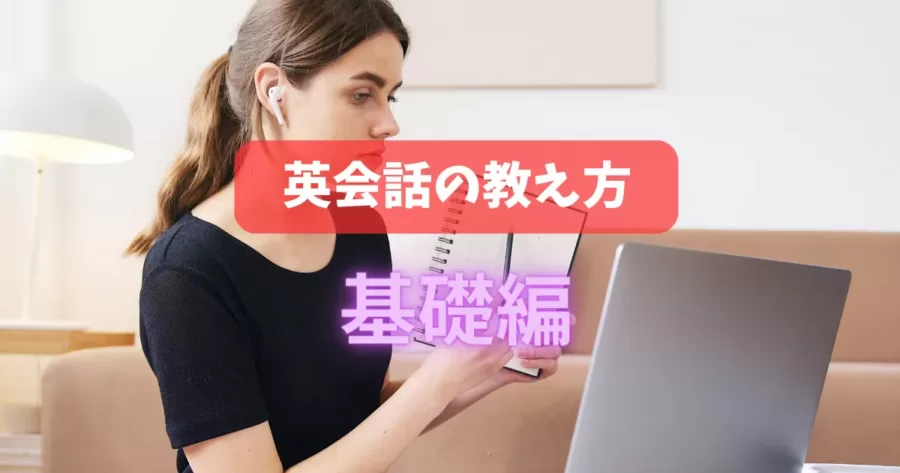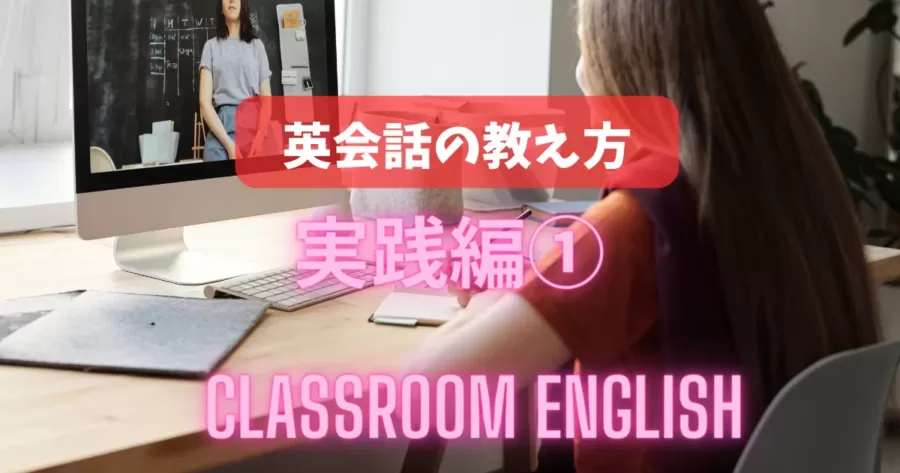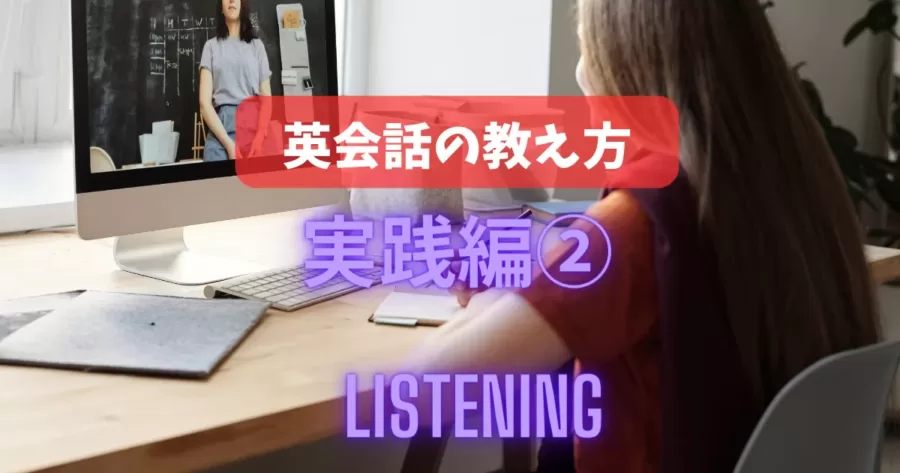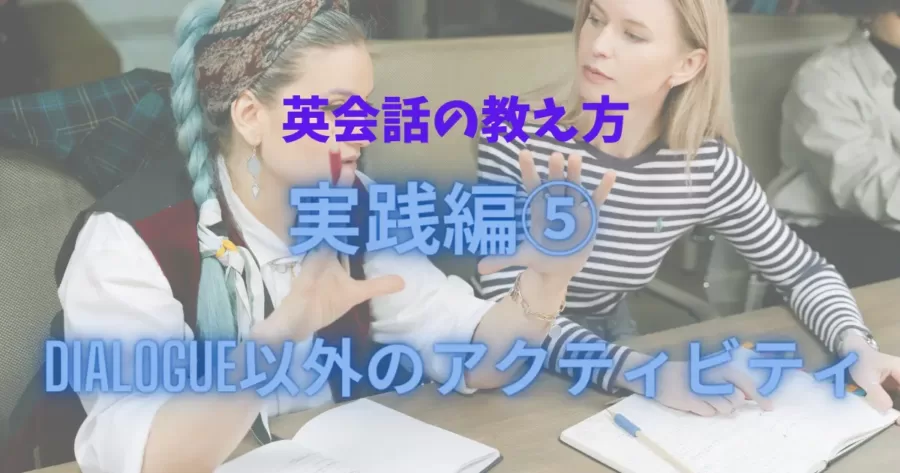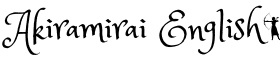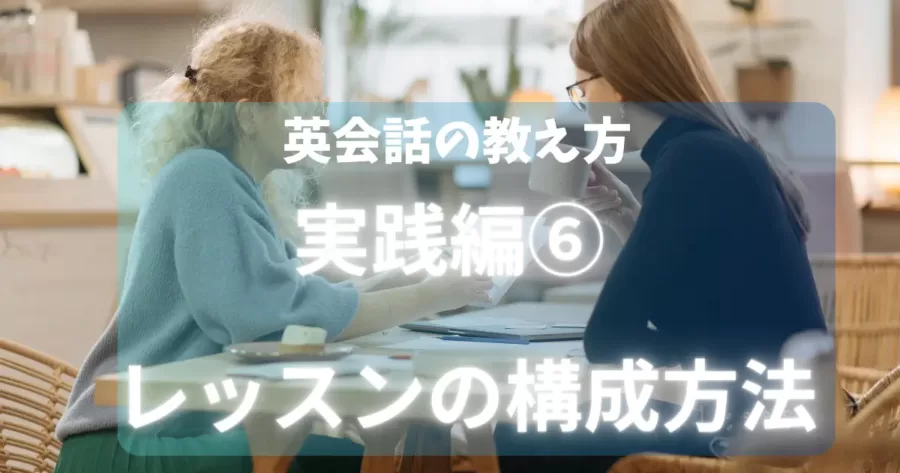ここまで、Listening、Drill、 Dialogueなど、各アクティビティの教え方を説明して来ました。ここでは、それらの各アクティビティを組み合わせて、一つのレッスンをどのように構成していくのかを説明します。
「英会話のレッスン」と言うと、「なんとなく楽しく話していればO Kなんじゃない? 別にレッスンの構成なんか考える必要なんてないと思う!」と思うのであれば、それで構いません。結局、週1回のレッスンだけで、英語が話せるようになる訳ではありませんので、レッスンが楽しくて、レッスン外で英語を勉強する時間が増えれば自動的に英語力は上がります。全く問題ありません。独自の方法でレッスンを続けてください。
この記事は、「少しでも効果的な教え方が出来ないか」「限られたレッスン時間を有効に使えないか」と真剣に考えている講師に向けて書いています。異なる価値観や考え方の講師を説得しようとする気持ちは一切ありませんので、他の記事を参考にしてください。
それでは本題に入ります。
1. レッスンの構成の仕方

まず、何点か基本的な考え方があります。レッスンで使用するテキストには色々なタイプがあります。また、レッスン時間やスケジュール、年間カリキュラムの制限があると思うので、進度や時間の使い方に工夫が必要になると思います。その中で押さえておくべき基本的な考え方が以下になります。
- ReceptiveなアクティビティからProductiveなアクティビティへ
- 簡単な内容からChallengingな内容へ
- レッスンに一貫性を持たせ、T/L(大切なポイント)を繰り返し練習する
簡単に説明します。
- ReceptiveなアクティビティからProductiveなアクティビティへ
-
2点目の「簡単な内容からChallengingな内容へ」と重なりますが、自然な流れを大切にすべきです。インプットしてから、アウトプットするのが自然な流れです。心理的な負荷をかけすぎないようにする必要があります。具体的な方法は後述しますが、受動する行動から能動的な行動へと言う流れを意識してください。
- 簡単な内容からChallengingな内容へ
-
やはり自然な流れを大切にするために、「簡単な内容からChallengingな内容へ」と言う流れを意識してください。外国語をレッスンを受けている生徒は、講師の想像以上に不安に感じています。「難しい!」「出来ない!」と言う感情は生徒を萎縮させてしまいます。レッスンの初めからいきなり難しいアクティビティを行なってしまうと、生徒間のレベル差が発生し、またテンポの悪い、生徒が沈黙する時間の長いレッスンになってしまいます。
- レッスンに一貫性を持たせ、T/L(大切なポイント)を繰り返し練習する
-
「英会話の教え方 基本編」や「英会話の教え方 導入編」で説明したように、Productiveレベルの英語力を養うためには、反復練習が必須です。ただし、レッスン全般で機械的な反復練習を繰り返したのでは生徒の学習意欲を削いでしまいます。タイプの異なる様々なアクティビティを通して無意識のうちに反復練習が出来ることが理想的な流れになります。
2. 具体的な構成方法

これまで、「Listening」「Drills」「Dialogue」「Dialogue以外のアクティビティ」とそれぞれのアプローチ方法を個別に見てきました。
これらを、「易⇨難」あるいは「Receptive⇨Productive」と言う流れに構成していきます。
ある意味、このまんまですね。
Receptiveなアクティビティ:T/Lの導入が目的
シンプルなProductiveなアクティビティ:T/Lの機械的な練習
Productiveなアクティビティ:Contextの中でT/Lを使う練習
Productiveなアクティビティ:Contextの中でT/Lを使う練習
テキストの種類にもよりますが、「Listening」がないテキストもあると思います。その場合は次のような流れになります。
Receptiveなアクティビティ:T/Lの導入が目的 (Listeiningの代用として使用)
シンプルなProductiveなアクティビティ:T/Lの機械的な練習
Productiveなアクティビティ:Contextの中でT/Lを使う練習
Productiveなアクティビティ:Contextの中でT/Lを使う練習
要するに、「Dialogue」をReceptiveなアクティビティ、且つ、Productiveなアクティビティとして使って行きます。
テキストの構成は様々なので、あまり厳密に考える必要はありません。「易⇨難」そして「Receptive⇨Productive」の流れが出来ていれば問題ありません。
基本的な流れはこれで良いのですが、実際のレッスンには多少プラスする事があります。
- Warm Up
- Closing
簡単に説明します。
- Warm Up
-
レッスン開始直後からいきなり、「本題」に入るのは少し無理があります。これは初心者に限った事ではありません。大人の学習者の場合、「頭の切り替え」が必要になります。週に1-2回の英会話レッスンですので、それ以外の時間は完全に「日本語の世界」です。仕事であったり、学校であったり、友人や家族とのコミュニケーションであったり、頭の中は完全に「日本語の世界」の支配下にあります。
いきなり「英語の世界」に入るのは難しいものです。「英語の世界」に入る準備練習として「簡単でストレスのない」時間を作ります。
それほど難しく考える必要はありません。生徒が皆話し慣れていることで少し英語を話せればOKです。
- 自己紹介
- 週末の出来事
毎週、受講者が変動するクラス形態の場合は、「自己紹介」で十分です。毎回同じような「自己紹介」をする訳なのでストレス無く話せます。
「週末の出来事」も同じですね。いつもレッスンの最初で「週末の出来事」を話すと言う意識があれば、心の準備が出来ているので、あまりストレスを感じることはありません。
レッスン時間にもよりますが、大体5分程度もあれば十分です。あくまでもリラックスして話せるように毎回同じ内容で構いません。
注意点:何点か注意点があります。
- 生徒の間違いをいちいち直さない
- 教えようとしない
- 時間をかけすぎない
簡単に説明します。
- 生徒の間違いをいちいち直さない
-
「リラックス」が目的ないので、ストレスを与えないようにします。あまり「間違い」を治してばかりいると、生徒が神経質になってしまいます。レッスンの本体では正確さを求める部分もありますが、このWarm upの段階では必要ありません。
- 教えようとしない
-
例えば、「週末の出来事」を話そうとして、言葉が出てこない場合もあります。その時に「1から10まで全部教えよう」とする必要はありません。あくまでも「リラックス」が目的です。レッスンの本体では、正確さを求める部分も出てきますが、Warm upの段階では必要ありません。
- 時間をかけすぎない
-
「週末の出来事」のように毎週話している内容は、生徒もだんだんと話しやすくなってくるので、時間が長くなりがちです。Warm upはあくまでもWarm upなので時間をかけすぎないようにしましょう。5分程度で十分です。
- Closing
-
レッスンの最初が「Warm up」なら、レッスンの最後が「Closing」です。あまり深く考える必要はありません。以下の内容をカバーします。
- Review
- HWや予習の指示
- 挨拶
- Review
-
文型でも表現でも単語でも構いません。当日のレッスンの中で大切なポイントを一つでも二つでも復習します。「説明」する必要はありません。何回かリピートしてもらえれば十分です。
- HWや予習の指示
-
「レッスンは予習を前提」に進めて行きます。次のレッスンで「どのページ」の「どのアクティビティ」を練習するのか、必ず伝え予習してきてもらいます。
- 挨拶
-
生徒全員に「レッスンの終了」を明確に伝える必要があります。これをしないと、いつまでも生徒が教室の中で「待機」してしまいます。
3. レッスンの構成例(50分レッスン)

例えば、1回50分のレッスンであれば、以下のように構成します。
自己紹介や週末の出来事など:「英語の世界」に入る準備練習として「簡単でストレスのない」時間を作ります。
T/Lの導入が目的のReceptiveなアクティビティ
T/Lの機械的な練習:フレーズ、センテンス単位の反復練習でT/LのFormを定着させる
T/LがContextの中で使用されている会話を練習する。
Controlled Practice:テキストの会話を練習し、T/LがContextの中で使われる状況を意識する
Freer Practice:T/Lを自分の言葉として使う練習をする
Controlled Practice:テキストの会話を練習し、T/LがContextの中で使われる状況を意識する
Freer Practice:T/Lを自分の言葉として使う練習をする
Review、予習・復習の指示など
*それぞれのアクティビティーの教え方は既に説明済みですので、ここでは割愛します。
*初めてこの記事を読んだ方はこちらを先に読んでください。
4. レッスンの構成(具体例)
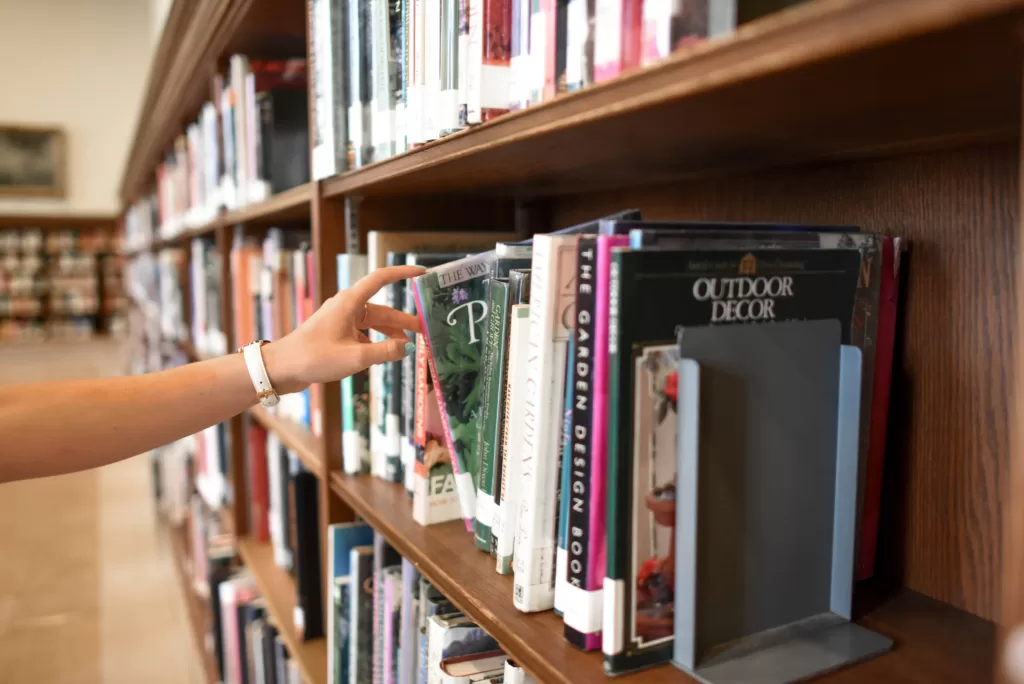
レッスンを教えた事のない人、あまり数多くのテキストを使った経験のない人にはイメージ湧きにくいかもしれませんので、一つ具体的な例を出します。NHKのラジオ講座をイメージしてみてください。
講座によってテキストの構成は異なりますが、一般的なラジオ講座のテキスト例は以下になります。
Lesson 1
Dialogue
Ricky : What time do you get up?
Becky : I get up at 6:00. How about you?
Ricky : At 7:30. What time do you leave home?
Becky : I leave home at 8:00.
Lesson 1
日本語訳
Ricky : 朝何時に起きるの?
Becky : 6時。リッキーは?
Ricky : 7時半だよ。何時に家出るの?
Becky : 8時。
今日のキーセンテンス
I get up at 6:00 in the morning.
- leave home
- eat breakfast
- take a shower
- brush my teeth
今日のキーセンテンス
私は朝6時に起きます。
- 家を出る
- 朝食を取る
- シャワーを浴びる
- 歯を磨く
もし、まだNHKラジオ講座を聞いた事がない場合は、まずテキストを購入して1回聞いてみてください。当然ながら、英会話スクールのレッスンとは、目的やレベル設定、対象生徒層も異なりますが、ここまでこの記事を読んでくれた方には、NHKラジオ講座の構成方法がよく理解できると思います。
先程の、「レッスンの構成例」に照らし合わせて考えます。ラジオ講座は15分程度なので当然ながら時間配分は異なります。
簡単な挨拶をして、各担当講師が自己紹介しています。数十秒程度の雑談をすることもあるかと思います。
メインダイアログを使用している事が多いようです。講師が簡単に状況説明して会話を聞きます。
キーフレーズやキーセンテンスの解説とリピート練習、簡単なSubstitution Drillをします。
Controlled:各パートをリピート練習した後、ロールプレイをします。
Freer:ドリルした内容をもとに、ダイアログの1部を置き換えます。更に講師が簡単な質問をして、自分のことについて話すこともあります。
Review、予習・復習の指示など
大体こんな流れになります。
ラジオ講座の場合、1回の放送時間も短いし、幅広いレベルや目的の生徒層を対象にしています。テキストを持っていない人やレベルの低い人も想定していますので、日本語で説明する部分も多くなる傾向があります。あくまでも「レッスンの構成の仕方」のイメージを掴むための例として考えてください。
このくらいの量のテキストがあれば、1時間程度のレッスンには十分です。これから英会話のレッスンを教えてみようという方は、是非ラジオ講座のテキスト1日分で1時間のレッスンを構成する練習をしてみましょう。これが出来るようになれば、どんなテキストを使用する場合にも応用できると思います。
5. まとめ

ここまで、レッスンの構成の仕方を説明してきました。
簡単にまとめますが、大切な事は、個々のアクティビティーの目的を理解した上で、それぞれの教え方をマスターする事です。各アクティビティーの教え方をしっかりと復習してください。
- ReceptiveなアクティビティからProductiveなアクティビティへ
- 簡単な内容からChallengingな内容へ
- レッスンに一貫性を持たせ、T/L(大切なポイント)を繰り返し練習する
- ReceptiveなアクティビティからProductiveなアクティビティへ
最初はよく理解できないかもしれません。
しかしながら、よく考えてレッスンを構成する準備を重ねて教えていく1年間と、何も考えずに教えていく1年間では、大きな経験の差が出てきます。その経験は必ず生きてきますので、よく考え抜いてしっかりと準備する習慣を身につけてください。